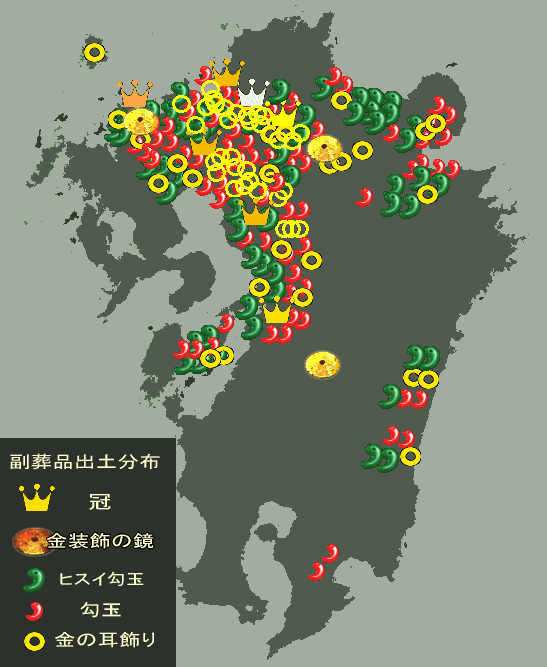◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
邪馬台国畿内説 Part335 ->画像>8枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/history/1521083390/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
邪馬台国論の鉄板、畿内説のスレです。
【骨 子】
・3世紀中葉には、古墳時代が開始していた。
・出現期古墳段階で、近畿中央部を中心に列島規模の政治連合が形成され始めていた。
・北部九州博多湾岸地域は、既にこの政治連合の傘下にあった。
ゆえに、倭女王卑弥呼の都があったのは畿内である。
邪馬台国論争ももう畿内で決着なのでロマンはありませんが
勝者の貫録を見せつつ、更なる真実を探求しましょう。
前スレ
http://2chb.net/r/history/1520782211/
◆0【 要 旨 】 ( >>2-12に各論、それ以下にFAQを付す )
纒向遺跡の発掘状況等から、ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ女性であったと考えられる。
その死亡時期は3世紀中葉とみられる。畿内に中国文化が急速に浸透する時期である。
これらを倭人伝の記事と対照すると、箸中山古墳の被葬者が倭人伝に記載ある曹魏に卑弥呼と呼ばれた人物であり、纒向が邪馬台国にあった倭女王の宮殿所在地であると同定できる。
2世紀の地球規模的寒冷化は、農業生産力を強化する社会的需要から指導的地位を占める析出集団の成長を強烈に促進し、弥生的青銅器祭祀を終息せしめ、高塚化した墳丘墓を現出させる。
換言すれば、弥生墳丘墓の巨大化が顕著な地域こそが、弥生社会に古墳時代へと向かう構造変化の著しい地域であり、3世紀に爆発的に広域化する萌芽期国家の中核である。自然環境変化に起因する社会構造変化が現象として纒向に凝集し結実したと言える。
倭人伝に記載された卑弥呼の活動期間に相当する庄内併行期は、畿内様式の土器が漸進的に北部九州に流入している時期であり、ことに那珂比恵地域への人口流入が急拡大していく。
博多湾貿易が対外交渉の主役に躍り出るこの時期には、西日本各地の人々が韓人や楽浪商人と直接交渉による交易をする段階となっている。
絶域であった日本列島が中華社会と二国間の国交を再開した時期、この外的刺激で最も変化の生じた地域こそが当時の倭国の中枢である。
倭人伝述べるところの、3世紀前半末に曹魏と通交した倭の女王はどこにいたであろうか?
それは桜井市纒向以外にありえない。 ◆1(女王所都)
奈良県桜井市に所在する纒向遺跡が2世紀末に人為的・計画的に建設された前代未聞の巨大祭祀空間であり、また北部九州を含む列島各地の文化を受容し融合し、そして全国に発信する中枢的な場であったことは、夙に知られている。(◆2,FAQ38参照)
現・纒向駅近くに東西軸上に複数棟連続して計画的に建築された大型建物群(4棟まで発見済み)は、3世紀前半のものと公式発表されている。
居館域は桜井線西側のみでも東西150m、南北100m前後の規模を持ち、大小それぞれ構造・機能を異にする複数の建物が方形の柵列に囲繞されており、重要な古道として知られる上つ道に接面している。これに比肩するものは、弥生時代に存在しないのは勿論のこと、飛鳥時代まで見当たらない。大型建物の傍(大型祭祀土壙SK-3001)で宗教的行事が行われた痕跡も発見された。
この建物群は、位置関係から言って三輪山及び箸中山古墳と緊密な関係が推察される。建物廃絶の時期と箸中山古墳建設開始の時期が近いこと(FAQ10参照)を勘案すると、三輪山と関係の深い宗教的指導者がここに君臨し、死後に箸中山古墳に葬られたと考えるのは合理的である。この大型建物群と箸中山古墳そして上つ道の位置関係は、トポロジー的に咸陽と驪山陵を想起させる。
箸中山古墳は、日本列島広域各地の葬制を総花的に集約した定型化古墳の嚆矢であり、初期ヤマト政権の初代王墓と考えられるが、被葬者が女性であるという伝承にも信憑性(◆3参照)がある
乃ち、その葬制の総花的性格から初期ヤマト政権の初代王は各地の首長に「共立」され求心的に集約された権力基盤を持つ者であり、かつ女性と考えられる。その死亡時期は3世紀中葉(FAQ30参照)である。
この地に、青銅鏡や武具、新たな土木技術や萌芽的馬匹文化(FAQ21参照)、列島に存在しなかった植物の花粉等(金原2015)など、中国文化が急速に浸透する時期は、列島が魏晋と通交した時期と重なる。
ほぼ同時代史料である魏書東夷伝倭人条(魏志倭人伝)の記事と上記の考古的諸事実を突合すると、箸中山古墳の被葬者は曹魏に卑弥呼と呼ばれた人物であり、◆2~8に詳述するとおり、ここ纒向が女王の所都である。
◆2(箸中山古墳に見る共立の構造と政治的ネットワークの形成)
前掲の大型建物が廃絶時に解体され柱まで抜き取って撤去されていることは、後世の遷宮との関連も考えられるが、歴代の宮のあり方に照らせば、建物の主の死去に伴う廃絶と考えることに合理性があるといえる。したがって、この建物の主人の活動時期は卑弥呼と重なる。
また、箸中山古墳はこの建物の真南2里(魏尺)に立地し、且つ上つ道(推定)で結ばれるなど緊密な関係を有しており、この建物の主が被葬者であると合理的に推認できる。
血統による相続原理が未確立な社会において、葬礼の執り行われる首長墓や殯屋は次代首長継承権の公認・公示される儀式の場(FAQ26参照)である。その場で顕示されている各地の葬制は、いわば王権の中における各地首長の影響力のバロメータである。
つまり、纒向に誕生した定型化前方後円墳のあり方は、共立された王をめぐる権力構造の表象たるモニュメントに他ならない。そして箸中山古墳以降、古墳の築造企画共有が、初期国家の骨格を形成する。
纒向の時代、上つ道に沿って系統的に展開する大王墓級古墳を時系列的に見ても、箸中山を嚆矢として西殿塚、行灯山、渋谷向山と明確な連続性が認められ、一連の政権が列島規模で存在したことが判る。これらの大王墓級古墳とそれぞれ築造企画を共有し、単純な整数比で縮小された首長級古墳が、全国に展開(澤田1999)しているからである。
築造企画の共有は、地縁的集団首長間の相対の結縁における相互承認関係を基調とした、擬制的親子或いは兄弟的政治力学関係を示していると考えられ、これが重層的に各地を網羅している状況が観察できる。
この個々の紐帯の集積が、律令的全国支配が企図される以前の、さらには各地首長の自立性が希薄化して国造化する以前の、倭国の政治的骨格である。ここでいう重層的とは、例えば大王級古墳の4/9の築造企画を持つ古墳においては、大王と2/3の力関係を誓約した大首長があり、更にその大首長と2/3の力関係を誓約した首長があるような関係を意味する。
乃ち、大王が4/9首長に対して直接指導力を発揮するのでなく、2/3大首長を通じて影響力を行使するような形態の国家権力構造である。
その始発点が、元来は無形である地域的政治集団間の政治力学関係が具現化・表象化し固定化される時期、乃ち機構的には未組織で初代国王の個人的カリスマに依存したプレ国家段階(庄内期)から或る種の政治的機関により運営される初期国家段階(古墳時代)へと移行する画期、乃ち布留0期にあるとみることが出来よう。
◆3(文献に見える箸中山古墳の特異性)
その行灯山、渋谷向山がともに帝王陵として伝承され、それらと規模的に同等である箸中山もまた「箸陵」の名が伝えられているにも拘わらず、帝王の姨の墓に過ぎないと紀で位置付けられている。
このことは、築造工事の大規模さや神と人の協業による築造という逸話が紹介されていること、就中それが紀の収録する唯一の陵墓築造記事であることも併せて鑑みれば、紀編纂時の、行灯山及び渋谷向山の規模を認識している読者視点に於いて、明らかに不自然である。
箸中山、行灯山及び渋谷向山は、例え位置関係及び築造年代の連続性を等閑看過しようと、その圧倒的質量において、同等格の主権者が連続的に存在したと人々に印象付けずにはおかない。
換言すれば、眼前の事実として当該陵墓を実見している読者にとって紀編纂時点で箸中山古墳の被葬者に崇神や景行と並ぶ男性帝王が被葬者として伝承されていたならば、現行のように改変を行うことは困難であろうということ、そして被葬者についての伝承が存しない場合も現行のように新規創作することが難しいであろう、ということである
また、所謂三輪山伝説の類型要素について記との相違点から考証すると、後世に陶邑から入って当地の勢力者となったと考えられる三輪氏の始祖譚など3世紀の史実とは無関係な要素が一連の地名起源譚等とともに接合されていることには疑いない。三輪山伝説類型の神婚説話や天岩戸神話など、付加された疑いの濃厚な類型的部分を除去すると、改変以前に存したと思われる伝承の残存部分が浮かび上がって来よう。
乃ち、手白髪陵に治定された西殿塚などより明確な形で、被葬者が男性の帝王でないことを示す伝承が紀編纂時においても無視しえなかった情報として存在したと考えることが出来よう。
女性被葬者のものと治定されている他の巨大古墳には、仲津姫(応神后、景行曾孫)や手白髪(継体后、雄略・市辺孫)など先代との血統的継続性に疑義のある大王に正統性を付与している配偶者のものなどが目立つ。或いは、五社神(神功)など本人が大王相当とされる者のものもある。これらの性格と比較しても、やはり箸中山の位置付けは異例である。
紀のしるす壬申乱の倭京での逆転戦勝に関連して、磐余彦天皇陵と箸陵の二つが登場することも加味しつつ、敢えて踏み込んで言えば、箸中山が考古学的知見から推察されるとおりの始祖王墓的な存在であること、かつ巫女王墓であるということを、当時の民衆が知悉しており、紀編纂当時の政治がそれを改竄し切れなかったという推測すら成り立つ余地があろう。
◆4(纒向の地政的意味と倭国の形成)
纒向は二上山と三輪山で奈良盆地を南北に二分する横断線の東端近くに占地する。この地は大阪湾から大和川を遡上した瀬戸内航路の終点にして、初瀬街道経由で伊勢雲出川河口付近から東海航路に向かう起点である。
同時に上つ道に面し、北陸・山陰にも抜ける交通の要衝である。乃ち、三輪山をランドマークとする辻に関塞の神を祀る地であり、古くより大市が立つ。
威信材の流れや墓制の消長から、弥生時代の北部九州では対外交渉力で突出した小国の興亡があったことが判明しており、そのうちには中国製威信財を独占的に入手し配布することで「倭国」的な政治的纏まりを現出せしめるやに見えた者もあった。
しかしながら、国家形成と呼べる水準に至らぬまま衰退し、最終的には2世紀末の大乱期、中国製威信財入手ルートの途絶を以て、この列島における旧世界の秩序は崩壊した。
代って、気候条件悪化に起因する社会不安の沈静化と政治的求心力の喪失による紛争の回避を目途として、この地纒向に新たな秩序の中枢が構築され、本格的な国家形成が緒に就く。
共立とは、各地の葬制を総花的に集約した定型化前方後円墳に表象されることになる政治的関係における求心的集約の状態を、当時の中国の語彙で表現したものに他ならぬと思われる。おそらくは当初に調停の庭であったそれが、完鏡等の威信財供与と祭祀の規格化に表象される首長間のリンケージの核となっていくのである。
それは首長と首長個々の相対の結縁が重層化した形態をとり、次代の前方後円墳築造企画共有に繋がっていく祖形となる。
定型化前方後円墳における葬制の「総花」性の中で、突出しているのは吉備地方であり、北枕原則が貫徹している畿内―吉備は葬制から見た政治状況中の枢軸といえる。
もとより畿内第V様式圏の文化的斉一性は、交流圏・通婚圏として纏まりが存在したことを示す
此の環大阪湾文化圏と吉備を核とする瀬戸内圏との合作は、日本列島中西部を縦貫する流通大動脈を形成し、現実的に倭国乱の帰趨を決したとも言えよう。
後段で触れる所の寒冷化による海水準低下で、多くの砂丘上の港湾集落が廃絶し潟港が埋没して機能低下を来たした日本海航路に対して、瀬戸内航路の価値は大いに上昇していた。纒向に誕生した政権の特徴である求心性も、この流通支配の趨勢を踏まえたものであろう。
この意味で、倭人伝に登場する倭の国が東夷伝中で珍しく流通や通信に言及していることは、注目に値する。
初期ヤマト政権の性格を、アンフィクチュオニーと通商連合の両面から理解することは、有益である。
◆5(倭国の形成と気候変動)
1に、南播磨を主力とする畿内系住民が北部九州に移住し交流しているとみられる状況
2に、河内と吉備の交流の深さ
この2点を併せ鑑みれば、東海地方(中勢)にも影響力を持つ宗教的指導者を、纒向の地に地域間紛争回避の機構として擁立した勢力の中核をなすのは、汎列島的交易網の再構築と拡大を目途とする、瀬戸内の海上交通を支配する首長たちの利益共同体であろう。
共立によって地縁的紐帯の域を超えた広域のプレ国家が誕生した。その成熟段階であろう3世紀前半末には、四等官を有する統治機構や市場の統制、通信網の整備などが観察されている。
これが更に個人的カリスマの死去を契機として、布留0期に、機関化した政治システムのフェイズへと進むのである。
2世紀は、炭素年代の較正曲線などからも太陽活動の不活発な状況が見て取れるとおり、寒冷化が進んだ時期であることが知られている。
この寒冷化は、世界的な環境収容量力の低下となって、漢帝国の弱体化を決定づける農村の疲弊(逃散を含む)や北方民族の南下を引き起こしており、世紀末葉の中国は天下大乱の時期となった
倭国乱もこの時期である。
寒冷化による海退は、砂丘の発達を再開させ、温暖期に安定していた砂丘上に展開していたいくつもの海浜集落を廃絶に追い込み、潟港の機能低下と相俟って国内流通網の再編(※日本海航路の衰退と瀬戸内航路の隆盛を含む)を促した。
弥生社会を終焉に向けて転身を強いていた気候変動の総決算である。
◆6-1(自然環境と下部構造からみた国家形成期社会の動態)
これより先、寒冷化に対応する生産力確保という社会的必要性が、開墾や治水・灌漑の分野で大規模開発行為を行うに足る労働力を大量に徴発できるような強権的な地縁型首長を誕生させつつあった。
これは、墳丘墓の急速な巨大化・高塚化から窺知できる。換言すれば、高塚化の加速した地域には急速な脱弥生の社会構造変動が起こっている。
先駆的な具体例としては、寒冷期に向かう不安定な気候が卓越する時期、吉備中南部で体系的な用水施設を備えた大規模な水田開発が、高塚化された大規模で入念な埋葬に見る威信や地位を付託された特定の人々の析出と共時的に生起(松木2014)している。
析出された特定者への威信付託の象徴として、モニュメントである墳丘墓に付帯するものとして、本源的に個人が身体に装着する物品に由来する威信財には親和性がある反面、個人所有に馴染まない楽器型青銅製祭器は前途を分かつたものと推察される。
後期に入って既に退潮となっていた大型の武器型及び楽器型青銅器祭祀は、より広範な地域統合を象徴する社会的ニーズの高まりから、その役割をより可視性の高い高塚墳丘墓によって代襲され、その社会的使命が終焉に向かう。
やがて地域間統合の阻害要因となりうる祭器の性格の差異を捨象する必要から、武器型の持つ金属光沢属性を鏡面に、楽器型の鋳造文様の造形的属性を鏡背に統合して引き継がれ、古墳祭祀の付帯要素に落着(吉田2014)した。
分節化した統合性の象徴として、小型で可搬性のある銅鏃のみが儀器化して古墳時代に引き継がれる。
方形周溝墓は主に親族集団墓として近畿・東海を中心に分布し、円形周溝墓は析出層の墓制として岡山に分布したが、その境界である南播磨で両者が共存した。
この延長上に、円形墳丘墓は弥生後期に摂津・播磨から阿讃播・摂河泉・丹波南部・大和山城、近江へと展開し、後期後葉には周溝陸橋部から変化した突出部付き円形墳丘墓として環大阪湾地域及び大和盆地にほぼ同時展開し、これが大和で巨大化の加速する前方後円形墳丘墓に繋がる。
二つの文化の共存した播磨で前方後円型墳丘墓と方形周溝墓の間の階層性が発生し、これが前方後円型墳丘墓巨大化の要因となって拡散した可能性がある。辺縁部で派生した葬制の変化が、畿内社会内部にも進行していた階層化を承ける形で中心部へとフィードバックされたのである。
この墓制の成立過程には、庄内式土器が制作技法、焼成方法ともに在地以外からの影響を受け技法の一部を取り入れて新たな型式を創出していること(長友2006)とも共通した特質がある。
◆6-2
高塚化の進行から窺知される社会構造変化は各地域で概そ銅鐸祭祀の終焉と期を一にしていることが知られているが、こと畿内とくに大和に関しては例外的に、銅鐸祭祀の縮小と高塚の発生(モニュメント社会の到来)に大きな時間差がある。むしろ高塚化に代えて第V様式が広範囲に斉一性を発揮しているように見えるのが畿内の特異性であり、世俗権力的な核の見出しにくい弥生後期畿内社会の特質の解明が待たれる。
巨視的観点からは、弥生石棒文化圏から銅鐸分布圏そして畿内第V様式と、令制畿内の前身が連綿として環大阪湾域を核とした東瀬戸内囲繞エリアを形成している。
◆6-3
ここで夙に指摘される畿内弥生社会の均質性の中から急激に巨大前方後円墳にみる権力集中が湧起したことは、近代のポピュリズムにも通じるものがある。権力の一局集中と公共性、一者が突出・隔絶することと他者が均質であることは、対立的に見えてその実良く整合が取れるのである。
一方、九州で高塚化が起こらなかったのは、その先進性が災いして中間階層が富裕で有力な社会構造であった為に、突出した権力の発生に対して掣肘が大きく働き停滞的であった所以であると考えられる。
この寒冷化が過ぎると、次の古墳寒冷期が開始するまでの間、砂丘上には再びクロスナ層の形成が始まり、集落も再生する。宗教的権威が政治力を行使できた背景には、このような一時的温暖化による社会不安の沈静化という現実があり、気候変動が祭祀者の存在感を強調する意味で予定調和的に働いた可能性がある。
このクロスナ層中の遺物に共伴するのが庄内併行期の土器である。
◆7-1(北部九州における人の移動と政治的動向)
3世紀初頭から約半世紀の時間幅が庄内併行期と呼ばれ、卑弥呼の活動期間が稍前倒し的にこれと概ね重なる。
北部九州で出土する楽浪土器は庄内併行期をピークに激減、土師器 IIB(布留0新相~布留I古相)期には確認例がない(久住2007)ことが知られている。これは停滞期(高久楽浪IV期)を脱した楽浪が再興期(同楽浪V期)に活発な対外活動を展開したのち急速に衰退する、という趨勢がリアルタイムに反映している。(FA43参照)
つまり旧二郡域との交渉はIIA期(布留0古相併行)の中でほぼ終了していたものとみられ、ピークとなる庄内期の中に魏と定期的交渉を持った西暦240~248年が位置すると考えられる。
庄内併行期は、先行する弥生V期に引き続き畿内様式の土器が漸進的に北部九州に流入している時期であり、ことにその最終時期である布留0期に級数的に進展する。この流入は人的移動を伴うものと考えられており、博多湾岸に広がり、河川に沿って内陸に浸透する。
上位の墳墓に畿内系土器が供献される事例が増え、3世紀前半のうちに博多那ノ津地域の政治中枢が弥生時代以来の春日地域から畿内系色濃厚な比恵・那珂地域へ移ることからも、その浸透状況の性格が覗われる。
逆に、最後まで在地系の独自性を維持するのが糸島地域で、その畿内系土器の受容に極めて消極的な姿勢は、ヤマト王権への接近傾向が顕著な博多とは対蹠的と言える。
外港である今津湾、加布里湾双方に畿内系の往来が見られるにも拘らず中心部が在来系一色で、極めて僅かの供献土器が祭祀遺構とされる一角で発見されるのみ、という状況は、あたかも包囲的閉塞の中で辛うじて政治的独立を保証されているようにさえ映る。
1つに、前方後円墳の浸透状況(外港:泊地区に久住IIB期、中心街:塚廻に同IIC期)がその後の伊都国の終焉過程を表象していること
2つに、強権的色彩を帯びた一大率が人口の少ない伊都国に治を置いて検察業務を執行していると記す史料
これらを突合すると、対外交易の主導権を喪失した後の伊都国の姿が窺知できよう。
◆7-2
北部九州の土器編年で言えば卑弥呼の人生の大半を占める時期の相当する久住IA・IB期、博多は対外交易について最大級の中心地である。そのころ、博多は畿内人の流入を含む深い人的交流があり、生活様式から祖先祭祀の形態まで、その影響を受けている。
その影響を受けた在来系と影響を与えた外来系が共存・集住している集団と、外来系に対して閉鎖的な在地集団の間に、前者を上位とする集団間の階層差も指摘(溝口1988)されている。
糸島三雲番上地区に一定数の楽浪人居住が確実視されていることも鑑みれば、倭が中国と国交を再開した3世紀中葉において、中国は必ず博多の情報を入手していると見做してよい。従って、中国魏王朝は畿内にあった倭人社会最大の政権を知っていると考えるべきである。土師器IB期が魏王朝と国交のあった時期に相当することは諸説の一致するところである。
この時期に、奴国の中枢域に比定される那珂比恵地域の土器相が畿内ヤマトの「飛び地」的展開に向かっている現実は、邪馬台国九州説にとって絶望的である。
◆8(結語)
日本列島の対外交渉は、古くは勒島貿易、ついで原ノ辻貿易、そして博多湾貿易と移行する。
原ノ辻貿易の直接主体が壱岐のオウであり、そこに最も影響力を持っていたのが前原三雲の王であることが有名である。
原ノ辻が活気を失い博多湾が対外交渉の主役に躍り出るのが、庄内併行期である。
その転換の最終段階には、大和や播磨から移住してきた人々やその二世世代が圧倒的シェアを占める港湾都市で西日本各地の人々が韓人や楽浪商人と直接交渉による交易を展開する時代となる
前原三雲の王は静かに表舞台から退場していく。
博多湾貿易の時代全体を通じて、那珂川地域ー足守川流域ー纒向は国内流通の大動脈を支えるトロイカとして機能し、その消長も時期的に一致する。これが倭人伝記載の三大国(奴・投馬・邪馬台)アライアンスであり、博多湾貿易を基軸とする倭国の政体であり、金海貿易へ移行するまで存続したと考えられる。
遡って、第二次高地性集落は弥生後期になると低丘陵上で一部の一般生活集落が防衛的要素を帯びた形態をとる。
この現象は、寒冷化現象に起因すると思われる社会変動の存在や、同じく寒冷化に起因する中国の政情不安による威信財輸入途絶という政治的要素を綜合的に判断すると、文献資料上にある「倭国乱」にほかならない。
この時期に高地性集落が中九州から東海、北陸にまで展開するという事実は、「倭国乱」が日本列島中西部を広範に巻き込んだ社会現象であることを物語る。
土器拡散にみる遠隔地交流の活性化と併せ見れば、2世紀末~3世紀の状況証拠は、すべて初期ヤマト政権と新生倭国の誕生を指し示しているのである。副葬習慣をほとんど受容しない地域であった畿内(佐原1970)の豹変的社会構造変化は、全国区的政権誕生に向かう胎動にほかならない。
そして絶域であった日本列島が中華社会と二国間の国交を再開したとき、この外的刺激で最も変化の生じた地域こそが当時の倭国の中枢である。
倭人伝述べるところの、3世紀前半末に曹魏と通交した倭の女王はどこにいたであろうか?
以上の根拠により、それは桜井市纒向以外にありえない。
◆9 参考 (URL)
●ネット上でも見られる、畿内説を取る代表的な学者のひとり
寺澤薫が一般向きに書いた論説
纒向学研究 第1号(PDF)
http://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-1.pdf 纒向学研究 第2号(PDF)
http://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-2.pdf ◆ 参考(市販書籍)
●文献ベースの入門的論説
西本昌弘「邪馬台国位置論争の学史的総括」日本書紀研究17所収
仁藤 敦史「倭国の成立と東アジア」岩波講座日本歴史1所収
●コンパクトで包括的な概説書
洋泉社編集部編「古代史研究の最前線 邪馬台国」
●東アジアの考古学へと視野を広げた解説書
東潮「邪馬台国の考古学」
等
◆10 実年代目安の参考
(現時点で高等学校日本史教科書などに採用されている年代観と概ね同等の、最も広く通用しているもの)
○弥生時代後期
1世紀第1・2四半期~2世紀第3四半期中頃
○庄内式期(庄内0~3)
2世紀第3四半期中頃~3世紀中頃
○古墳時代前期前半(布留0~1)
3世紀中頃~4世紀第1四半期
○古墳時代前期後半(布留2~3中・新段階)
4世紀第2四半期前半~4世紀第3四半期
○古墳時代中期前半(布留3の一部、TG232~TK216)
4世紀第4四半期~5世紀中頃
(古代学研究会 森岡、三好、田中2016による)
※箸中山古墳は布留0古相に該当(寺澤2002)
※本文◆7の「3世紀初頭から約半世紀の時間幅が庄内併行期」は
庄内0を庄内式直前として弥生後期に分類する考え方で、実年代観は同一である。
同様に、布留0を庄内に分類する考え方も実年代観に違いがない。
庄内併行期を弥生時代と呼ぶか古墳時代と呼ぶかが実年代観の相違でないことと同じ。
※北部九州編年(久住)との並行関係(久住2002,2006,2010)
IA期ー 大和庄内0~1 ー 河内庄内I~II
IB期ー 大和庄内2~3 ー 河内庄内II ~III ●纒向矢塚、矢藤治山
IIA期ー 布留0古相 ー 河内庄内III ●箸墓、権現山51号
IIB期ー 布留0新相~布留1古 ー河内庄内IV~V ●西殿、桜井茶臼山、黒塚、
浦間茶臼山、西求女塚
IIC期ー 布留1中相~布留1新 ー河内庄内IV~布留I●椿井大塚山、神原神社、
メスリ山、行灯山、祇園山
◆11
◆FAQ 1
Q:倭人伝には九州のことばかり書いてあるではないか!
A:九州は倭国の一部なので問題ない。
郡使は伊都国で常に駐するので、九州のことがよく観察されているのは当然のこと。
逆に、伊都国の属する博多湾岸地域に見られない風俗や産物(灼骨卜占や丹井)が記されている事実は、倭国の地域的広がりを推定するうえで重要な情報であり、就中、倭国の都が博多湾岸地域には無いことを物語る。壹岐一国では観察されたが首都よく観察しても見出せなかった風俗を、倭国全般の風俗と記録することは、合理的行動でないからである。
畿内は朱の生産地を擁しており、これは3世紀の九州に見られないものである。水銀朱精練遺構は三重の丹生の天白遺跡や森添遺跡、宇陀の丹生河上が縄文、唐古鍵・清水風が弥生中期で宮古北が布留0と、古くから利用されている鉱床所在地近辺に点在する。
水銀朱採掘遺跡そのものは未発見であるが、丹後赤坂今井墳丘墓(弥生終末)出土の水銀朱が明らかに丹生鉱山産朱の特徴を示し(南ら2008)、ホケノ山の水銀朱はMn,Feの含有量に於て大和水銀鉱山と同じ特異性(南ら2001)を示す。
桜井茶臼山(3世紀末)出土の水銀朱が大和産であることは水銀、硫黄及び鉛同位体比分析によって判明済み(南ら2013) である。これらの状況から、3世紀の宇陀や丹生に丹山が有ったことは確実視される。
北部九州の古墳出現期には、津古生掛古墳など畿内と関連の深い一部の限られた墳墓より畿内産の水銀朱が発見され(河野ら2013)ている。被葬者でなく埋葬施設に施朱するのは九州では殆ど見られない儀礼(志賀・谷口2012)であり、東方からの影響と考えられる。
また、纒向遺跡から出土した卜骨も倭人伝の記事と合致する。(FAQ51参照)
倭人伝に糸魚川産の硬玉ヒスイが登場していることにも疑義の余地はなく、当時の中国人が認識する倭国の範囲は日本列島規模である。
◆FAQ 2
Q:水行とは河川を行くことだ!
魏使は九州を出ていないではないか!
A:海を行くときも「水行」と記載された実例があるので不成立。
「水行」と書かれているが川であるか海であるか判明しないケースを、川と判断する理由は無い。
逆に、明確に河川を移動しているケースで陳寿が「水行」という語彙を使った例は無い。
(例)
「泝流」が6回
「泝(+固有名詞川名)が7回
倭人の地が大陸ならぬ大海中の島嶼上に所在することは予め明示されている。
倭人伝における「水行」の初出が「循海岸」と副詞的に形容されている以上、以降の10日や20日に及ぶ「水行」をその省略形であると見做すことには合理性がある。
◆FAQ 3
Q:行程論から言って、畿内説は無理ではないのか!
A:倭人伝の記す行程を記載通りに辿れば、沖縄本島付近の南海上(◆FAQ40参照)となる。史料にいかなる解釈を施して上記以外の比定地を求めても、それはテキストの改竄もしくは粉飾に他ならない。
「當在」という語法からは、筆者が里程等から倭人の国を会稽東冶(現・福州市近郊)程に南方であると具体的に推計し、倭人の南方的風俗との整合性確認を意図したことが明らかである。故に、「自郡至女王國」の「萬二千餘里」は倭人の国が会稽東冶ほどに南方であると言う筆者の認識を端的に示している。
以上から、倭人伝の里数及び「南」という方位倶に致命的な誤りが含まれていること、並びに筆者が1里=1,800尺を用いていること、の二点に疑問の余地がない。(註※)
実際の倭人の国々は倭地は会稽山陰はおろか魏都許昌ほどの南方に過ぎず、纒向は洛陽とほぼ同じ北緯である。
三海峡渡海は概ねの定点を得ることが可能なので、測距に錯誤があることが明らか(◆FAQ19参照)である。加えて、九州本島最南端は会稽山陰より猶ほ北方である。また、現実の1/5ほどの架空の1里を想定するならば、楽浪を「雒陽東北五千里」とする地理感に照らすと倭地は洛陽の猶ほ北であり、倭人伝記事と全く整合しない。
筆者の認識した万二千余里の数字、及び「南至邪馬壹國」の方位「南」。この双方に錯誤を認めない限り、「當在會稽東治(当作「冶」)之東」と記述されることは有り得ない。東冶の「東」の方位に誤差を認めて強引に現実的地理に近づける解釈を行うことも、角を矯める愚を犯すに等しい。
実際の地理上3海峡の間隔が等距離でないことはもとより、倭人伝所載のとおりの行程を辿ったのでは、伊都国であることが確実視される糸島三雲にも、奴国たるべき博多・比恵那珂エリアにも到達できないことは自明である。
このように、行程記事は方位・距離ともに著しい誤情報を含み実用に耐えないので、所在地比定には採用しない。検証にのみ用いる(関連:◆FAQ8,17,18,19,20も参照)
※検証 古代中国の地理感覚(続漢書地理志注記による)
遼東郡:雒陽東北三千六百里 楽浪郡:雒陽東北五千里
予章郡:雒陽南二千七百里 南海郡:雒陽南七千一百里
(雒の用字より漢代原史料に基づくものと推定)
倭人伝云う所の12,000余里うち韓が方可4,000里であるから、南方向成分は9,000里程度となろう。楽浪が東北5,000里より南方向成分を概略3,000里程度と見積もると、
楽浪から、会稽山陰よりも稍や南に所在する予章まで南北で6,000里以下、広東まで10,000里程度とイメージできる。上記約9,000里は帯方~現・福州市間の南北距離として矛盾がない。
また、12,000余里うち南方向成分が9,000里程度となると方位は著しく南南東に偏し、倭人伝冒頭に掲げる「帯方東南」との齟齬が大である。このことも「南水行」の方位に錯誤を認むべき根拠となろう。
◆FAQ 4
Q:纒向遺跡は、七万戸だという邪馬台国には小さすぎる!
A:誰も、纒向遺跡=邪馬台国だなどと、主張はしていない。
纒向遺跡は、巫女王の居た王都であり、国ではない。
また、「邪馬台国は大和国」と言う表現を用いる諸説も、多くは邪馬臺の語源(音写元)についての言及であって、領域としての令制大和国という定義を主張していない。
畿内説においては、邪馬臺を大和朝廷の王畿とした内藤湖南の見解(内藤1910)以来大きなブレは無いものの、令制国の疆埸と3世紀とでは時間差による異同が無視できない。よって、邪馬台国の厳密な範囲については材料不足であるものの、令制五畿の概念に代えて、考古学的観点から概ね2世紀末葉時点の近畿第V様式分布域を想定する。
また、邪馬台国と女王国を=でなく⊂で考えた場合、纒向遺跡に搬入量の多い中勢雲出川流域等をはじめとする畿内周縁部もまた、女王国に含まれる可能性を考慮する必要もある。
◆FAQ 5
Q:方位を間違っていたなら海峡を渡れず遭難する!
A:1719年に朝鮮通信使の一行として来日した申維翰は、対馬で南下しているのに東へ向かっていると誤認した。さらに対馬は東西に長い島(東西約三百里,南北はその1/3)と著書『海游録』に記す。(「東西可三百里、南北三之一分」)
佐須浦(現・対馬市上県町佐須奈)は対馬の北西端、府中(現・厳原)はそこから東(実際は南)二百六十里と書く。
(「自此西距釜山四百八十里、東至島主府中二百六十里」)
小船越では、実際昇る朝日を見ているのに、依然東に進んでいると考えており、彼の地理勘はちょうど90度狂っている。
対馬から見て釜山を西、大阪京都を北、長崎を東と認識している。
ところが、対馬からの京都大阪の方位について大きく錯誤しているにも拘わらず、江戸は京都の東千三百里と正しく把握している。
むろん遭難などせず、ちゃんと日韓を往復している。
このように、使者が方位を誤認していても安全に往還可能であることの証明が存在するとともに、誤情報の竄入によって全体の整合性は易々と喪失することが明らかである。
◆FAQ 6
Q:畿内説では、卑弥呼は記紀の誰なんだ?
A:記紀の王統譜をそのまま史実と見做さないため、卑弥呼を記紀の誰かにそのまま当て嵌めない。近年の歴史学のあり方に沿った考え方と認識している。
◆FAQ 7
Q:纒向から九州の土器が出ないではないか!
纒向は九州邪馬台国と交流のない別の国だろう?
A:そのような事実はなく、当然交流があった。
畿内第V様式、庄内式、布留式みな時系列に沿って北部九州から出る(本文◆7参照)し、纒向においても筑紫で製作された庄内甕(久住2006)が出る。畿内と北部九州を結ぶ海路の重要拠点からも畿内系・吉備系の土器が発見される。(◆FAQ31参照)
このことは、往来していたのが畿内系・瀬戸内系の人間だったことを示し、畿内と北部九州の片務的関係を示唆する。かつ畿内系が社会的に上位である。(◆7参照)
◆FAQ 8
Q:「女王國東渡海千餘里、復有國、皆倭種」
と倭人伝にある。畿内説は南を東に読み替えるから、これは北だな?
A:読み替えない。
行程論とは別の方法で纒向を倭国の都と特定した結果「南至邪馬壹國」の南は「東」の誤りと判明した。つまり、行程論で邪馬台国の位置を比定しようとする九州説の多くとは論理の向きが逆の方法論である。
これは他の箇所をも読み替えるという主張ではない。
伊豆七島などは唐古鍵の時代から畿内と交流圏である。考古的遺物の分布からも、古来百船の渡会たる伊勢より三遠駿さらに南関東に至る海上交通路の存在が明らかであり「女王國東渡海千餘里」の情報源として注目される。
◆FAQ 9
Q:狗奴国はどこだ?
女王を共立したのが西日本を覆うような広域だとしたら
女王に属さず逆に脅かす程の勢力、狗奴国とは何者か?
A:S字甕第1次拡散域ならびに多孔銅鏃分布域が中部から北陸、関東に及ぶ広域に存在した
有力な候補である。
中九州を中心とした免田式分布域も面積的には狭いが、倭国の対外交渉を阻害する可能性という側面での危険性を考慮すれば対抗勢力として評価できる。
倭女王卑弥呼は二郡の対韓戦役に協力した形跡がなく、その言い訳に狗奴国の脅威が強調された可能性もある。
いづれにせよ領邦国家が成立している史的発展段階にはなく、当時の「国」は複数の政治的地域集団が点と線で結ばれ彊埸が不分明であったと考えられることは念頭におく必要がある。
王名の卑弥弓呼を称号と理解する限りでは倭国と同一文化圏に属するものと解せるので、卑弥呼の共立に対して不服な分派という解釈もあり得よう。
◆FAQ 10
Q:箸墓は宮内庁管理の陵墓で発掘できない筈だ!
年代が判るという考古学者はおかしいではないか!
A:箸墓(箸中山古墳)墳頂で採取された土器相は宮内庁書陵部から報告書が出ており、その成果が弥生後期後葉から連続する時間軸上での指標となっている。
陵墓指定から外れた墳丘裾、渡り堤、周濠は発掘され、県の機関から正式の報告書が出ている。
封土を築いた土取り穴底で発見された土器等が工事開始直後周濠最底部に埋没した土器であって完成直後の時点を示すと判断され、布留0古相の範囲内で築造され完成したと判定されている。
しかしながら封土以前には地山切り出し工事があるため、着工がさらに若干遡る可能性も否定できない。
◆FAQ 11
Q:倭人伝の国は律令下の郡ほどの規模だろう!
それらの国が30国程度なら、筑前・筑後・肥前三国程度の規模にならないか?
A:倭人伝の記述からは、5千戸未満の小国と、万単位の大国に二極分化している状況が見て取れる。
・前者が、自然国境等に阻まれて規模的に弥生拠点集落の域を脱していない「クニ」
・後者が、河川流域や平野等の単位の大きな纏まりへと進化した、新しい時代の「国」
とみられる。
後者に属する奴国の位置は、博多湾岸地域最大である福岡平野に求めることが妥当である。彊埸には筑前型庄内甕の波及範囲を想定することが出来よう。
使訳通じる30国のうち両者の構成比は不明だが、すべてを郡単位と見做すのは不合理である。
◆FAQ 12
Q:倭人伝には「兵用矛」と明記されている!
畿内説は倭人伝と合わないのではないか?
A:矛という考古学用語は古代中国人の認識とは異なる。よって判断材料とならない。
福岡県においても、3世紀前半と確認できる鉄矛はひとつも出土しておらず、条件は同じである。
弥生時代に導入された銅矛は、儀器化する一方で実用武器として一部が鉄器化したが、殆ど普及しないまま弥生中期で概ね消滅した 。
以降、古墳時代に入って、騎兵の突撃を迎え撃つための三角錘型の穂先を持つ突刺武器=矛が再出現するまで途絶した理由は、実用武器として堅牢性の要求水準が袋状鉄斧等より高く、鋳造品である銅矛と同等の袋穂構造を鉄の鍛造品で作ることが経済合理性の上で鉄槍に劣後したためと考えられる。
当時の槍は中世以降のものと容貌を著しく異にしていて、剣状の穂先を4つの杷木で挟んで糸で巻き黒漆で塗りかためて固定しており、使用法も形状も矛の後継品であったと思われる 。
倭人伝に描写された3世紀前半は矛の副葬が盛行した嶺南地方と対蹠的に、本邦で信頼に足る鉄矛の出土例が見られない時期であり、当時の倭人社会で使用されている長柄武器は、現代語で言う槍である。
倭人伝にいう実用武器の「矛」の実体は、倭人伝原資料の報告者が目撃したところの倭人の武具、乃ち今日の考古学者が槍と呼ぶ遺物である可能性が最右翼といえるだろう。
当時の中国で「槍」という文字は長柄武器を指すものではないので、現代人の言う3世紀当時の槍を実見した中国人がこれを表記した可能性のある語彙が他に見当たらず、自分たちの社会で最も類似した道具の名前で呼んだとして何ら不思議は無いからである。
なお、「日本考古学の習慣で柄に茎を入れるものをヤリ、袋部に柄を差し込むものをホコといっているが、これは現代考古学の便宜上の区別に過ぎない」(「弥生から古墳前期の戦いと武器」日本の古代6)ともいう。
加えて
「『兵用矛楯木弓。竹箭或骨鏃。』とあるは、大要漢書地理志の儋耳朱崖の記事を襲用せり。此等は魏人の想像を雜へて古書の記せる所に附會せるより推すに、親見聞より出でしにあらざること明らかなり。」(内藤1910)
の指摘は今日も有効である。
◆FAQ 13
Q:倭人の墓は「有棺無槨」と明記されている!
古墳に槨のある畿内は倭人の国ではない!
A:槨という現代日本の考古学用語は、古代中国人の語彙である槨(本来の槨)とは異なるものである。よって否定材料にならない。
現代語「槨」が古代中国のそれとかけ離れていることは粘土槨や礫槨など古代中国にない呼称を用いていることでも明白であり、考古学者の間でも批判的意見のあるところである。
古墳の竪穴式石室もまた古代中国人の云う槨の概念とかけ離れた形状・構造であり、両漢魏晋人に槨と認識される可能性は無きに等しい。
畿内で一般的な墓は木棺直葬で「有棺無槨」に適合している。
逆に、北部九州に多い箱式石棺は中国人に槨と認識される可能性が否定できない。
◆FAQ 14
Q:畿内の政権が、本国を遠く離れた九州伊都国に諸国が畏憚するような強制力を持つ機関を置くことは困難なのではないか?
A:北部九州最大勢力の奴国域内に畿内系住民が多数おり、奴国と畿内は密接な協調関係にあったと合理的に推定できる。この人的資源を背景として、伊都国の外港を管掌する位置にヤマト王権が強権的な監察者を置くことは十分に可能であったと思われる。
伊都国の王都域とされる三雲遺跡から今津湾に注ぐ瑞梅寺川の河口付近には、博多在住の畿内系住民が往来したとみられる特殊な拠点がある。
糸島は壱岐と強いパイプを有していたことから、弥生中・後期にあって対外貿易の利を独占的に享受していた経緯が、遺物から窺知される。北部九州にあっても威信財の配布に於いて明らかに格差のある扱いを受けてきた辺縁部の首長にとって、対外貿易当事者の利権独占を制約する強権的な監視者の存在は有益である。
このような状況下で、畿内出自の流官が北部九州において、諸国が畏憚するような強制力を持つ機関を主導することには、これといった困難が認められない。
◆FAQ 15
Q:鉄器の乏しい畿内の政権が覇権を握るのは無理だ!
A:倭人伝の描かれた卑弥呼の政権は覇権的でない。
宗教的権威者を核に、各地の首長が自主的姿勢で政治力を求心的に集約(共立)したものであり、考古学が解明した3世紀の状況とよく整合する。
一方、伐採用石斧の減少状況から鉄器の普及状態を推測すると、九州と畿内でも極端な格差が無い。準構造船(久宝寺南:庄内新)をはじめとする木製品の加工痕からみても、一定量の鉄器が普及していたと思われる。
遺存例には大竹西遺跡の鉄剣(弥生後期初頭)や唐古鍵40次調査の板状鉄斧、痕跡では加美遺跡Y1号周溝墓の鉄斧による伐採痕や唐古鍵SD-C107鉄斧柄、纒向遺跡メクリ地区の大型鉄器を研磨したと推定されている大量の砥石(3世紀前半~中頃)など。
鍛冶を伴う遺構は纒向石塚の北東200m近辺出土の鞴羽口や鉄滓等(3世紀後半)、淀川・桂川圏で中臣遺跡(京都山科,弥生後~古墳初)、西京極遺跡(京都市内,弥生後前)、和泉式部町遺跡(右京区,弥生後~古墳初)、
南条遺跡(向日市,弥生後前)、小曽部芝谷遺跡(高槻,弥生後)、美濃山廃寺下層遺跡(八幡,弥生後後)、星ヶ丘遺跡(枚方,弥生後後)、鷹塚山遺跡(枚方,弥生後後)、木津川圏で田辺天神山遺跡(京田辺,弥生後~古墳初)など。
纒向での鉄利用状況については、大型建物D隣の大型祭祀土壙SK-3001より出土したヒノキ材(庄内3)の分析で、その加工痕及び周辺で植生上少ないヒノキの多用という状況から
「集落を包括した工人専業集団の発達がなされ、鉄器が一般使用または使用できる集落」(金原 2011)
と結論されている。
弥生終末期(庄内新相)の畿内中枢に於て遺物が直接土壌と接触しにくい墓制が普及し始めると同時に俄かに豊富な鉄器が登場するという状況を鑑みると、畿内の土壌の特性が鉄器の遺存状態に大きく影響していたことには疑問の余地が無い。
◆FAQ 16
Q:記紀には卑弥呼に当たる人物が登場しない!
九州の邪馬台国と大和朝廷が無関係だからだろう!
A:3世紀の史実を、8世紀に書かれた記紀が逐一忠実に反映しているとは期待すべきでない。
ことに、記紀の成立した当時の国是は治天下天皇が外国に朝貢した歴史を容認しない。
◆FAQ 17
Q:三国志の東夷の部分は短里で書かれていたのだ!
A:同一書の中で説明もなく、同名の別単位系を混用するのは不合理である。
また、倭人伝の里程を現実の地理と突合した有意な規則性は。未だ提示されてない。
よって短里という単位系を帰納することは不可能であり、短里は存在しないと言える。
このことは白鳥庫吉(1910)以来縷々指摘されているが、有効な反論がない。
◆FAQ 18
Q:3世紀の科学では、目視出来ない長距離の直線距離も天測によって求めることが出来た筈だ!
A:いかなる史料上にも、そのような測定実施の記録がない。
万が一にも、そのような測定があったなら福岡県が魏の許都の真東に所在することが明らかになるので、倭人伝の記事と齟齬する。
したがって測定は存在しない。
また、魏代の三角測量技術を示す当時の史料上では1里=1800尺であることが明瞭であり(『海島算経』劉徽,A.D.263)、多数出土している尺の現物と突合すれば、異常に短い架空の里単位系が実在しないこと、これ明らかである。
◆FAQ 19
Q:釜山~対馬あるいは対馬~壱岐の距離は、信頼できる基準ではないか!
これに基づいた里程論で、邪馬台国は九州島内に求められる!
A:1~2例から単位系を帰納すること自体が手法として非科学的であるというより、帰納の方法論に反する。ましてや、海上の距離のような測定困難な値から、古代の単位系を逆算することはナンセンスである。
新しいものでは、1853年の『大日本海岸全圖』にまで釜山~豊浦(対馬北岸)は48里と書かれている 。江戸時代の48里は約189㎞であり、海保水路部距離表に基づく釜山~佐須奈間は34海里(=63㎞)である。
江戸時代に1里が約1,300mという「短里」があったであろうか? 否、間違った距離情報があっただけである 。
まったく信頼性のない情報を用いて得た邪馬台国の比定地は、当然ながら信憑性が無い。
逆に、郡使の「常所駐」と記される伊都国から奴国の距離「百里」を、有効数字一桁(50~150里)の範囲で三雲遺跡から日向峠越えで博多南遺跡に到着するまでの実距離20km超と突合すると、正常な中国の単位系(1里=1800魏尺)で十分に解釈可能である。魏人或いは楽浪人の実見した可能性が最も高い地域で現実性ある数値が得られていることは、空想上の単位系を前提とした邪馬台国論の空虚さを物語っていよう。
◆FAQ 20
Q:倭人伝の里程はすべて概ね実距離の1/5~1/6
これで説明が付く!
A:そのような整合性は認められない。
考古学的知見から、帯方郡治は鳳山郡智塔里の唐土城、狗邪韓は金官伽耶に比定される
対馬国邑は不確定ながら、一支国邑は原ノ辻、末盧は唐津市中原付近、伊都は糸島三雲、奴は那ノ津に求めることが出来る。
信頼に足る実測に基づく限り倭人伝記載の里程には有意な規則性が認められず、倭人伝の里程には多数の間違いが含まれることになる 。
郡から九州本島に至るまでの距離は、ちょうど1万里になるように机上で創作ないし強引に調整されたものであると考える方に妥当性があろう。
九州説の重鎮たる白鳥倉吉が、現実の地理と照合して里数に有意な規則性が見出せないことを以て里程に基づいた邪馬台国位置論の抛擲を提言(白鳥1910)してより、既に100年が経過したが、有効な反論は提起されていない。
◆FAQ 21
Q:箸墓の周濠から馬具が出土している!
箸墓の築造は5世紀に近いとみるべきだ!
A:箸墓(箸中山古墳)の周濠が機能停止して埋没する過程で堆積した腐食土層より、廃棄された木製輪鐙が布留1式土器とともに発見されている。つまり周濠が機能して流水が通じていた時期にシルト層が堆積した時間幅に続いて腐食土の堆積した時間幅がある。
箸中山古墳の築造を布留0古相の3世紀第3四半期、布留1を西暦300年前後±20年程度とする実年代観と矛盾しない。
このような摩擦的な遺物の存在は、魏晋朝と纒向の初期ヤマト政権の交流による断片的な馬匹文化の流入と途絶を示すものとして合理的に理解される。
中国本土では前漢代の雲南省「シ眞」(テン)国の陶俑の片鐙、中華王朝では湖南省西晋墓の陶俑片鐙(西暦302年埋葬)が最古発見例で、現物は西暦340年の河南省出土例まで降る。
三国志には魯粛が下馬する際に孫権が鞍を支えた記述があり、鞍に装着された昇降用片鐙に体重が懸って鞍が傾くの防いだ状況が窺われる。
西暦302年時点で騎馬に従事しない陶工が正確に描写できる程度には普及が有ったと見ることが出来ることからも、4世紀初頭に日本列島で現物が出ることに不合理はない。
◆FAQ 22
Q:歴博がAMS法による土器付着炭化物のC14を測定、箸墓の築造年代を西暦240~260年と発表した!
これは信用ならない!
同じ層位から出土した桃核が100年約新しい年代を示しており、こちらが信用出来る!
A:箸墓(箸中山古墳)で発掘された桃核のひとつが1σ西暦380~550年という数値を示しているが、2σは西暦245~620年である。
もう一個が1σ西暦110~245年であり、土器付着炭化物の数値群と整合性がある。
つまり、桃核の測定値が系統的に新しい年代を示すとかいうのではない。
考古学的常識を大きく逸脱した一個の異常値を盲信するのは非科学的である。
炭化物の多孔性が持つ吸着力はコンタミネーションのリスクを伴うことも含め、統計的に信頼に足る量の測定例集積を待つべきである。
逆に、矢塚古墳庄内3層位出土の桃核2つ(NRSK–C11及び12)並びに土器付着炭化物1つ(NRSK–6)は、揃って3世紀第2四半期前半をピークとする値を綺麗に示している。

これを、桃核なら信じられるという主張に則って庄内3の定点として信用した場合、後続する布留0古相を3世紀中葉とする歴博見解を強く裏付ける好材料となるであろう。
一部に土器付着炭化物の測定値が系統的に古い数値を示すという意見があるが、そこで提示されている稲作到達以前の北海道の測定例は海産物由来のリザーバー効果で説明できる。一年草である米穀の吹き零れを測定した歴博例と同一視することはできない。 ◆FAQ 23
Q:卑弥呼の冢は円墳なのだから箸墓ではありえない!
A:「径」は円形以外のものにも用いられる表現である(ex.典韋の斧の刃:魏書18)ので、円墳と特定する根拠はない。
また、築造過程で箸中山古墳は円丘と基壇部のみの前方部から成っていた時期がある。
基壇部は水平方向から見ると隆起していない。
よって、基壇部の築造企画が当初より前方後円型である事実は、方丘後付説を否定できる材料ではない。
箸中山古墳は以下の過程で築造されたと推定される。
1)地山周囲を馬蹄形に掘り込み基壇部と周濠、渡り堤等を削り出しで整形構築
2)基壇後円部上に円形に堤状の土塁構築
3)その内側を埋めて円丘の段築を一段完成、2)から繰り返し円丘を完成させる。
この時点で、基壇前方部から円丘頂上に向けてスロープがある。
4)主体部を構築しスロープより棺を搬入し、墳丘上で葬送儀礼を行う。
5)前方部基壇上に盛土と方丘を構築して完成
以上の段階1~4で方丘が存在していない。
1)は基壇部や周濠の渡り堤が一体に地山から削り出されていることから
2)3)は椿井大塚山の事例から
スロープについてはアジア航測によるレーザー計測で存在が確認された。
箸中山古墳では第4段テラスに接合して実用性が認められるのに対し、時代が降るとともに形骸化している。
方丘築造が後出であるという判断は以下に拠る。
・箸中山古墳の後円部と段築が接合しないこと。
・箸中山古墳の円丘から降りてくるスロープが墳丘くびれ部から前方部寄りの位置で、前方部盛土に遮られる形で消失していること。
・椿井や中山大塚の構造や、河内大塚や見瀬丸山など築造中に中断放棄されたと考えられる古墳で、前方部に盛土がないこと等
◆FAQ 24
Q:黥面文身は九州の習俗で畿内には無いだろう!
A:黥面文身を九州説の根拠とすることは不可能である。
黥面土器の分布から見て、弥生時代終末から庄内併行期にこの習俗が特に盛行したのは岡山県及び愛知県(設楽1989)であり、九州ではない。
両地域と深い交流のあった纒向に黥面の人々がいたことは確実であろう。
古墳時代の畿内にも、この習俗が濃厚に存在したことは埴輪から明らかである、
このように、倭人伝の黥面文身記事は九州説にとって不利な記述である。
◆FAQ 25
Q:九州にあった倭国が大和の日本に取って代わられたことは、旧唐書に明らかではないか!
A:7世紀或いはそれ以前の史実解明を、日本列島と国交のない10世紀の後晋で書かれた後代史料の新出情報のみに依拠するのは、学問的でない。
旧唐書では倭・日本別国説と倭→日本改名説が両論併記されており、中国側の認識の混乱を表している。以下の各項等を勘案すると、別国説は、壬申乱に由来する訛伝等として片付けて毫も問題ない。
・唐代に書かれたことが明らかな史料がみな倭=日本という認識を示していること。
・唐会要(倭=日本と認識)より、旧唐書における錯誤の発生過程が時系列的に認識できること。
・突厥伝で同一国異政権を「別種」と表記している事例が確認できること。
後晋は僅か10年しか存続しなかった短命国家であり、政変の頻発する中で、旧唐書は編集責任者が転々とする過酷な環境のもとに編纂され、国家滅亡の直前にようやく完成をみた。
このためか、倭と日本が同一国でありながら伝が重複するという不体裁が発生しているばかりでなく、他にも同一人物の伝が二本別に収録されるなど、他の史書に例を見ない杜撰が複数件発生している。
◆FAQ 26
Q:古墳時代にあっても前方後円墳の企画が一律に展開しているわけではない!
ヤマトに統一政権があったなど幻想ではないのか!
A:日本列島における国家形成は弥生終末から急速に進展し、庄内期のうちにヤマトの王権を頂点とする萌芽期国家の紐帯が醸成されたとみられる。しかし、領邦国家の誕生は未だ遥か先である。
統一政権という語彙に、律令時代をも凌駕する近代的な地域的政治集団をイメージするのは、明らかに間違いである。
遠隔地同士の盟主的首長が、擬制的兄弟或いは親子的結縁で主に通商ルートに沿ってネットワークを構築し、網の目が列島の過半を覆った時点でも、それら点と線の合間には各個の盟主的首長には各地各個の敵対者もいるであろうし、中立的に距離を保つ者もいるのは当然である。
さらには、このネットワークの構成要素たる個別的関係が、世代を超えない当代首長単独相対の不安定な関係であったと考えられる。なぜなら、被葬者の遺伝的形質から推定される当時の親族構造から言って、血縁的相続関係が各地首長権の安定的継承を保証し得ていないからである。
ゆえにこそ、首長権の継承を決定づける古墳の墳頂祭祀において、そのステージの造作や儀式の所作で、首長権の継承を保証する従属者の奉事根元声明(誄)とともに、上位者や盟友に関する外交関係の継続も宣言されたのであったと考えられる。
古墳の定型化はこういった政治的諸関係の公示を含む組織化・規格化にほかなるまい。
◆FAQ 27
Q:ヤマトという地名が、奈良県に古くからあった固有のものという確証などあるまい!
A:ヤマト、カハチ、ヤマシロ、アフミなど、これら地理的特性を説明している地名は、古来のオリジナルと考えて支障えない。
ことにヤマトとカハチは対概念であり、確実にセットでオリジナルの古地名と考えるべきである。
◆FAQ 28
Q:九州には平原1号墓や祇園山古墳などに殉葬の例があるが、畿内の古墳には無い!
卑弥呼の墓があるのは九州だ!
A:平原1号墓、祇園山古墳ともに公式調査報告書は殉葬墓の存在を認めていない。
また、殉葬の奴婢たちが卑弥呼冢域に埋葬されているとする文献的根拠は無い。
参考事例であるが、始皇帝陵の陪葬坑はその多数が冢どころか陵園外にある。
日本の古墳においても墓域の認識は要検討であり、ましてや垂仁紀のように殉死者の遺体が遺棄されるのであれば痕跡も発見困難である。
以上のとおり、墳丘本体に殉葬痕があるか否か卑弥呼冢の判定基準にしようという考えには合理性が無い。
◆FAQ 29
Q:魏への献上品に絹製品があるだろう!
弥生絹があるのは九州のみ!
A:献上品に含まれている高密度絹織物「縑」は弥生絹ではない。
高密度絹織物は弥生時代の九州には存在せず、奈良県下池山古墳(布留1式古段階:3世紀末)が初出であり、景初の遣使が献上した班布がこれであると推定(布目1999)されている。
九州の弥生絹は織り密度の低い粗製品で、弥生中期の発見例が多いが、弥生後期には衰退している。弥生末期はわずかな発見例のみで、品質的にも低く、織り密度も低下している。
一方で、古墳時代の絹生産は伝統的な撚り糸を用いながらも弥生九州と比較にならない高密度の織布を行っている点で、技術的系譜が連続していない。
九州と畿内の絹生産は中国製青銅鏡の様相と酷似した推移を示していると言えよう。
「縑」に特徴的な、経糸と緯糸に併糸を加える技術で織られた大麻製織布が弥生中期の唐古鍵で発見されており、弥生時代における布の織り密度としては記録的に高い値を示している。(21・23次概報)
正始四年に倭の献上した絳青縑は赤色部分をベニバナで染色された「縑」であり、当時の纒向遺跡でベニバナの栽培乃至染色が行われていた状況(金原2013,2015)と一致する。茜染を意味する「蒨絳」の語彙が別途使用されているため、単独の「絳」deep redはベニバナ染と解されるからである。
以上から、3世紀前半以前の畿内で絹織物製造の画期的技術変革があったと思われる。
九州説にとって不利な条件と言える。
◆FAQ 30
Q:卑弥呼が死んだのは3世紀中葉と言っても3世紀前半のうちだ!
箸墓の築造と時間差があるだろう!
A:正始8年は帯方の新太守が赴任した年であり、卑弥呼はその着任を知って郡に状況報告の遣使をしたと考えるのが妥当である。よって正始8(西暦247)年は卑弥呼没年ではなく、生存の最終確認年である。
隔年の職貢が途絶したこの時から「及文帝作相、又数至」(晋書東夷倭人)とある景元4(263)年までを動乱期として捉えると、卑弥呼の没年は3世紀第3四半期の前半頃で、造墓開始がこれに続くものとみることができる。
「卑弥呼以死大作冢」とあるので、卑弥呼の死と「大作冢」の間には因果関係が認められ、寿陵ではないと判断できることと、卑弥呼の死の先立って張政の渡倭と檄告喩という政治的状況が開始している時系列を勘案した結果である。
以上から、大作冢の時期と箸中山古墳の築造とされる布留0古相の時期とには整合性がある。
なお、「以死」を「已死」と通用させてその死期を繰り上げて考える見解もあるが、通常の「因」の意味に解することに比べ特殊な解釈であり説得力を欠く。
また、「已」と解しても会話文の発話時点を遡るだけなので、地の文である本例では意味がないため、倭人伝の当該記事の記述順序を時系列順でないように入れ替えて読む根拠としては脆弱と言える。
このことは目前の用例からも明らかで、「已葬、舉家詣水中澡浴、以如練沐」の「已」が直前行の「始死停喪十餘日、當時不食肉、喪主哭泣、他人就歌舞飮酒」と時系列を入れ替えないことは誰もが知るところである。
解釈上も、繰り上げて卑弥呼の死を正始年中とすると、併せて壹與の初遣使も遡ることになり、不合理である。
「田豐以諫見誅」(魏志荀彧)、「騭以疾免」(歩騭裴註所引呉書)、「彪以疾罷」(後漢書楊彪)などの用例に従い、「(主格)以(原因)→(結果)」の時系列で読むのが順当である。
なお、倭人伝自体に正始8年以降の年号記載がないが明らかにそれ以降の記事が載っていることを勘案すると、張政派遣に関する一連の記事は嘉平限断論に基づいて書かれた改元以降の事柄である可能性が高い。
◆FAQ 31
Q:投馬国はどこに比定するのか?
A:畿内説の場合、投馬国を吉備玉島や備後鞆あるいは出雲に当てる説が従来から知られている。
考古学的に見て3世紀には瀬戸内航路が基幹交通路であったと見る立場、及び初期ヤマト政権の形成と勢力拡大に吉備が大きく関わっていたと見る立場からは、これを早鞆瀬戸や鞆の浦など鞆(船舶の部位名称)を含む地名や玉島・玉野など音韻的に近似する地名が多く分布するところの、瀬戸内航路に深く関連する地域的政治集団の連合体とみる見解が、整合性の上で有力視されよう。
もとより、交易ルートを分有する首長は利害を共有し易く、強固なギルド的連合を組成するインセンティブが存在する。
氏族名の上では上道氏・下道氏の祖に御友別の名が見られることも興味深い。
当時の基幹交通路には、吉備形甕の分布形態から、博多湾沿岸→周防灘→松山平野・今治平野→備後東南部→吉備→播磨・摂津沿岸→大阪湾→河内湖→大和川→大和というルートが推定(次山2009)されている。
また河内産庄内甕の伝播経路を、(播磨~摂津~河内)間を陸路として外を同上に見る見解(米田1997)も参考として興味深い。
これら瀬戸内ルート説は、海水準低下に起因する日本海航路の機能低下を鑑みると妥当性が高い。
優れて規格性・斉一性に富んだ吉備形甕の分布域は、博多湾域への大量搬入を別とすると、東においては揖保川流域で畿内第第V様式圏と重なり、西には芸予・防長の文化圏と予州で重なる。伊予以西から博多湾までは吉備形甕、庄内甕及び布留甕みな大きな集中がなく沿岸部に点在しており、吉備・伊予を核として各地沿岸部の小首長が協調的に交易ルートを維持し博多湾に到達していた状況が窺知される。
吉備は葬儀用器台文化の中心であり、瀬戸内・畿内は勿論のこと西出雲や但丹狭にまで影響を及ぼしている。
弥生後期から古墳前期における吉備中南部の人口動態(松木2014)と、足守川流域における墳丘墓の卓越性から見て、中瀬戸内における港津性を有する主要河川ごとの首長の連合体の中核はこの地域を想定するのが妥当と思われる。
畿内色に染まって以降の那珂川地域と、足守川流域、ならびに纒向という3エリアの消長が時期的に一致していることは注目に値しよう。
これを倭人伝記載の三大国(奴・投馬・邪馬台)のアライアンスとして理解し、博多湾貿易を基軸とした政体が金海貿易への移行とともに解体するものと概念把握するのである。
◆FAQ 32
Q:畿内説はなぜ記紀を重要視しないのか?
A:いかなる史料も史料批判が欠かせない。
3世紀の史実解明にとって、原史料すら成立が6世紀を遡る見込みの乏しい史料を使用することは、考証に要する労力負担が過大な割に成果の期待値が低い。
これが部分的利用に留まる所以である。
◆FAQ 33
Q:「女王國東渡海千餘里、復有國、皆倭種」
と倭人伝にある!
海を渡るとは陸続きでないところに行くことだから、女王国は本州にある畿内ではないな?
A:陸続きのところへも渡海するので、伊勢から遠駿相総等への東海航路と見做して問題ない。
「夏六月,以遼東東沓県吏民渡海居斉郡界」(三国志三少帝)遼東熊岳付近→山東半島
「東渡海至於新羅、西北渡遼水至于営州、南渡海至于百済」(旧唐高麗)北朝鮮→韓国
◆FAQ 34
Q:平原王墓の豪華な副葬品を見よ!
伊都国は隆盛のさなかである!
A:平原1号方形周溝墓の築造時期は弥生後半~弥生終末とされるが、より詳細には、埋没の開始した周溝下層出土の土器相から、弥生終末(西新式直前)と位置付けられる。(柳田2000)
原の辻貿易が終焉にさしかかり糸島が対外貿易のアドバンテージを喪失することとなる時期に当たる。
副葬品は中国製青銅鏡を含まない鏡群中心で構成され、使用された金属素材は、鉛同位体比分析に基づけば一世紀ほども前に入手された輸入青銅器のスクラップであった可能性が高い。
当時は楽IV期(停滞期)にあたり漢鏡6期の完鏡舶載品が払底していた時期で、舶載鏡の多くが鏡片として研磨や穿孔を施して利用されていた。
国産の小型仿製鏡は漢鏡6期の破片を原料として利用することも叶わず、それ以前に舶載された所謂前漢鏡タイプ(馬淵W領域)製品のスクラップを原材料としたと考えられるが、平原出土鏡の約半数がそれらと同じ素材で作鏡されている。それらは漢鏡4期の舶載鏡素材に近い特徴を示している。
残り半数には上記領域をはみ出した素材(同WH領域)が用いられており、原料不足を異種青銅器スクラップないし異質の備蓄で補填した可能性がある。これらには山東省出土の戦国期遺物に近い特徴が認められる。
大量鋳造の中途で異種の金属素材が追加投入されるような状況は、荒神谷の銅剣で観察されている。(馬淵ら1991)
後漢鏡に用いられる金属素材は、漢鏡5期の早いうちに所謂前漢鏡タイプ(馬淵W領域)から後漢鏡タイプ(同E領域)に移行している。
平原1号出土の大型乃至中型仿製鏡群は、漢鏡4期及び5期の模倣作であり、かつ後漢鏡タイプの金属素材を使用せず、かつまた北部九州で拡散することがない。
いづれも古墳時代の仿製鏡や復古鏡とは断絶がある。
後続する2号以下にはめぼしい副葬品は発見されておらず、規模的にも退潮が明らかである。
このように、「絶域」時代で、大陸系文物の入手経路と、倭国の代表たることの背景としての漢朝の威光が共々喪なわれ、また博多湾貿易への移行によって経済的基盤も喪失している状態である。
以上より、平原1号は、伊都国当事者にとって自分たちの凋落が決定的という認識のもと、大規模とは言えない墳丘墓の被葬者のために年来の保有資産を思い切り投入した墓所、という様相を呈していると見ることができるであろう。
◆FAQ 35
Q:当時の出雲には日本海側を総括するような大帝国があったのだ!
A:四隅突出型墳丘墓の分布域は一見して山陰・北陸を糾合しているかに見えるが、墓制の異なる但丹狭でもとから東西が分断されている。しかも雲伯と越、さらに因幡にも異なる地域性があり、墳丘規模的にも西出雲の西谷墳墓群が隔絶して卓越するとは言い難い。
ことに西出雲西谷が最盛期にあって因幡の西桂見がこれらを凌ぐ規模であることに加えて、葬儀用器台の文化が吉備から直接流入しているのは西谷のみである。
以上より、各地域の自主性ある地域的独立政権を成員として統一的指導者なき緩やかな同盟関係があった可能性、という以上の想定は困難である。
ことに越地域は、雲伯との政治的連携があった形跡が希薄であることが指摘されている。(前田1994,2007)
一方で、西出雲の西谷墳墓群は、草田3(弥生後期後葉・楯築墳丘墓や平原1号墓と同時期)から草田5(庄内後半併行、布留0含まず)の時期に最盛期を迎えたあと急激に衰退する。
それでも弥生中期以来の文化的伝統を保持したまま、古墳時代に入ってもヤマトの文化圏に呑併されずに、独自性を保った地方首長として永く存続した特異な地域である。
国譲りの神話は、ヤマトに従属的とはいえ同盟関係であった地方政権(※)が、5世紀以降に分断・解体の圧力に晒され宗廟祭祀の存続保証と引き換えに独立性を著しく減衰させていく、という政治的状況を反映した後代所生の教条的逸話と考えるべきであろう。
弥生後期から古墳初期の史実を追求するにあたって、記紀に基づいて出雲を過大評価することは非現実的である。
同時に、北部九州勢力等に武断的に征服された等と過小評価することも、全く非現実的である。
※神原神社(箸中山古墳に後続する3世紀後半、三角縁紀年銘鏡を蔵)が四隅突出墓から方墳に退行した直後段階と評価できる。
◆FAQ 36
Q:弥生中~後期に隆盛を誇った伊都国は、終末期にもヤマト政権発足に関して強いイニシアチヴを発揮している筈だ!
A:伊都国は、3世紀前半から半ばにかけ北部九州で畿内系土器が拡散する状況下において、極めて閉鎖的であったことが明白であり、伊都国側が政治的に有利な立場は観察され難い。
博多方面で外来系に対して閉鎖的な在地集団が集団間の階層差において劣後する状況も鑑みる必要があろう。(◆7参照)
文化面においても、打ち割りタイプの銅鏡祭祀は従前より既に列島各地に波及していることから、その淵源が北部九州であっても畿内に対して影響力を有したとは評価できない。
また、畿内で主流となる護符的用途の完鏡祭祀(囲繞型をとる非破砕祭祀)は畿内で完成したもので、伊都国の影響ではない。
吉備ー畿内で支配的な器台祭祀が九州に見られないこと、精製三器種による祭祀は畿内から九州に入ったこと等を見ても、宗教面で伊都国がヤマト政権に先駆的であるとは見られない。
なにより、漢鏡6期流入段階では既に糸島地域(伊都国)は漢鏡流通の核としての機能を停止しており(辻田2007、上野2014など)、仿製鏡の製作者としてもこれを流通に供して威信財供給者として影響力を行為することがない。
那珂川流域(奴国)が規模を縮小しながらも小型仿製鏡の生産と供給を維持しているのと対照的である。
伊都国の文化的先進性は、古墳文化に消化吸収された源流の一つという以上の評価は難しいであろう。
◆FAQ 37
Q:特定の戦役が考古学的に存在確認されることなど滅多にない
纒向が九州勢力に征服されたことを考古学的に否定など出来ない筈だ!
A:纒向遺跡は、土器相・葬制共に畿内と複数辺縁地域との相互作用によって累進的に発展してきた遺跡である。
外部の特定地域からの支配的影響力は認められない。
これが総花的・キマイラ的と言われる所以である。
ことに高塚化の希薄であった北部九州については、根本的に社会構造が違っていたと見られ、畿内側が一貫して北部九州の政治的様相に影響を与える側である。
古墳時代のモニュメント型社会の根幹を形作る突出部付円丘の墳型もまた2世紀末から畿内に胚胎していた因子の史的展開経路上にあり、箸中山から西殿、行灯山、渋谷向山と大王級古墳が連続する。
ヤマト王権が2世紀末の形成期から4世紀中葉まで、外部から侵略等を受けることなくこの地に連続的に存在していたことに、疑問の余地はない。
◆FAQ 38
Q:纒向遺跡は一般人の住む竪穴式住居がなく、首都たり得ないのではないか!
仕えているはずの多数の侍女や警護の兵士はどこに住むのだ!
A:一般人の居住空間が宮城を囲繞する中国式の城市は持統朝を待たねばならない。
意図的企画により建設された纒向遺跡は、首長居住域も集住環境の埒内にある弥生時代の大集落とは一線を画しており、内郭が独立し宮殿及び禁苑域が発生した萌芽的政治首都と評価できる。
金文の「宮」が並行する複数建物と囲繞する方形牆垣からなる朝政空間を象形していることからも、庭院と回廊性の屋外空間を伴うこの大型建物群は宮殿の要件を具備しているといえよう。
古来中国の宮都造営は河川の利用と改変を伴うのが常で、多くの場合に漕渠が開鑿される。
この点も、矢板で護岸工事を施した長大な大溝の掘削で開始した纒向遺跡との類似性が認められる。
「自為王以来少有見者、以婢千人自侍、唯有男子一人給飮食伝辞出入。」
とあるとおり、卑弥呼に近侍するもの寡少で、その居処が一般人の居住区とは隔絶していた状況が窺知される。
纒向遺跡の示す非農村・非居住空間性、祭祀空間性といった性格と合致していると言えよう。
霊的威力者と信じられている者が一般人と雑居しないことは民俗的に肯われるが、弥生末に拠点集落が解体して内郭が首長居館を為す方形区画として独立化している傾向とも平仄が合う。
大溝の建設や、封土の運搬量が五百~千人日×十~五年とも言われる箸中山古墳をはじめとする土木工事跡は、相当の人口が纒向で労働していた証左である。農村型集落でないにも拘らず居館域下流の水路で多量のイネ科花粉が発見されていることで、稲籾や雑穀など穀類の集積的収蔵があったことが判明していることも、これを下支えする。
初瀬川の水運も有之、相当の昼間人口の参集することが可能であったことからも、弥生的大型集落が発展的に分散・解体したとされるこの時期、纒向遺跡の近傍に郊外的居住環境が展開していたことは確実である。
侵入経路の限定される奈良盆地自体に防衛上の利点があり、かつ四通八達の交通要衝でもある
新生した倭国の首都と目するに相応しい遺跡といえよう。
◆FAQ 39
Q:魏志によれば卑弥呼の都があるのは邪馬壹國である!
邪馬台国と呼び習わすのは畿内の大和と結びつけたい作為だろう?
A:倭人伝の記載する倭人固有語には日本語のもつ開音節言語の特徴がよく顕れており、閉音節であることを示す入声かつ二重母音となる「邪馬壹國」が、後世に発生した写本間の誤写であることは確実と言える。
女王所都の用字については12世紀を境に「臺」から「壹」へと移行して截然としており、誤写の発生時期が概ね明らかである。
◆FAQ 40
Q:倭があるのは会稽「東治」の東である!
九州でいいではないか!
A:孫策に敗れた会稽太守王朗が「東治」(拠 書陵部蔵 南宋刊「紹熙」本)へと敗走している。

行き先が東冶の候官(現 福州市冶山遺跡)であることは同行した虞翻ならびに追撃した賀斉の伝、並びに閩越の地と記す裴註所引献帝春秋にて明らかである。
福州市の東は沖縄であり、倭人伝の里程記事で邪馬台国所在地論争をすることの無益さを示す
◆FAQ17で触れた短里なるものを想定し難い証左でもある。
会稽東冶は、「会稽東冶五県」(呂岱伝)という用例からも判るとおり会稽郡東冶県の意味ではなく、同郡南部の通称的地域名(県名も当時既に冶県でない)である。
沿革も「李宗諤圖經曰…元鼎中又立東部都尉、治冶。光武改回浦為章安、以冶立東候官。」(資治通鑑所引注)などと紛らわしく、諸本とも治と冶の混用が多い。
東候官(故・冶県)は魏代・呉下は単に候官と称され、のちに会稽郡を分ち建安郡の属となった
このため、陳寿が三国志を執筆したとされる太康年間に会稽郡東冶県が存在しないことを以て東治は会稽東冶と別であるとする少数意見があるが、不合理である。そもそも会稽東冶が郡県名でないのみならず、儋耳朱崖など晋代にない歴史的地名が同じ倭人伝に用いられているからである。
捜神記や大平広記に登場する「東治」も全て冶県を指す。
◆FAQ 41
Q:平原1号を見よ!
九州には古くから三種の神器がある!
大和朝廷は九州勢力の後裔なのは明らかだろう?
A:その主張は、出現期古墳が鏡・剣のみで玉を欠く事実によって否定されている。
出現期古墳は、発生より2~3世代は玉を副葬に用いない畿内の習俗を継続しており、文化的混淆が進むには未だ時間を要していた。玉を副葬する文化圏の出身者は頭初からは初期ヤマト政権の中枢に参与していないと判断できる。
また、王権の象徴たるレガリアは、世界史的に見て被征服者から征服者に移転する傾向が強い。
記紀においても、榊に伝宝である鏡・剣・玉を懸垂して征服者を迎える降伏儀礼が記されている。(景行紀、仲哀紀)
畿内系土器は、葬送祭祀の供献土器として、古墳時代に系列的に展開する大王級古墳に採用されている。これらの受容に極めて消極的(FAQ36参照)であった三雲遺跡の支配者が、初期ヤマト政権と政治権力として連続しているという想定には、微塵も現実性がない。
弥生後期以降盛行した小型仿製鏡は内行花文鏡と同じ連弧文鏡系列に属すが、弥生後期のうちに分布が畿内圏まで達しており、その供給地は那珂川流域に求められる。
平原の八葉鏡は仿製鏡として独自の簡化と肥大化を遂げており、系統樹では古墳出土鏡の系譜に繋がらない枝葉に属する。同じく大宜子孫銘鏡(径27.1cm)も異形の内行花文鏡である。
これに対し、古墳出土の国産大型内行花文鏡は細部の仕様に倭臭を加えつつも、基本の幾何的設計原理(※)を舶載内行花文鏡から踏襲しており、系譜的に平原と断絶している。平原出土鏡と古墳時代に盛行する内行花文系仿製鏡との間のヒアタスは大きいといえよう。
※内行花文鏡の幾何的設計原理
円を8分割し、円周に内接する正方形を得る。
この正方形に内接する円を、雲雷文帯と連弧文の基調線とする。
この基調線の1/2径の同心円を圏帯の基調線とし、その内側に柿蔕鈕座を配す。
この、コンパスと定規だけで笵上に描画できる設計原理が、舶載の長宜子孫内行花文鏡から大型仿製内行花文鏡(柳本大塚、下池山など)に継承されており、平原鏡と異根である。これらが同笵鏡を持たないことも平原鏡と異質である。
◆FAQ 42
Q:初期の布留式があちこちで古式新羅伽耶土器と一緒に見つかっているではないか!
新羅の建国の頃まで時代が下るのだから当然箸墓は4世紀の古墳だ!
A:古式新羅伽耶土器とは新羅や伽耶という国の土器ではなく、新羅と伽耶の地域性が発現する以前の時代の土器を指す用語(武末1985の定義による)なので、単純な誤解である。弁辰韓V期(後期瓦質土器)に後続する年代の様式とされており、箸中山古墳の年代とも矛盾しない。
弁辰韓V期初期の良洞里162号墳では最終段階の弥生小型仿製鏡と漢鏡6期が共伴する。
申敬澈は慕容鮮卑による扶余の崩壊に起因する事象として木槨墓 II類の成立を捉えて大成洞29号墳の実年代を求めたが(申1993)、文献解釈として説得力ある根拠とは評価できない。しかし両耳付陶質短頸壺の成立を西晋陶磁器の影響下にあるものとした申編年には説得力があり、3世紀第4四半期に位置付ける結論には問題がない。
定角式銅鏃の編年により椿井大塚山(布留1)がこの直後の年代に位置付けられる。
申編年による大成洞29号墳の陶質土器金官伽耶I期は久住 IIB期に併行するが、申が同じI期に含めた良洞里235号墳は前段階である弁辰韓V期に編年されており(高久1999)不整合である。
良洞里235号墳を木槨墓I類とみる金一圭は、嶺南の陶質土器編年をより詳細に10段階に細分して陶質土器の初源をもう一段階古く3世紀半ばから(金2011)とした。これは忠清道系陶質土器を共伴する加美周溝墓の庄内 II~III(久住IB~ IIA)や、久宝寺の瓦質土器(弁辰韓V期)模倣品の年代と整合性がある。
参考事例に西暦250年代とされる昌原三東洞2号石棺墓に副葬された硬質(陶質)土器短頸壺(釜山女子大学博1984)がある。
嶺南の陶質土器が形態上西晋陶磁器の影響下にあるとする前提は、より二郡に近接する忠清道系の陶質土器の起源がもう一段階古いとする動向と整合性がある。
このように日韓の交差編年は年々精緻化し、通説が強化されている。
◆FAQ 43
Q:平原が2世紀末だというのは何故だ? 箸墓は何故3世紀半ばなのだ?
炭素や年輪は信用できないし鏡は伝世しているかも知れない!
確かな根拠などないだろう!
A:楽浪・帯方郡塼室墓は分類・編年すると
1B II型式→ 1BIII型式→ 1BIV型式と漸移的に変化している。
また、1C型式が1BIII~IV型式の時期に亘って並存していた。
その築造年代を端的に示す紀年銘塼が
・1B II型式新段階の貞梧洞31号墳から興平2年(195)銘
・1C型式の鳳凰里1号墳から正始9年(248)銘
・1BIII-1型式のセナル里古墳から嘉平四年(252)銘
・1BIV型式の楸陵里古墳から太康四年(283)銘である
以上から
1B II型式新段階(2世紀末~3世紀前葉:塼室墓最盛期)
→1BIII型式(3世紀中葉:衰退期)
→1BIV型式(3世紀後葉以降:末期)
という実年代が得られており、このうち塼室墓1B II型式新段階が楽浪木槨墓V期と併行する。(高久2009)凡そ公孫氏が郡県支配を再編し倭韓との接触を強化してから、倭人の魏への定期職貢が途絶するまでの楽浪郡再興期に当たる。
楽浪木槨墓V期は下大隈式に後続する西新(I式)及び庄内と併行する(白井2001)
また後期瓦質土器の登場は西新式と同時期である(李昌熙2008)
よって西新式直前の平原1号墓が2世紀末に、布留0(大和庄内最新層)の箸中山古墳が3世紀中葉後半に相当する。
◆FAQ 44
Q:三角縁は存在しない年号が書かれている!
国産に決まっている!
A:景初三年から正始元年の改元事情を鑑るに、景初四年は実在したと考えざるを得ない。
史料上で抹殺された年号は珍しくない。
このような当事者しか知りえない事実は、中国製の証拠として有力である。
中国皇帝の即位は原則として踰年改元であり、即位後最初の正月に改元と共に慶賀の大会が催されるが、魏明帝は景初三年正月元日に死去したため、即位祝賀と忌日が重なる事となった。
この問題の解決法として魏朝は、明帝の推進した三統暦思想を敢えて廃案にし、再び夏正月を採用し元日を一ヶ月のちに移動させた。(宋書志礼一)
最終的に後十二月として閏月扱いとなるが、忌日と新年の大宴会作楽を分離させる為には景初四年正月の実在が必須である。
この改暦議論は忌日直前の十二月に入って始めて議論が始まって急遽決定された事柄であるため、暦の運用に当たって混乱が生じるのは自然であり、幾つかの記事にその痕跡を留めている。
一例として「春二月乙丑、加侍中中書監劉放、侍中中書令孫資為左右光祿大夫。」の記事は、景初四年(正月壬午朔)でなければ干支が合わない。
景初中の倭女王遣使から正始元年の冊封使派遣までの間、景初三→景初四→正始元各年銘の銅鏡が慌しく制作される状況の想定は現実的であり、
従来より考古学者が推定する所の、相互に連携した複数工房で同時進行し急いで集中的に制作されたという三角縁神獣鏡第1ロットの制作環境と合致する。
◆FAQ 45
Q:纒向遺跡に中国と通交した痕跡などあるのか?
A:◆1で略述したとおりである。
ホケノ山古墳は、3世紀に製作された後漢鏡や素環頭大刀などの武具を副葬品に蔵する。
箸中山古墳は、幾何的な正円を築く土木技術が用いられた列島最初例であり外来の技術である。
その周濠からは萌芽的馬匹文化の痕跡(FAQ21参照)が見出された。
倭人が上献した班布や倭錦そして絳青縑(FAQ29参照)も重要である。
ベニバナ及びバジルという、これまで列島に存在しなかった植物の花粉等(金原2015)は、朝鮮半島での発見例が無く、中国本土との直接交渉の結果であると見るのが最も妥当である。帰属時期は庄内3頃(纒向61次:李田地区溝1-A、橋本2008)とされる。
同じく花粉の大量検出によって大型建物群の近傍に桃園があったことが確認され
(金原2011)、SK-3001出土の桃の大量供献事例と併せ、魏志上で張魯の教団と同じ「鬼道」という呼称を用いられている卑弥呼の宗教が初期道教の影響を受けた新宗教であるとする見解について裏付けが得られた。
また、纒向遺跡から遠からぬ萱生の下池山古墳(布留1式古段階:3世紀末)からは、中国にない超大型国産鏡を収納するための、国産ではあり得ない羅張りの夾紵製容器が出土しており、中国に特注したとしか考え難い状況が観察されている。(河上2008)
その入手時期は二郡との通交が途絶する以前に求めざるを得ない。
◆FAQ 46
Q:洛陽晋墓から連弧文と蝙蝠座鈕の間に円形のある内行花文鏡が出土している!
これが魏晋鏡だろう?
A:洛陽晋墓からは日光鏡や昭明鏡など前漢鏡も出ており、本鏡も伝世した後漢鏡と見てよい。
2世紀の鏡である。
内行花文鏡全般において、連弧文と蝙蝠座鈕の間にある圏帯は
内側に櫛歯文を伴う圏帯→櫛歯文が省略され圏帯のみ→圏線に退化→すべて消失
という順に簡化していき、漢鏡6期(2世紀)において圏帯、又は圏線のあるもの(VA)と既に消失したもの(VB)とが共存する。
蝙蝠座鈕内行花文鏡の場合は、圏帯のあるものがI型、無いものが II型と呼称される。
この前半タイプI型が共伴する遺物の紀年銘には
A.D.94(洛陽近郊出土),105(長安出土),191(洛陽出土)
などがある。
2世紀末時点で既に伝世鏡であろう。
雲雷文のない四葉座内行花文鏡の成立する漢鏡6期の始期も、自ずと明確である。
◆FAQ 47
Q:魏志によれば「其國」には2世紀前半から男王が存在している!
2世紀末から始まる纏向遺跡では無理ではないか?
A:素より、「其國」=纒向遺跡と考える者は畿内論者には事実上いない。
魏志記す男王は、異説もあるが、後漢書謂う安帝永初元年請見せるところの「倭國王帥升等」とし、これを倭人の外交を事実上とり纏める立場にあった伊都国王に当てる見方が有力であろう。
これに倭国王と称すべき実態が具わっていたか否かについては寧ろ否定的に捉える必要がある。
弱体化した後漢帝室には東夷王度海奉国珍を積極的に求める動機があり、帥升「等」という表現からは倭国王をその他と隔絶した者として扱っていない漢朝の姿勢が窺知できるからである。
少なくともこの政治体制は、地域的統合の不首尾や甕棺分布域の縮小、漢鏡6期鏡の減少などから見て既に衰退期にあり、2世紀末には漢鏡を副葬する弥生首長墓の終焉とともに最終的な崩壊を迎えたものと推定される。(FAQ34,36参照)
倭国乱を収束に導いた卑弥呼共立と新生倭国の国家形成はこれと無縁であり、女王の都する所が桜井市纒向であることを妨げない。
◆FAQ 48
Q:そもそも纒向遺跡とはどの範囲を指すのだ?
考古学的に確認されているのか?
A:纒向遺跡は、考古学的な範囲確認調査により、旧烏田川河道から旧纒向川河道の間の扇状地に所在する複数の微高地上に展開する遺跡とされている。
遺跡建設の早い時期に大型の運河が開削され、また照葉樹系の花粉に代わり乾燥した人為地を好む草本の花粉が検出されるようになっており、計画的な開発行為が大規模に行われていた状況が窺知される。
桜井市教育委員会は旧烏田川河道北岸にも同遺跡が広がる可能性を指摘し、天理市にまたがる考古学的想定に基づいた遺跡全体図をも公表している(桜井市同遺跡保存活用計画書2016)が、柳本町及び渋谷町側で連続する遺跡は現状では確認されていない。
広大な遺跡であり、宮内庁を含めて地権者が膨大な数にのぼるため、調査には文化財保護法第四条3項はじめ種々の制約がある。
このため調査が及んでいる範囲は現状は未だ全体中の僅かな部分に過ぎないが、我が国における王権誕生への道筋を辿れる遺跡群として極めて重要視されている。
◆FAQ 49
Q:光武が印綬を賜うた委奴国はイト国と読むべきではないのか?
A:古代音韻史が未発達であった時代の謬説であり、過去の遺物である。
今日の定説では「奴」をdoと濁るのは隋唐長安音であり1世紀の発音としてあり得ない。上古音nagが順当であろう。
また、范曄後漢書に先行する袁宏(東晋)後漢紀光武帝紀にも「倭奴国」として現れており、「委」が「倭」と同義であることに疑問の余地が無い。
魯宣公倭が委とも表記されることからも通用が明らかである。
「宣公 名倭。一名接。又作委。文公子。」(杜預左氏伝註)
さらに「委」、「倭」の子音はwであり、伊都国はyであるので全く発音が異なる。
固より光武時には已に「倭人」という民族名が知られており、此の文字を同じ倭人の国名表記に、民族名としての倭という語義を含意させずに固有名詞「倭奴」として用いることも、就中発音の異なる表音文字として使用することも、凡そ正常な用字とは考え難い。
また、正式の国名が複合語であるケースも「(女偏に若)羌」「車師後部」など珍しくない。
◆FAQ 50
Q:纒向の大型建物群はそれほど画期的で空前絶後なものなのか?
どこにでもありそうだ。
A:建物群が大小とも中心軸を共有する規格性を有することは画期的であるが、計画的配置という点では伊勢遺跡という先行例がある。
画期的と言う意味では、建物及び囲繞柵列が作る空間が「庭院と回廊からなる朝庭」的空間を想起させる点は、接面する幹線道路の質と相俟って、柵列を伴う倉庫群と一線を画す。
纒向全体の規模と計画性を鑑みれば、必然的に比較対象は飛鳥等の宮処となろう。
勿論、箸中山・渋谷向山・行灯山の規模を考えれば誉田山・大仙に対応する未発見の宮処がより上位であることは予察されるものの、現状では飛鳥時代の宮処以前に纒向の大型建物群に比肩するような知見はない。
単に床面積のみ着目すれば時代的に後続する七尾の万行遺跡SB02(布留0併行)は大規模であるが、立地ならびに構造から見て用途が宮処ではないので、比較対象外である。
◆FAQ 51
Q:卜骨は九州にとって不利な条件ではないのだ!
壱岐や有明海沿岸で発見事例があるではないか!
A:九州説が倭人伝に照らして不自然である、という結論しか出ない。
灼骨卜占は倭人全般の習俗として記載され、考古学的知見と合致している。
郡使往来常所駐と云われる伊都国でその習俗が見当たらないのであれば、より重要な倭人の拠点ーー例えば女王所都のようなーーで目撃されたと推察するのが自然であろう。
壱岐で目撃され、奇異ゆえ印象的で記録に残ったとするならば、一支国の条に特記されるのが順当である。
弥生時代の卜骨の発見例は20都府県50余遺跡に及ぶ。
日本海ルートで能登・佐渡に、太平洋ルートで東海・南関東に波及し、弥生社会全般に広く流布した習俗と考えられるが、東山道・南海道及び九州本島で希薄である。
卜占を系譜的に辿れば半島よりの伝播であるが、博多湾岸地域に遺存例が無く、壱岐島から飛んで因幡の青谷上寺地と大和の唐古鍵の二遺跡に集中があることは、海上交通ルートの歴史を考察する上でも興味深く、この習俗と海上交通に従事する職能集団との関係が窺知される。
年代的に推移を見ると、弥生前・中期に壱岐ー山陰ー畿内と点在し、後期に瀬戸内ー畿内が浮上するからである。
ことに、唐古鍵で弥生後期初頭に成立したと考えられる卜占の技術体系タイプが、後期末頃までに九州を含む全国に波及していることも、興味深い。
五畿での出土例は以下の摂河和各遺跡
新方・森之宮(摂津)
雁屋・鬼虎川・亀井(河内)
唐古鍵・纒向・四分・坪井大福(大和)
ことに唐古鍵では弥生前期から後期まで連続して複数存在する。
◆FAQ 52
Q:纒向衰退後に邪馬台国はどうなったのだ?
A:双系制社会では平穏な地位継承でも盟主地盤が地理的に移動することが有り得るので、考古学的に見た中心地の域内移動は必ずしも政権交代とは断じられない。纒向の衰退は、◆8で述べた経済基盤の変化のほか、祭祀型盟主からの質的変化を含意している可能性がある。
奈良盆地内でも有意な地域集団は、式のほか葛城と添がある。大王級古墳の消長から見て、纒向(式)につぐ次期宮都は添の平城宮下層が有力候補地となろう。南山城・近江との関係が興味深い。(参考:塚口2012)
巨大集落遺構の確認されている葛城地域は対応する大王級古墳を欠いており、河泉との関係において更なる探求を要す。
甲冑保有形態から筑紫の老司・鋤崎両古墳が畿内の前期政権に近しい旧来の地方首長で、畿内の中期政権からは寧ろ牽制対象であったとする分析(藤田2015)には、式・添と河泉・葛城の間で盟主系譜の不連続が示唆されている。
◆FAQ 53
Q:一大率は女王の膝許で、その威光の元に権勢を揮ったのだろう?
A:諸国を畏憚せしむるような勢力者が特置され、その治所が伊都国に在ることは、博多湾岸が女王の都からは直接統治の容易でない遠隔地にあることを示す。当時は最も注意すべき検察対象に治所を定めたと理解するのが自然であろう。
此の「大率」の用字や発音が「襲津彦ー沙至比跪」や「筑紫率」と通底することは興味深い。
刺史は中央が派遣して地方に駐在する勅任官であり、任地の州に治所を置き地方官人事を三公府を経ず皇帝に劾奏する刺挙の吏である。
定期上奏は東漢初に在地出身の上計掾史の職務(続漢書所引東観漢紀、続漢書百官志州郡)へと合理化(「州牧自ら還りて奏事するを断つ」光武帝紀)改革されている。
秩禄の軽重や地方行政への関与度は年代により異なるが、監察官・軍監の職能と皇帝の使者としての性格は変わりない。
この刺史に類比されることで、大率が遠隔地に赴任して来た流官であることは明瞭であろう。但し、此の様な地方転出者が容易に土着して在地首長化することは、後世の少弐氏など枚挙の例に事欠かない。
◆FAQ 54
Q:一大率は女王国以北に置かれているんだ!
以北ってことは女王国も含むんだぞ!
A:実際の用例ではそうならない。
「從右北平以東至遼…為東部、從右北平以西至上谷為中部…從上谷以西至燉煌…為西部」
(三国志所引魏書鮮卑)
「自單單大山領以西属楽浪、自領以東七県都尉主之」
(三国志東夷伝濊)
「建安中、公孫康分屯有縣以南荒地爲帶方郡」
(同韓伝) ※屯有県は楽浪に属す。
◆FAQ 55
Q:韓は倭と「接」している。地続きだ。
狗邪韓国は倭人の国の一つだぞ!
A:「接壌」とあれば地続きであるが、「接」だけでは根拠にならない。
外接遼東、得戎馬之利(続漢書孔融)
山東省の刺史が遼東と「接」
訶陵國、在南方海中洲上居、東與婆利、西與墮婆登、北與真臘接(旧唐書南蛮)
海中の島国がカンボジアと「接」
狗邪(伽耶)は金官国、安邪(安羅)は咸安郡と、3世紀に主要な遺跡のある半島南岸は弁辰の諸韓国で占められ、3世紀前半は弁辰韓V期の文化圏である。(高久1999,久住2006,朴2007)
倭人の国ではあり得ない。
◆FAQ 56
Q:「世有」は「代々」という意味ではない。「魏の治世に」という意味だ!
A:「世有」には「代々…」という意味と、「世間には…」「この広い世界に…」などと訳すべき用例がある。「魏の治世に」という意味はない。
「世間に…」in the world の用例
・「世有人愛假子如孤者乎?」(魏氏春秋秦朗)
・「世有仁人、吾未之見。」(先賢行状王烈)
・「世有思婦病母者、豈此謂乎!」遂不與假。吏父明日死,思無恨意。(魏略王思)
・「世有亂人而無亂法」若使法可專任、則唐虞可不須稷契之佐、
殷周無貴伊呂之輔矣(杜畿子恕)
※範囲は全世界、時代は魏朝に限らず、いつの時代にも不易
※これらは不特定者someoneの存在を示唆する例である。
「代々…」の用例:
・魏因漢法、母后之號、皆如舊制、自夫人以下、世有增損。
太祖建國、始命王后、其下五等…(后妃傳第五)
※漢朝下の魏王の頃から魏朝まで代々変更を重ねている。
・世有名節、九世而生寧。(傅子管寧)
※田斉を去った管仲の子孫が、漢代に北海で家を再興してから9代目が管寧
・袁氏子孫世有名位、貴達至今。(裴註袁渙)
※袁渙の父は漢朝の司徒、渙は魏武に重んじられ、子孫も顕官に達し晋朝に至る。
・今汝先人世有冠冕(王昶)
※のち魏の司空となる王昶が子と甥に語る訓戒
昶の伯父柔は漢護匈奴中郎将、父澤は代郡太守、兄で甥の父機は魏東郡太守
当然ながら先人は王昶一人のことではなく、父祖代々を指す。
・臣没之後、而奮乎百世、雖世有知者、懷謙莫或奏正(翻別傳)
※百世に亘って代々を想定
◆FAQ 57
Q:弥生時代に前史を持たない纒向がなぜ宮都の地に選ばれるのか?
必然性がない!
A:奈良盆地は古奈良湖の消失過程にあり、河道周辺の未乾燥地を稲作向きの農地へと、木製農具でさえ容易に開墾可能であった。
この特性により、奈良盆地は高い人口吸収力を有し、移民を誘致しやすく、首長権力の伸長(◆6参照)を可能とする立地条件を具備していた。
法隆寺付近や島の山古墳の東西に弥生遺跡が分布していることで、当時既に古奈良湖の痕跡は極めて狭隘な残存部分しか存在していなかったことは明らかである-
 「大和弥生社会の展開とその特質」寺澤2016
「大和弥生社会の展開とその特質」寺澤2016
( 奈良盆地の弥生時代の遺跡分布と基礎地域 『纏向学研究 4』 p6 図2)
-が、河合町の川合浜等の地名からも判明するとおり、奈良盆地各地を縦横に結ぶ大和川水系の水運は近世まで盛んであった。
居住に適した微高地を水稲耕作にqqqqqqqq 適した低地が囲む単位集落が無数に発生し、それらが水運で結ばれることで、自然国境に局限されない国家形成を支えるインフラが予め準備されていたと言える。
加えて、三輪山麓は交通の要衝(◆4参照)である。東海S字甕の拡散ルートである東山道に依存せずに交易ルートを東に伸ばすには、初瀬街道から中勢に抜けて海路を確保するのが要諦であった。
大和川水系に属し、且つ、上つ道で淀川水系を経て摂津山背・東国・北陸・但丹狭へ通じる交通網の多重結節点である当地には、塞の神が祀られる必然性がある。
畿内及びその隣接地各地の首長が会盟し、調整の裁定を大巫女に仰ぐ場所としては、近隣首長の色が付いていない纒向の地が適切であろう。 ◆FAQ 58
Q:行程論で検証すると、畿内説は無理ではないのか!
A:行程記事には、方位・距離ともに誤情報が含まれていることが明らかなので、所在地比定には採用しないが、検証には用いる(関連:◆FAQ1)
「自郡至女王國萬二千餘里」のうち、九州本島到着までに萬餘里相当を費消済みであるので、行程解釈で伝統的な連続説或いは放射説の孰れに依拠しても、残余は1,300~2,000里となる。
これは魏尺24cm×1,800尺=1魏里432m換算で概ね562~864kmに相当する。
参考値として博多港より奈良県桜井市の三輪参道入口(大鳥居前)までフェリー航路と現代の道路上の通算距離を得ると、直行航路の場合概ね620km、寄港地11設定の場合概ね793kmとなり、妥当な範囲に収まり適合する。
「南至投馬國水行二十日」「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」
より、連続説に依拠し所用日程を通算した場合
「大宰府海路卅日」(延喜式卷第廿四主計寮上)と照合して水行日程が妥当である。
また、推古紀所載裴世清の旅程より
「六月壬寅朔丙辰、客等泊于難波津。是日以餝船卅艘迎客等于江口安置新舘」
「秋八月辛丑朔癸卯、唐客入京。是日遺餝騎七十五疋而迎唐客於海石榴市衢」
以上48日経過である。外交使節旅程の類例に照らし、陸行日程が妥当である。
さらに、里程1,300~2,000里を日程合計60日で除すると約22~33里@日で「師行三十里」(漢書律歴下)、「師日行三十里」(同王吉伝)等と整合性がある。
また、既知の日程から距離を逆算したと推定される類例がカローシュティ文書(楼蘭~精絶)等に見出せる。上記通算日程60日に30里@日を乗じて1,800里が、25里@日の場合1,500里が得られる。
以上、結論として検証に耐える。但し、この試算は邪馬台国の位置比定に使用しない。
◆FAQ 59
Q:「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」
の起点は帯方郡である! 畿内に到着し得ない!
A:不合理である。
「南至」が「倭人在帶方東南大海之中」と矛盾する。
また
1「南至投馬國水行二十日」
2「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」
は構文が同じであり、「南至邪馬壹國」の起点を帯方郡とするなら「南至投馬國」の起点も帯方郡にせざるを得ないが、投馬国には水行のみで到着し得る。
よって韓地陸行説が蹉跌し、陸行日程が韓地で費消し得ないため帯方郡起点説は成立し得ない。
◆FAQ 60
Q:「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」のような日数表記が
「東行至不彌國百里」のような里程表記と混在するのはおかしいではないか!
所用日数を別に記したのだ。日数の起点は帯方郡である!
(且末國)去長安六千八百二十里。…西北至都護治所二千二百五十八里、
北接尉犂、南至小宛可三日行、…西通精絶二千里。
(精絶國)去長安八千八百二十里。…北至都護治所二千七百二十三里、
南至戎盧國四日行、…西通「手偏に于」彌四百六十里。
(ケイ賓國)去長安萬二千二百里。不屬都護。
…東北至都護治所六千八百四十里、東至烏「禾偏に宅の旁」國二千二百五十里、
東北至難兜國九日行、西北與大月氏、西南與烏弋山離接。
(烏弋山離國)王去長安萬二千二百里。不屬都護。
…東北至都護治所六十日行、東與ケイ賓、北與撲挑、
西與犂「革偏に于」・條支接。
行可百餘日、乃至條支。…自條支乘水西行、可百餘日、近日所入云。
(大月氏國)去長安萬一千六百里。不屬都護。
…東至都護治所四千七百四十里、西至安息四十九日行、南與ケイ賓接。
(姑墨國)去長安八千一百五十里。
…東至都護治所二千二十一里、南至于闐馬行十五日、北與烏孫接。
(以上、漢書西域上)
◆FAQ 61
Q:「到其北岸狗邪韓國、七千餘里」
これは実測したとしか考えられない!
誤りというなら誤りが発生した理由を明らかにせよ!
A:未知の単位系が存在すると帰納的に証明されていない以上、魏尺実寸に照らして誤りとするほかない。錯誤発生の原因特定は再発防止以外の意義を認め難い。
戦果報告は十倍にして公表する習慣がある。「二郡遂滅韓」の戦果報告が誇張されていて不思議はない。 「破賊文書、舊以一為十」(国淵伝)
或いは「方四◯◯里」が「四方◯◯里」と同義に使用されることがあり、混用による錯誤も有り得る。
また、倭奴国王の朝貢が万里の遠国と顕彰された形跡が有之、これが規定値として固定され、渡海3回と按分された可能性を考慮する必要がある。FAQ58に述べた約2,000里と合算すると万二千里が得られる。
「建武之初…時遼東太守祭肜威讋北方聲行海表、於是濊貊・倭韓萬里朝獻」
(後漢書東夷)
「如墨委面、在帶方東南萬里」(如淳)
さらには、大同江河口の鎮南浦より仁川・木浦・麗水を経由して釜山に至る航路は1,296km(距離表S22)である。
ここで交州~交趾の約5,000里が現代の航路で900kmであるから(「靖尋循渚岸五千餘里」許靖伝 )往時航路の紆曲と心理的負担感及び苦難の誇張を加味した倍率として認識しつつ、この比率を上記に乗ずると、7,200里が得られる。
このように、倭人伝所載の非現実的な里程の発生には幾らでも原因の想定が可能である。公文書に現れる両漢魏晋の度量衡に照らして其れらが間違いであると判定する以上の詮索は不要であろう。
◆FAQ 62
Q:帯方郡や狗邪韓国をどこに比定しているのだ! 明確にせよ!
A:定説に従う。
金石文等により、楽浪郡治が平壌市楽浪区土城里、黏(虫偏に單)県が温泉郡城(山偏に見)里土城。南浦市江西区台城里は県名未詳。
帯方郡治が鳳山郡智塔里土城、郡の外港と考えられる列口県城が殷栗郡雲城里土城(南浦の対岸付近)、旧南部都尉治の昭明県城が信川郡北部面青山土城、長岑県城が信川郡信川邑、含資県城が安岳郡柳城里に比定される。
二郡は孰れも大同江水系に展開し、遺跡分布より、帯方郡は支流の瑞興江・載寧江及び西江流域流域、北を慈悲山、南を滅悪山脈の長寿山まで沙里院・鳳山郡・銀波郡・麟山郡、西を載寧郡・新院郡・銀泉郡・安岳郡・信川郡・殷栗郡・三泉郡・松禾郡の区域と考えられる。
近代的道路が整備されるまで滅悪山脈は迂回せねばならず、同山脈以南で墓制の異なる碧城郡・海州市は郡域外であろう。
以下、漢系遺物を多数出土する韓系遺跡が、伯済国とされるソウル風納洞・夢村から、月支国と目される天安清堂洞、そして泗川勒島、義昌茶戸里、馬山を経て金海まで海路で結ばれている。金海良洞里及び大成洞が弁辰狗邪(狗邪韓)国に相当する。
楽浪と濃密な交渉実績のある交易拠点遺跡が沿岸部や島嶼部に点在することから、沿海航路が重要な通交ルートであったことが明らかである。
◆FAQ 63
Q:旧唐書に「倭国者古倭奴国也」とある! 倭国は九州にあった倭奴国の後身なのだ!
A:「古○○也」は政治的連続を表さない。
同じ旧唐書に「(獣偏に奇)氏 漢縣、古郇国也」等とあるのと同じである。
唐の河東道(獣偏に奇)氏県は、周代の姫姓侯国であった郇国が戦国時代に滅び、変転を経て漢代に郡県に編入された地であり、姫姓郇国からの政治史的・系譜論的な関連は無い。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上テンプレ
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
注意*前スレが終了してから書き込んでください。
なお、書き込みは
邪馬台国畿内説に関係が有って
根拠のある内容をお願いします。
畿内説以外の独自説を単独で開陳することはご遠慮ください。
前スレ終了以前の書き込みは荒らし行為と看做させて頂きます。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【追加・変更点】 ◆FAQ 57に図を追加
邪馬台国はヤマト国、葛城山系以東の奈良盆地一帯です。邪馬台は単なる地名です。ヤマトの地が卑弥呼を共立した勢力に征伐され、都が置かれました。
纒向の外来系土器、円形周溝墓などがその証です。殉葬などそれ以前になかった風習が持ち込まれたことも、新しい別の勢力がヤマトの地を支配した傍証になります。
女王国、大和朝廷を作ったのは、出雲など山陰の勢力、尾張三河など東海の勢力、阿波、宮崎や遠賀川の石神など、縄文系勢力と縄文系勢力に半分乗っ取られた古い海神。
畿内や九州北部の渡来人系勢力はこれらの勢力に征伐されました。
魏志倭人伝当時、狗奴国の版図であったなにわの地は陥落しています。
魏志倭人伝当時の狗奴国は邪馬台国ヤマト国の南。和泉と河内です。
334の
>>580 >>当然、案内人や道標や道なり道に従って進むから、道に迷わないし、<
>じゃ、出発の方角も書く必要ないし、突然なぜか途中からの距離を書くことも、なにも必要ないな
なんで、そんなこと書いてある?<
皇帝に報告して大体の行程を判ってもらう事と、
後にまた倭国へ来る使節にも参考になった方がよいから。
>>584 >>「主行程」記載は、不彌國から「南至邪馬壹國、女王之所都」であるから<、
>なら、水行10日陸行1月が帯方郡からの日程だというのは、真っ赤なウソだな<
×だな。
「水行10日陸行1月」は、その直前の「女王之所都」に対する説明文になるのであり、
「女王之所都」は、「從郡至倭」の目的地であるから、
「從郡至倭~女王之所都」の日数説明の文だ、という事になる。
>>586 >纏向が成立した後は関係ない
東海地方は遅れて参入した地域で邪馬台国の主体じゃない
あくまでも邪馬台国成立前の主体となった勢力は吉備<
「邪馬台国」なんて存在していなかった。
そして、吉備も大和も、
筑紫倭国の「東征毛人55国」の「倭国の植民」の地。
>>587 >「壹と臺」が書き分けられている という根拠なし それは単なる主観<
「壹拜」と「因詣臺」とが、きちんと間違えずに書き分けられている。
>>590 >近江、東海の勢力は邪馬台国成立前は独自の広域連合のようなものを作っていた様子が見える<
近江、東海は、(出雲系の)「見る銅鐸」部族であったが、
筑紫の倭國の「東征の毛人55国」に拠って、倭国系と出雲系や越系の混合地域になり、
やがて、筑紫倭国の支配下になって、銅鐸祭祀も消えていった。
>邪馬台国成立に際してこの構成員として参入して発展的に解消して取り込まれた流れと思われる
その流れの中で多少の小競り合いがあってそれが狗奴国との戦いとして残されているんだろう<
邪馬台国なんて存在しないし、狗奴國も「南≠東」に拠って」×。
>>592 >畿内はⅤ式の頃に侵入を防ぐかのような高地性集落が出来ている<
高地性集落は、筑紫倭国の繰り返しの東征軍に圧迫されてのもの。
>これが対外なのか、それとも内部的な統一の流れの話なのか
寺澤氏は安定した農耕社会の畿内での劇的な変化は強力な外圧のようなものを想定してるな<
寺澤は、倭国の東征毛人55国の事を失念しているアホ。
【守銭奴】 株・FX・トレーダー <キリスト"再臨″> 史上初テレパシー演説 【救世主】
http://2chb.net/r/liveplus/1521080734/l50 >>598 >畿内はⅣ式の頃までは拠点集落も安定して存在していて大きな変動がないがⅤ式になるとみてわかるような変化が起こる
この時期の急激な変動は何らかの強い力が働いたとみるしかないな
この辺は色々な学者の意見が一致してる<
筑紫の倭国の「東征毛人五十五國」があったから。
>>599 >纒向遺跡の初期の外来系土器は東海が主体だぞ。<
大和にも、筑紫倭国の「東征毛人」軍が来ていたし、
倭國の「地方の市を監督する大倭職」もいたから。
>邪馬台国の母体は東海の勢力だよ。<
「邪馬台国」なんて存在しないし、「母体」は、と東征軍と市。
>狗奴国と東海は全く関係ない<
「南≠東」に拠って、×。
>>604 >そもそも東海の土器の分布を見れば東海に邪馬台国の主体がないのは明瞭
あくまでも吉備、畿内の土器がその主体<
土器は、生活用品であって、市を介して販売されるものであり、
武器などのような、国家や部族の「支配」の関係を示すものではない。
>>607 >テンプレは「南」が「東」の間違いだと 論拠をあげて主張してるんだから
「南≠東」問題から逃げたと言うのは 真っ赤な嘘でしょう<
テンプレの論拠が、
「大和が筑紫倭國から別れた別種の旧小国」
という史料事実や史料実態を隠蔽したウソ論理であったから、
論拠になっていないんだよ。
>>66 >>>「主行程」記載は、不彌國から「南至邪馬壹國、女王之所都」
これ、ザラコクが 自分で書いた文だぞww
>×だな。
×はザラコクだww
自分で『「主行程」記載は、不彌國から』と書いておいて
『「從郡至倭~女王之所都」の日数説明の文だ』とかよく書けるよな
本当に、「何の根拠もなく思いつきで書いている」ってことを
「自分のコメントの中で矛盾を示しながら暴いていく」スタイルww
儒教道徳で生きていると、間違い一つ認められなくて大変だね
同情はしないけどさ
軽蔑はするけど
>>610 >>(鏡片は)親愛なる部下へのペンダント的な下賜品であったようで、<
>ザラコク独特の思いつきだね 根拠も皆無だし w<
破砕して出来た鏡片の角をこすって縁を滑らかにして、
角に近いところに「孔」を開けて、ひもで吊るせるようにも、なっていた。
>>77 逆に聞いてやればいいんだよ。
どんな相手に破鏡を与えたのか。
どうせ答えられない。
>>55 > 畿内及びその隣接地各地の首長が会盟し、調整の裁定を大巫女に仰ぐ場所としては、近隣首長の色が付いていない纒向の地が適切であろう。
ちょっとテンプレを読んでみたら、1行ごとに気持ち悪い文章が出てきて耐えられなかった。
奥村はやはりおかしい。
>>664 >南洋系というが、 奈良は宮崎系というよりは、 熊本系<
王年代紀や新唐書に拠って、神武は倭奴國の(天孫族の)阿毎氏系。
筑紫の俀國のタリシホコも阿毎氏。
宮崎は、(阿毎氏の)神武らの父のウガヤフキアエズの の)赴任先。
「自女王國以北 特置一大率 檢察諸國 諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史」
この文章の前後の文章は全て女王国か女王卑弥呼に付いての説明文であり、主語が書かれていなくとも主語は女王国か女王卑弥呼だと読み手には分かるようになっている。
それ以外の主語の場合は「諸國畏憚之」のように主語が明記されている。
「一大率常治伊都國」と主語が明記されていないので「常治伊都國」の主語も女王卑弥呼である。
なので「女王卑弥呼が伊都国で常に治めている」との意味になる。
では何を治めているのか?
女王卑弥呼が治めているのは自女王國以北の諸国である。
「常治伊都國」は「(女王卑弥呼が)伊都国で(一大率を使い自女王國以北の諸国を)常に治めていた」の意味であり 主語の女王卑弥呼と()内が省略されている。
治の類似の用法は漢書西域伝に見られる。
「大宛国 王治貴山城 去長安 万二千五百五十里…」
大宛国について、王は貴山城に治す、と王の所在を明らかにしている。
では「自女王國以北」とはどこか。
以北はその出発地を含む。出発地は「自女王國」とある。
つまり、女王国とその北にある国々を、そこに置いた一大率で支配したのである。
要するに女王国と伊都国は念を押して言い換えただけであり、一大率は伊都国にあり、伊都国が女王国、女王の都するところ、邪馬台国であるということである。
「於國中有如刺史」・・・刺史は各地の行政機関内に常駐している監察官
「女王国(を含めたそこ)から北の諸国には、(女王卑弥呼が)特別に一大率を配置して検察させており、諸国は(一大率を)畏れ憚っている。
(女王卑弥呼が)伊都国で(一大率を使い女王国から北の諸国を)常に治めていた。
これは魏で皇帝が刺史を州に派遣し検察させて洛陽で治めているのと同じようだ」の意味となる。
女王国が伊都より東にあったら、文章の意味が通らない。
畿内説では、一大率が支配していたのは奈良(女王国)およびその北である京都や丹波になってしまう。
女王国以北はおよそ里程や概要を記すことができるとされているが、里程が記載されているのは対馬海峡と福岡県内の国だけだからである。
すなわち女王国以北(女王国を含む)は伊都から北であり、女王国(邪馬台国)が伊都国であることを示している。
畿内説は実は東遷説だな。
【畿内説の主張のまとめ】
(奥山氏
>>1の発言をまとめたもの)
「伊都国の太陽祭祀を継いだ卑弥呼が、瀬戸内海勢力の実力を背景として、総花的に纏向で共立された」
「首長のいない広域政治集団が発生したが、圧力が高まって、急激な首長権が確立した」
「弥生中~後期に隆盛を誇った伊都国は、蝋燭の最後の輝きをはなって音もなく衰退した」
>>82 また岡上が露骨な捏造してるな
バカじゃないのか?
>>701 >末盧国がどこにあるか、きちんとぐぐってみなよ
自分がどんなにバカか分かるぞ<
何だ?。お前が「松浦」だ、という変な解釈を言っていたんだぞ?。
>大理と、成都と安南の位置を地図で確認するなんて<
大理なんても、お前の解釈であるだけであり、
成都の西南2400里の地であれば、そこから安南は東~東南東であり、
東で間違っておらず、
東なら「如至成都、通水陸行」の説明とも合う。
>>75 >「大和が筑紫倭國から別れた別種の旧小国」
>という史料事実や史料実態を隠蔽したウソ論理であったから、
そんな史料事実は無くて捏造だから、×。
>>706 >抹殺してないだろ
歴代天皇の名前に「倭」が何度も登場するんだから<
記紀の「盗用造作」の方だ。
>>84 >成都の西南2400里の地であれば、そこから安南は東~東南東であり、
現実の地理はまったく無視か・・・
さすが九州説
この時代の情勢を抜きにしては正しいことは分かる筈がない。
まず、方形周溝墓を墓制とし、絵画土器を威信材する勢力が日本の広範囲を支配下に収めてた。
それが和国大乱によって分裂した。
以下は勝手に考えてみてくれ
>近隣首長の色が付いていない
つまり外部からの占領
>>723 >(『魏志倭人伝の考古学』佐原真から)<
佐原も「南→東」の嘘吐き騙しの・・・・学者のようだな。
>>724 >畿内の邪馬臺→邪靡堆(大倭、大和)<
邪馬臺も邪靡堆も筑紫だから、×。
>>739 >>竹島→壱岐が東 <
>対馬を経てるのに?<
「至」と書いていないのに?。
>九州説は史料を歪曲するんだね <
大和説者は、「南→東」と同じように、
「經→至」の史料歪曲をするんだね?。
【葛城鴨王家の系譜】
大和国葛城にいた古代氏族の系譜。
その祖は博多の王である大山祇の子であり、摂津に鎮座する三島溝杙耳(陶津耳)である。
その息子は登美に移住して神武と戦った長髄彦であり、娘は活玉依姫である。
出雲の国譲りの後に大和に移住していた事代主は三輪山の神となっていたが、活玉依姫に娘と息子を生ませる。
娘は後に神武の妃となるイスケヨリ姫(五十鈴姫)であり、息子は天日方奇日方(櫛御方)である。天日方奇日方はまたの名を鴨主という。
天日方奇日方の曾孫が太田多根子となる。
この家系には別の伝承がある。
飛鳥大神の娘である登美夜姫が、高天原からやってきた天照の孫であるニギハヤヒとの間に生んだ子が、物部氏の祖であるウマシマジである。
登美の長髄彦は、神武との戦いの中で「自分は天神の子であるニギハヤヒに仕えて妹をニギハヤヒに娶らせたが、どうしてまた天神の子と称するものが来て土地を取ろうとするのか」と言っている。
とすると、登美夜姫と活玉依姫はともに長髄彦の妹ということになる。
いずれにしても、大和国の主だった勢力はいずれも筑紫か出雲、高天原にその起源があることになる。
>>92 >「至」と書いていないのに?。
何度言えばいいんだろう
ザラコクは漢文読めないんだから無理するなって
至るって書いてなくても経るって書いてあるだろ?
反論にも何もならないことを自信満々に書いちゃうところが
ザラコクだよな
間違いが認められない儒教道徳者ww
ついでに書いておくと、「至」と「到」には特段に使い分けはないぞ
例えば
三國志卷一/魏書一/武帝紀第一
太祖兵少。
乃與夏侯惇等、詣揚州募兵。
刺史陳溫丹楊太守周昕、與兵四千餘人。
還「到」龍亢、士卒多叛。
「至」銍建平、復收兵得千餘人。
単純に対句になってるのが分かるだろ?
そして、「到」と「至」に意味の差はない
傍線行路だの主線行路だのの区別はないんだよ
>>91 >邪靡堆
これ、なんて読む気だ?
これ、通な文字化け(?)で、邪摩堆のまちがいというのが通説
これもヤマトって読むんだよ
伊都国あたりに「ヤマト」って読む地名ないだろ?
もちろん、太宰府付近にもないぞ
普通に伊都国=邪馬壹国なんてないからww
六拾弐病
六拾弐病(ろくじゅうにびょう)とは、定年退職後の老年期に見られる、
周囲を見下した言動や、自惚れに満ちた妄想を連呼する様などをさす語。
自らを客観視することができず、盲目的に自身を絶対化する、というのがその典型的例。
現役時には社会に適合してゆくために相対化させざるを得なかった自己が、
定年によって自らをとりまく環境が急激に変化することで相対化のバランスを失い、
自分が特別な存在であって欲しいとする願望が顕在化することで発症する。
簡単に言えば、「俺様偉い病」である。
その思考の基礎となる知識は、遠い昔に聞きかじった程度の浅いものや、
定年で生じた余暇によって取得した程度の中途半端なものであるため、
罹患者の主張は往々にして突飛な妄想でしかなく、周囲に受け入れられることはない。
しかし、本人は自身の思考は特別に優れているものだと盲信しているため、
受け入れられない原因を周囲のせいであると主張し、攻撃性を高めつつ、負のスパイラルへと堕ちていく。
このため、「六拾弐病」は陰謀史観との相性が非常によい。
なお、「六拾弐病」の名は、定年後数年を経て症状が顕在化することから名付けられたものであり、
もちろん全ての罹患者が62歳で発症するものではない。
似た症状を呈するため、「六拾二病」は「老年性中二病」と称されることもあるが、
思春期に自身を特別な存在だと仮想する「中二病」が、
確立されていない自己とそれを取り巻く社会の拡大とに折り合いを付けられず、
自己を疑似的に絶対化することで周囲との相対化の波から逃避しようという、
いわば自己防衛的な理由によって発症し、
ほとんどの場合本人の成長とともに症状が改善されるのに対し、
「六拾弐病」は、罹患者が生来持つ傲慢さがその根底にあるため、
一度発症してしまうと、死ぬか、惚けて思考能力が失われるかしない限り、
症状が改善されることはないとされる点は対照的であるといえる。
全1病
全1病(ぜんいちびょう)とは、邪馬台国畿内説スレに出没する九州説論者のみが発症する、心の病。
畿内説側の書き込み全てが
>>1◆UiepmfCeDJqによる物であると信じ込む、一種の強迫観念である。
学問の世界ではすでに追い詰められている、という事実を認めたくない九州説論者が、
畿内説に多くの賛同者などいるわけがないのだ、と自分自身を騙そうとすることで発症する。
>>1◆UiepmfCeDJqが自演によって多数派を装っているのだ、と言う発想は、
実は、自身が自演を頻繁に行っているという事実の裏返しにほかならない。
現時点では治療法は発見されておらず、一度発症すると死ぬまで治ることはない。
ザラコク
邪馬台国関連スレに出没する非常識異常行動者のひとり
呼称は、Yahoo掲示坂で使用していたハンネ「zarakoku」から
古田武彦と彼が提唱した九州王朝説を盲目的に信仰しており、その信心の深さは、
世間的には偽書として決着している『東日流外三郡誌』を未だに真書であると主張するほど
自らを「素人おじん」と称することもあり、一見、自身を客観視できているかのようであるが、
その書き込み内容は、自分の信奉する説以外はすべて間違いだと決めつけてかかる、六拾弐病患者特有のもの
素人が専門家をこき下ろすという行為に疑問を感じなくなっているほど思考が硬直化している
「全レスバカ」と呼ばれることがあるほど片っ端からレスを付けまくるが、
ほとんどが他人の会話への横レスかつ超遅レスであり、周囲と会話が成立することはまずない
レスを付けることが目的化している節があり、その内容は、
他人の発言を長々と全文引用したあげく、賛成!とか間違いだ!とか数文字書き足すという程度のもの、
自分の都合のいいように語句を入れ替えただけのオウム返しのものなど、無意味なものばかりである
投稿数だけは圧倒的で、コピペ連投並みにスレを荒らす結果となっているが、本人に自覚はない
社用のPCで勤務時間中に5ちゃん投稿に血道を上げる問題経営者である
自分に不都合な情報を自分に都合が良いように勝手に脳内変換していることが多いが、
ソースを提示されても、自身の記憶や理解の方が正しいと主張する、傲慢な思考の持ち主
常駐していたYahoo掲示板を倫理規定に触れて出禁になったらしく、最近5ちゃんに居付いてしまった
「生きる独善」との形容がぴったりな75歳
キウス
邪馬台国関連スレに出没する真性の基地外であり、病的なウソつき。
「希薄」を読むことができず、「箕臼(キウス)」と誤変換し続けたことから「キウス」と呼ばれるように。
自演爺、四棟粘着爺、指さし厨とも。
ウソの書き込みや自演、成り済ましを平然と行い、畿内説スレの
>>1を騙り偽スレを立てること数度。
>>1のトリと同じ英数字を名前欄に書き込んで成り済まそうとしたこともある、最低のクズである。
「全1病」罹患者にして典型的「62病」発症者。
「自論」、「私見」、「勉強してください」、「学がない」、「貴君」、「しかり」など特徴的な言い回しの多用、
5ちゃんでは一般的ではない「スレ主」頻発、名前欄への書き込み多用などの特徴ですぐに判別できる。
1◆UiepmfCeDJqfを奥村と呼ぶ、寺澤薫氏・同志社大学・纒向学研究センターをディスる、
草を生やす際に半角で1文字目大文字、?を連続させる、といった特徴もある。
キウスの書き込みを褒めたり、礼を言ったり、「ワロタ」と応じたりする書き込みは、すべて自演である。
他人を騙す行為も自分ならばすべて許されると信じている節のある、傲慢の塊である。
日本語の読み書きが満足にできないこと、日本史や日本の地理に関する基礎知識がないことなどから、
日本の義務教育を受けていないどころか日本国内に居住していないのではないかと推測されている。
岡上
邪馬台国関連スレに出没する狂人のひとり
考古学界では全く賛同者がいない説を「考古学的に確定している」と主張し、ありもしない大規模調査をでっち上げ、
学界の多数派である邪馬台国畿内説を破綻したと主張する、ゴッドハンドも真っ青の捏造常習犯である
自分は正しく、これまでの研究者がみんな間違っていた、などと平気で主張する、典型的「六拾弐病」患者
コテ+トリと、コテの九州王、伊都国女王、卑弥呼、名無しを使い分け、自説を関連スレで書き込みまくる
糸クズ、八咫バカ、連続句読点キチともよばれる
「咫」の説明である「周尺」を「円周の尺」と読み、
伊都国を女王国であると漢文の用例を無視して誤読し、
平原遺跡出土鏡の文様には八咫烏があると現物を知らないで主張し、
魏志倭人伝中の「下戸」を「酒が飲めない人」と訳すなど、
お笑いエピソードには事欠かない
偽スレや妄想スレを立て続ける異常性に気がついていないのは本人だけ
未確定な事項であっても、自分に都合がよければ勝手に確定事項であると脳内変換し、
それを根拠として立論してしまうチェリーピッカー
日本史の方法論をまるで理解していない、自分偉い教の教祖である
ザラコク
>…< 嘘吐き騙し 南≠東 大和説 !。 ?。 ×。
キウス
スレ主 奥村 しかり 大笑い Ww いい線ついてる 正論 ヤマト王政 論じろ
岡上
八咫の鏡 伊都 平原 内行花文鏡 三種の神器 神道 キナイコシ 、、、 。。。
ハナホジ
物部 葛城 鴨 大物主 ヒメタタライスズ ミミ 出雲族
サイキバ
鉄がない 奈良湖 倉庫
2013年の大規模調査なんてない
日本経済新聞(2013/2/20)
卑弥呼の墓?初の立ち入り調査 奈良・箸墓古墳
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1905C_Q3A220C1CR0000/ 研究進展に期待
日本考古学協会など考古学、歴史学の15の研究者団体は20日午前、
宮内庁が陵墓として管理している奈良県桜井市の箸墓古墳を立ち入り調査した。
宮内庁が研究者側からの要望に応じて立ち入りを認めるのは初めて。
同古墳は邪馬台国の女王・卑弥呼の墓とする説もあり、陵墓の公開や研究の進展につながると期待されている。
立ち入り調査をしたのは研究者16人。
約1時間半をかけて墳丘の最下段を一周し、地表に見える葺(ふ)き石や土器などの遺物の状態、墳丘の形などを観察した。
参加した日本考古学協会の森岡秀人理事によると墳丘表面で、築造以前の様子を示す弥生最末期の土器などが見えたという。
森岡理事は「古墳の詳しい状況を実感できた。今回得た知見や印象によって研究が加速するのでは」と話し、
今後の陵墓公開に向け「国民の文化遺産として大切に守るべきもの。宮内庁とさらなる協力体制を目指したい」と強調した。
研究者らは午後、宮内庁が管理する西殿塚古墳(同県天理市)も調査する。
650日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:03:02.66
元ねた見つけたわ
国土地理院時報(2000 no.94)
「近畿地方の古地理に関する調査(国土地理院地理調査部)
http://www-im.dwc.doshisha.ac.jp/~nihei/nara/index.php?%C6%E0%CE%C9%CB%DF%C3%CF%A1%A7%C3%CF%B7%C1%A1%A6%C3%CF%BC%C1%A1%A6%BF%E5%B7%CF
657日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:12:52.10
>>650のリンク先にある「奈良盆地の地形学的研究」53ページに
>なぜなら、奈良盆地が更新世以降において湛水し湖沼化したという事実は認められない。
とあるな
660日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:18:00.17
奈良県遺跡地図Web
http://www.pref.nara.jp/16771.htm 664日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:21:12.40
データベース名 遺跡
ID 11A-0104
市町村 川西
遺跡名 下永東方遺跡
所在地 磯城郡川西町下永東方
種類区分 集落・町屋,社寺
時代区分 縄文,弥生,古墳,奈良,平安,鎌倉,室町
時代詳細 縄文・晩~古墳・後、奈良~室町
遺跡概要 方形周溝墓、井戸、掘立柱建物、区画溝
遺物 縄文、弥生、土師、須恵、黒色土器、中世土器、木製品、石器、石製紡錘車、土馬
文献・備考 白米密寺伝承地、『下永東方遺跡』(文化財報86)2001、『奈良県遺跡調査概報2003年度第1分冊』2004、『奈良県遺跡調査概報2004年度第1分冊』2005
668日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:24:19.31
データベース名 遺跡
ID 11A-0123
市町村 川西
遺跡名 下永東城遺跡
所在地 磯城郡川西町下永東城
種類区分 集落・町屋,墓・墓地
時代区分 縄文,弥生,古墳,鎌倉,室町
時代詳細 縄文、弥生・中、古墳・前~中世
遺跡概要 方形周溝墓、土坑、掘立柱建物、井戸
遺物 石器、弥生、土師、石釧、木器
文献・備考 『下永東城遺跡』(文化財報103)2003
674日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:37:38.33
http://www.ksmt.com/panorama/130501nara/130501nara.htm >2013.5.1 Kashihara 橿原
>飛鳥を自転車で回ろうと思い近鉄橿原神宮前駅へ。
>まず奈良県立橿原考古学研究所付属博物館の「5世紀のヤマト~まほろばの世界~」を見学。
>5世紀の遺跡から出た資料が展示されており興味深いのですが、最も興味を引いたのが5世紀の地図。
>古奈良湖は既になく、奈良盆地全体が陸地をして描かれています。
(略)
>橿原考古学研究所の受付の方にお願いすると、水田の発掘担当者の方に直接話を聞けることになりました。
>運が良かったようです。
>担当者の方の話によると、
>
>1.縄文後期の遺跡が奈良盆地の一番低いところにも存在するので、縄文後期には既に古奈良湖は消滅していたと考えられる。
>法隆寺付近に古奈良湖が7世紀頃まであったという説は、どうやら間違いのようです。
超重大発表。
女王卑弥呼の苗字判明。斎藤卑弥呼。
斎藤氏は卑弥呼の女系子孫。神道の「結びの神」の一族。
斎藤卑弥呼は日本古神道の開祖。中国国家機密「天」の技術を授かり、
それを日本の八百万の神の柱に「神通力」として伝えた。
八百万の神の柱はヒトの交配実験をして血筋を継いでいる。
女王斎藤卑弥呼の女系子孫、斎藤氏は「結びの神」であり、
「結び」は結婚とともに、「輪」を作るひもを縛る技術を意味する。
「輪」は「和」であり、平和を意味し、聖徳太子の十七条の憲法「和を以て尊しとなす」の隠し暗号である。
このことばは日本人の日本人による生殖を示す。
>>101 >コテ+トリと、コテの九州王、伊都国女王、卑弥呼、名無しを使い分け、自説を関連スレで書き込みまくる
すべて別人なのに、アンチ畿内説がそんなにいるはずがないという思い込みから同一人物だと誤解。
実際には畿内説は孤立無援で滅亡寸前。
性懲りもなくザラコク一人のためにを幾度も立てる変態がいる
不快感を与えるようなスレ 二人でメール交換しろ
性懲りもなくザラコク一人のためにスレを幾度も立てる変態がいる
>>749 大和説は、結局、
「南」などの都合の悪い史料事実を否定曲解して、
都合がよいデータだけ切り取って、それを曲解断定して、
いろんな分野のトンデモ情報をかき集めて出来ている、
人種差別的国粋皇国史観の戦争狂の・・・・詐欺師グループなんだなあ。
>>759 >戦争中は敵国を蔑称で呼んで普通じゃないか<
殺し合い戦争そのものが、
「諸国民との協調」や「平和共存」を規定した憲法に対する違反であり、
「蔑称で呼ぶ」事が犯罪者的。
>>762 >水銀朱以外を丹と呼んだ例は?<
魏志だけでも、「丹木」や「鉛丹」が書かれており、
おそらく「ベンガラ」も丹であった。
>>766 >九州と言えば日本の史書では北部九州を決して身内としては扱ってないな
降伏して来た地方豪族か、まさに伊都国の人間なんか外来扱いさえしてるな
皇室が身近に扱ってるのは東南部 宮崎や隼人などの人々
畿内、吉備の勢力が瀬戸内海を通じて九州に進出する際に
橋頭堡になった地域を重視してるのが見えるな <
記紀は、筑紫倭国の存在や歴史を抹殺し、盗用造作した半分×書。
>>113 まいにち罵倒や侮蔑の言葉ばっかり並べてるザラコクって
憲法違反の犯罪者的老人なんだね
>>769 >九州は那珂八幡のように纏向型のかなり早い段階で前方後円墳を作成するような状況にあるのに、<
いや、前方後円墳は、那珂八幡などの筑紫が先行。
>邪馬台国の中心地である纏向からその土器を見いだせない<
邪馬台国なんて存在しないし、
大和は、倭国の別種の旧小国であり、倭国の「東征毛人55国」の中の一国。
>邪馬台国連合の共同の祭祀の場である纏向に<
邪馬台国連合なんて存在しない。「南≠東」に拠って、纏向も×。
>参加できないと言うことからして、
九州は倭人伝にあるように隷属的な地位に置かれていたと考えた方が良いだろう<
筑紫倭国が田舎の旧小国の祭祀に参加する必要がない。
>初期古墳も畿内の人間の出先機関、一大卒などと関わるものであると考えると辻褄があう<
畿内なんて存在していなかったし、大和は、「東征毛人55国」の一国。
>那珂八幡の第二主体の1枚のみの三角縁副葬品などを見てもここの被葬者が決して地位が高くないことが分かる<
三角縁神獣鏡も、筑紫が先行。
>>770 >九州説のアホはともかくとして初期の邪馬台国における九州の扱いは中々難しいところがあるな
最初期からの参加が見えるのに、纏向に来てない
支配や征服と言うほどの状況も見えないが、九州自身の自立性は薄いと
どう判断していいのか意外と難しい <
思想宗教にクルった大和説には難しいかも知れんが、
普通の国民には簡単。
倭国は「南≠東」などに拠って筑紫にあったのであり、
大和は、倭国の別種の旧小国であったのであり、
倭国の「東征毛人55国」の中の1国。
>>772
>すこしも難しいことではないんですよ。 阿波から、纏向や九州への展開とすれば、簡単に説明が附く話です。
もういい加減に現実に目を向ける時が来ていますよ。
考古学は着々と真実を示し始めています。 @阿波<
阿波も、以前は出雲系であったが、
筑紫倭国の「東征毛人55国」に拠って、筑紫倭国の支配下になった。 >>773 >前方後円墳の枠組みにどの地域よりも早く参加してるのに<
逆。
前方後円墳も那珂八幡などが先行しており、纏向は那珂八幡の模倣進化拡大。
>纏向祭祀にいないっていうギャップが解釈を難しくしてるんだよな
半分自立的な自由が認められてるのか、ハブられてると考えるか、
纏向の祭祀への参加は絶対条件ではないのか <
筑紫は、「東征毛人55国」の中の1国の祭祀に、一々参加しない。
>>121 いくら妄言を連呼しても
那珂八幡が北部九州に進出した畿内系の古墳な事実は
覆せないから
>>755 >【静かな拡散】 弥生中期から後期まで続いた瀬戸内海を舞台にした長く激しい争い。
それとは対照的に弥生終末期の畿内系土器の急速な、しかし静かな拡散。
この2つの間に西日本で何が起きたのだろうか。<
倭国の「自昔…東征毛人五十五國」があったの。
>平和的に畿内系の土器が拡散したのは、そのとき既に西日本全体がある統制の下に
置かれていたからだろう。<
近畿の土器は、筑紫への搬入上納時の生活用品として使われ、
近畿人は、筑紫でそれを売って生き延びたの。
>統制の開始は、瀬戸内以西に限って言えば、弥生中期にさかのぼる可能性もある。
そのころ早くも九州では、瀬戸内から多くの土器の移動現象が確認できるのだ。
畿内系土器の拡散は、この現象の延長線上にあると思われる。<
それが「自昔・・・東征毛人55国」の結果。
>>775【市(いち)】
>なぜ畿内の土器だったのか。<
筑紫の東征将軍の支配下になったから。
>それは要衝ゆえ、その地に畿内と周辺地域を後背地とする市(いち)が立ったためだろう。
つまり、弥生中期の瀬戸内海の侵略戦争が発端となり、やがて弥生終末期の畿内で、
モノや人の取引をする大規模な市場が出来上がったのだ。人の取引、要は奴隷売買である。
考古学的に見える畿内系土器の拡散は、畿内を供給地とする奴隷の広域取引の痕跡であったと思われる。<
食えない人々は、筑紫倭国への上納出稼ぎに生活用品を拐帯していったの。
>そうして、多くの畿内出身の労働者が、列島の広い地域で各地の生産活動の一翼を担うようになった。
これが列島にとって効果的な労働力供給手段となった。
それに伴い、吉備・山陰の大型墳丘墓から少し遅れて、九州を含めた全国の広い地域で、
ほぼ同時に多くの古墳築造が可能となった。<
高冢古墳は、筑紫の祇園山が先行。
>その意味において、古墳時代が畿内から始まるというのは、あながち間違いではないのかもしれない。<
間違い。筑紫が先行。
>ただ、この畿内の奴隷売買は外部勢力による搾取・略奪という性格のものではない。
畿内のそれが、先駆の瀬戸内のものと決定的に違った点は、畿内の現地勢力自身が、
取引の主導的立場を担ったことだろう。全国的な土器の拡散はそのためと思われる。
ただし、いずれも後背地の人的資源の急激な枯渇により、取引自体はそう長くは続かなかっただろうと考えられる。
おそらく、これが纏向の隆盛と衰退の原因だろう。
ともあれ、畿内は奴隷取引により多くの財を得て、列島内での存在感を高めていくこととなる。<
大和は、白村江の後まで、筑紫倭国の別種の旧小国であった。
>>778 >畿内スレは位置論争とかバカ話する場所じゃなくて
畿内の邪馬台国成立や在り方を考える場所<
「畿内」も「邪馬台国」も存在しなかった。
ここはザラコクのためにあるスレということを よく理解するように
>>779 >それは、最初期からの参加が見えたというのに、一種の錯覚があるからでしょう。
畿内地域からの移民が九州の奴国地域で有力者階級になった結果、
纏向で目だった活動をしているのは畿内系奴国人であり、
彼らが使用しているのが筑前型庄内甕であるため、
一見しただけでは北部九州人が纏向に来てないように見えるだけでしょう。<
筑紫倭国の「自昔」からの「東征毛人55国」があって、
倭国の将軍や大倭職が、大和に「市」を作って、筑紫に上納搬入させたの。
>>786 史料事実や学問や科学に、
「南→東」などの嘘吐き騙しや、非科学で対抗するのが大和説者ってことね 。
笑)
>>96 >伊都国あたりに「ヤマト」って読む地名ないだろ?
もともとは九州北部が倭、すなわちヤマトと呼ばれていた。
>>112
>「南」などの都合の悪い史料事実を否定曲解
いや、方角の間違いは大陸の史書の原典を挙げて、解釈とともに間違いを明確に示してあるだろ?
方角が間違っているとなると都合が悪いザラコクが認められないだけでさ
そして、まともな反論ができていないのがザラコクの方
距離が国と国の間だけで国内距離はないとか、位置説明と移動説明が違うとか
何の根拠もない脳内妄想だし、出発方向が書いてあるだけとか、頭が悪いにもほどがある
末慮国から伊都国は、どうやっても北東で90度回っている
現在の唐津港から海岸沿いに出発方向だから南東という主張は
1.移動は国の外れからというザラコクの主張と矛盾する
末慮国の中心は現在の唐津港より東側にあるので、
「ザラコクの主張が正しいとしても」出発位置にはならない
2.当時の末慮国の港は現唐津港の位置にはなく松浦川河口近くの潟湖
現唐津港付近には弥生時代の遺跡がない
松浦川河口の潟湖が港湾として優れているし、潟湖が港になっている例は多い
港を出発地とするという「ザラコクの主張が正しいとしても」そこから
海岸沿いに出発なら「東」方向で、魏志倭人伝の「東南」はそれでも間違いになる 隋書の対馬から壱岐~筑紫が「東」になっているのを、「經」都斯麻國だから対馬は通ってないとか言っているが、「經」は経由の経だからしっかり通ってるぞ
三國志の「經」の実例
三國志卷一/魏書一/武帝紀第一
引軍出盧龍塞、塞外道絕不通、乃塹山堙谷五百餘里、「經」白檀、歷平岡、涉鮮卑庭、東指柳城。
軍勢を率いて盧龍塞を出たが、塞外の道は断絶して不通であったため、山を壍って谷を堙ぐこと五百里余り、白檀を「経過」し、平岡を通過し、鮮卑の地を渉り、東へと柳城を目指した。
そして、旧唐書の大理-安南間は、前スレの950で詳解してある
この三ヶ所はどうやっても「大陸の史書の方位の間違い」なのは確定
「大陸の史書は方位を間違うはずがない」というのは、複数の反例によって否定される
従って論理学的に「偽」だ
ザラコクお得意の、論証抜きの「南≠東」には、何の意味もない
まあ、「儒教道徳者のザラコクさんの価値観」では認められないんだろうけど、
それは現実や真実とは何の関係もない
>>129 >もともとは九州北部が倭、すなわちヤマトと呼ばれていた。
倭をヤマトと読むのは「奈良盆地に本拠地を置く、現皇統につながる王権」の歴史書
である記紀において、であって、倭はヤマトの音訳ではない
逆に北部九州がヤマトと呼ばれていたなら、「倭」という字は使われない
本当に九州説は、行き当たりばっかりの思いつきだけで、論理の欠片もないな
>>803 >纏向の土器が 東海と吉備というのは、共立という文言からだと
持ち寄ったと想像されるかも知れんが
先住が東海系の部族で 吉備系の人員が纏向から東海銅鐸人を追い出した
ということにはならんのだろうか?
土器や銅鐸の編年とかよう知らんけど。<
根本的には、大和は、筑紫城の倭奴國の阿毎氏の東征で出来た、地方の市を監督する大倭職の国であり、
その後も、何度も「東征毛人55国」の東征があった、という事でしょうね。
>>808 はいはい、九州説は史料批判と史料事実や史料実態そのものだが、
大和説は、都合の悪い史料事実の否定曲解や、
大和に都合のよい文言のにピックアップだけなのだよなだけな。
w
>>812 >>発掘報告の、墳裾の62個の墓は、祇園山の墳頂の主体の埋葬の50年位後までの、集合墓であった、
という説明が×になったんだよ<
>そんなこと言ってるやつ、一人もいないだろww
甕棺墓と段築葺き石ありの古墳では、何百年単位で時間差があるぞ <
祇園山では、甕棺墓などの殉葬墓の直後に、段築葺き石の「高冢」が造られた事になるの。
>>816 >つか、須恵器でてるし 藁 <
吉武高木に「陶器」が出ているし、
筑紫の遺跡からも、「陶質土器」や「陶器」の出土が沢山あったし、
陶器窯も沢山見つかっている。
>>818 >残念ながら・・・ 金石文じや敵は日本だよ<
その墓内の碑文の時期は、
筑紫倭國も大和も「日本」を号していた時期であったんだよ。
>>824 >>「循海岸水行≒波打ち際的水行」などという水行を意図している、
という事が史料事実であり<
>本当にデタラメ爺だなぁ 循海岸というのは、大雑把な地図での循海岸だ<
いや、魏使らは、まだ地図など持っておらず、
全て、実際の移動見聞記録だ。
>そして、それが史料事実だったら、ザラコクの言う「韓は陸行」っていう
戯言が成り立つ余地を自分で否定してるってまだ気づかないかねぇ<
韓国に入ってからは、「歴韓國乍南乍東」の陸行だった、と書かれている。
ここはザラコクのためにあるスレということを よく理解するように
>>831 >寄港上陸していたら、隋使や隋書は「至」とはっきり書き分けてる、なんて
「史料事実」は いったいどこにあるの?<
明年、上遣文林郎裴清使於倭國。
度百濟、行至竹島、南望[身冉]羅國、經都斯麻國、迥在大海中。
又東至一支國、又至竹斯國、又東至秦王國、其人同於華夏、以爲夷州、疑不能明也。
又經十餘國、達於海岸。
>>839 >松浦郡の郡衙がどこかとか、考えたこともなかったんだな 嘲笑)<
松浦郡の郡衙がどこであったのか?、決して言えなかったんだな ?。
嘲笑)
>>840 この人種差別殺戮戦争狂の国粋皇国史観の・・・・に限らず、
大和説者って、
相手が理由や根拠を言ってある事を知らん振りして、
「根拠は?」と叫び続けて、
「俺様の結論」をワメくだけだよね 。
なんで?、自分の説を言わないのかな。
>>851 学会教育界学者 「新卒 俺を裏切るなよ」
新卒 「はい、南→東先生 どこまでもついていきます」
>>853 安部夫婦や地獄の鬼 「こりゃや財務省、捏造しやがって 舌を抜いてやる」
財務省 「あううう、お許しくだせえっ 安部さんを裏切るなんてできなかったんです ぐあああああああ」
>>854 安部文部省や学会教育界や地獄の鬼 「どうだ、この捏造野郎!」
新米考古学者 「うげええっ、おぎゃぎゃぎゃぎゃぎゃああああ」
弥生時代研究の第一人者 金関恕さん90歳死去
https://mainichi.jp/articles/20180315/k00/00e/040/285000c 弥生時代研究の第一人者、金関恕(かなせき・ひろし)さんが13日、
心不全のため死去した。90歳。
>>138 >韓国に入ってからは、「歴韓國乍南乍東」の陸行だった、と書かれている。
トンデモ古田本にか?
w
>>135 >造られた事になるの。
ザラコクの頭の中ではそうなんだろうなww
現実や真実とは何のかかわりもないけれど
>>858 >畿内説は実は東遷説だな。<
「畿内」なんて存在していなかった。
>【畿内説の主張のまとめ】 (奥山氏
>>1の発言をまとめたもの)
「伊都国の太陽祭祀を継いだ卑弥呼が、瀬戸内海勢力の実力を背景として、総花的に纏向で共立された」<
「南≠東」で×。
大和は、筑紫城の倭奴國の阿毎氏から別れた別種の旧小国で、
「自昔・・・東征毛人五十五國」の中の一国。
>「首長のいない広域政治集団が発生したが、圧力が高まって、急激な首長権が確立した」<
東征毛人55国が継続し、東征将軍や大倭職の支配下になった。
>「弥生中~後期に隆盛を誇った伊都国は、蝋燭の最後の輝きをはなって音もなく衰退した」<
阿毎氏の壹與の後も、阿毎氏系倭王が続き、
(317年頃に姫氏に王位が移って久留米~八女に遷宮した後も)
伊都国王や一大率や平西将軍などとして栄え、
磐井が一旦政権を握ったのに挫折したが、
またタリシホコが天子を称して栄えた。
>>873 >飛騨辺りの勢力が出雲を作り、大和朝廷を作ったとあるしな。<
大和に「朝廷」などなかったから、×。
超重大発表。
女王卑弥呼の苗字判明。斎藤卑弥呼。
斎藤氏は卑弥呼の女系子孫。神道の「結びの神」の一族。
斎藤卑弥呼は日本古神道の開祖。中国国家機密「天」の技術を授かり、
それを日本の八百万の神の柱に「間術」として伝えた。
八百万の神の柱はヒトの交配実験をして血筋を継いでいる。
女王斎藤卑弥呼の女系子孫、斎藤氏は「結びの神」であり、
「結び」は結婚とともに、「輪」を作るひもを縛る技術を意味する。
「輪」は「和」であり、平和を意味し、聖徳太子の十七条の憲法「和を以て尊しとなす」の隠し暗号である。
このことばは日本人の日本人による生殖を示す。
斎藤は、祭頭だ。まつりがしらが斎藤氏だ。
卑弥呼は日巫女。
斎藤卑弥呼は祭頭日巫女。
藤原氏の藤は、斎藤氏から一字もらったと考えるべき。
藤原氏より斎藤氏のが先。
「間術」とは、脳情報通信技術での間諜を含む偵察術、忍術であり、日本神道の生殖「さかき」を表す「間」でもある。
>>879 >その、東テイ人とやらが隼人と同一の存在であったというソースは?
文化的共通点があるの?風俗が同じとか???
否定しえない、じゃないんだよ。そうだという証拠を出せ。<」
勿論、上野原遺跡が中心。
「倭人在帶方東南大海之中」の「会稽東治之東」推定の北部九州に対比して、
会稽海外で20国も存在し得るのは、南九州しかないし、
東テイ人の住居説明も竪穴式住居に一致し、
琉球人や薩摩人や隼人も、北部九州以東の倭人に対して、全く違う容貌の人種に見えるから。
>>141 >松浦郡の郡衙がどこであったのか?、決して言えなかったんだな ?。
嘲笑)
質問もしていないことに
相手が答えないって嘲笑するって、頭おかしくない?
>>152 北部九州が「会稽東治之東」だなんて、九州説は方向オンチだね
そんなことじゃ、東だぁ~南だぁ~言ってて
邪馬台国を見つけるのは無理でしょ
>>884 >>1号墳<
>ザラコクは平原1号墓は、墳じゃなくて冢だって言ってなかったっけ?
自分に設定すら覚えていない、その場しのぎの言いっ放し<
また変な・・・・アホの大和説者が出て来たな?。
私が「高冢」だ、と言ったのは、祇園山だよ。
>>886 >>古墳が違えば<
>平原1号墓が古墳だというなら、その時点で卑弥呼の墓の確率は0だな
そういうのは一切理解してないんだよな、ザラコクは <
また、大和説の・・・・アホ登場。
私は、卑弥呼の墓は、「高冢」の祇園山、説。
>>149 >「畿内」なんて存在していなかった。
当時まだ北京がなくても誰もが普通に「北京原人」と言うし、誰もそれを変だとは思わない
>>132 >倭をヤマトと読むのは「奈良盆地に本拠地を置く、現皇統につながる王権」の歴史書
皇国史観?
>逆に北部九州がヤマトと呼ばれていたなら、「倭」という字は使われない
根拠は?
>>921 >倭奴国(北九州一帯)は倭国の極南界である。
日本(南九州の天皇家、但し神武は中央=畿内生誕)は、<
神武の生誕地も生育も九州であり、九州から東征したんだから、×。
>古くは小国であったが、
その後倭国(大和・吉備・出雲・奴国など西日本)の地を併合した <
筑紫の倭國を併合吸収継承したのは、大和の日本国であるから、×。
>>159 >根拠は?
そもそもヤマトだったら、邪馬臺って書かれるだろ?
倭の上古音は「wai」に近い音だよ
そして、ここにいる九州説の言う伊都国奴国の領域に、ヤマトの地名はない
>>929 >エヴァンズらが一部のバルディビア土器片との文様の類似を
発表したのは阿高式土器なので<
成程。
>ズビニ鉤虫を九州人の移動根拠にするのであれば
ズビニ鉤虫がなぜか九州人にだけ寄生が始まり<
そりゃ、呉王夫差の後裔の火の国山門に渡来があったし、
「所有無與tan耳、朱崖同」や「倭地温暖、冬夏食生菜、皆徒跣」があったし、
南洋や琉球系と思われる上野原遺跡の東テイ人や、侏儒國人もいた。
>感染した九州人が短期間に直接各地で排便して土壌を汚染してまわり
他の民族よりも不衛生な食習慣により体内に成虫を寄生させ続け
さらに南米やヨーロッパまで移動していったということになる<
縄文土器が見つかっているのは、エクアドルと南洋の島だけなんだろ?。
>>163 エヴァンズ夫妻以外に、エクアドルで縄文土器が見つかっていると言ってる人は?
>>163 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と中粒種のイネは?
.
>>163 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したと言っているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>946 >邪馬台国はヤマト国、葛城山系以東の奈良盆地一帯です。邪馬台は単なる地名です。<
「邪馬台国」なんて、存在しません。
>ヤマトの地が卑弥呼を共立した勢力に征伐され、都が置かれました。<
「南≠東」に拠って×です。
大和は、倭国の別種の旧小国であったのであり、
倭国の「東征毛人55国」で征服された国の一つです。
神武系は近江王朝なんだよ
南九州は交流した地域
北九州の奴国が脅威だったため、日向王朝をつくった
>>950 >そして、安南は大理の「南東」だから「東」は間違い
通水陸行は、安南への行程にしかかからない <
「陽苴咩城は今の大理」が断定出来ない。
大理だとしても、そこからハノイは「東南」よりも少し北であり、
大理→昆明→南寧方面の水陸行は、更に「東」方向に近くなって、殆ど「東」。
つまり、「東至安南如至成都通水陸行」は、殆ど間違っておらず、
この男の「旧唐書が東南と東を間違った」説は、成り立たない。
>>953 >>不彌國で萬二千余里が殆ど終わってしまっているように書いている<
>これが既にごまかし 不彌国からまだ千三百里余っている
「島巡り仮説」など、大陸のどんな史書をひっくり返しても、
そんな書き方の例は一つもない「捏造」の読み方<
魏使らが(方四千余里の)對海國の国内移動を記録し、
(方三百里の)一大國の国内移動を記録し、
陳寿が、それを見て計算した、という事が史料事実であり、史料実態。
だから、それを算定しないこの男は、・・・・。
>大理から成都ほどの距離があっても2400里、千三百里はその半分より長い<
唐代の2400里は、当然「長里」。
魏志は、当然(長里の6分の1の)「短里」。
それを同じだとして比較したこの男は、やはり・・・・。
九州では収まらないよ
>>173 >魏使らが(方四千余里の)對海國の国内移動を記録し、
>(方三百里の)一大國の国内移動を記録し、
飼ってに「国内移動」って言い張ってるけど
なんの根拠もないよね
逆に、ほかの国で「国内移動」が無いなら
支離滅裂だよ
>>161 >これが妄想で、倭国の中の女王の都が置かれた場所の地名が
邪馬台国=ヤマト国で、<
これが妄想で、邪馬台国というものは存在せず、
「南≠東」で「倭国の中の女王の都が置かれた場所」が「ヤマト」でもない。
>のちにこのヤマトが倭国全体を代表する地名になったため、<
ヤマトが倭国を併合吸収継承したのは、白村江の後の701年。
>訓では倭と書いて「ヤマト」と読むようになった、 というのが正しい順番<
「倭をヤマトと呼んだ」のは、記紀以後の大和の捏造。
>今の大和の字は、大倭から字を改めたもので、
ヤマト(もとの大和言葉、音のみで字はない)
↓ 邪馬台国(大陸王朝の音訳による当て字)<
「邪馬台国」なんてそんざいしないし、
「南≠東」であるから、×。
>↓ 倭国と書いてヤマト国と読む(邪馬台国で倭国を代表するようになる)
↓ 大倭国(ヤマト国)<
「大倭」は、倭国の地方の市を監督する役人名であったから、×。
>↓ 大和国(ヤマト国、文字を改める) の順番だよ <
異常、この男は、不正な記載ばかりであり、×人間。
>>962 >さらに、日本という国号を創始した後の日本書紀では、
「日本」と書いて「ヤマト」と読ませている<
もしそうであれば、また、書紀のインチキがバレた事になる。
>邪馬台国(ヤマト国)以来、漢字表記は変わっても、ずっとヤマトなんだよ<
「邪馬台国」なんて存在しないから、×。
存在する事を挙げれば、「山or邪馬」の「門or戸」。
>>964 大和皇国史観の安部政府や右翼マスコミや右翼学会教育界の「南→東」などの嘘吐き騙しの、
大和説なんて信じてるから、心を病むんだよ。
>>969 >別に縄文人じゃなくてもそれ以外にも、ズビニ鉤虫を媒介できる民族がたくさんいるんだよ?
この状態で、どうしてズビニ鉤虫が縄文人の移動の証拠になるんだい?
ズビニ鉤虫がいるところが縄文人の移動の証拠なら、
縄文人はアフリカ、アジア、アメリカの熱帯地域
及び中東、北アフリカ、南欧にも進出していた、ことになるよな? <
違うね。
縄文土器は(旧大陸では)列島にしか見つからず、
それが新大陸の南米のエクアドルで見つかったのをどう説明するのか?という事で、
縄文人が縄文土器を携え太平洋を渡ったのか?、
シベリア~アラスカ経由で行ったのか?、という問題になっていたの。
>>971 >じゃあ、当然になんたら土器も、作ったホモ・サピエンスが縄文人って決めつける必要ないし
決め付けられないよなww
エクアドルに縄文土器があるっていうのは、そういうことを言った「人がいる」だけだよ <
縄文土器が存在したのは、列島と、南洋の島と、エクアドだけなんだよ。
>>986 大和説者の嘘吐き騙しが、全て、
主語などを入れ替えるだけで、簡単に否定反論されてしまう、という事が、
大和説の終わりを告げているな 。
>>988 >>50里以下の場所は里数を記載していない<
>例えば高句麗は都の丸都が方可二千里、戶三萬と書いてある
二万余戸の奴国の国内移動が50里以下なんてことにはなるまい?<
まず、丸都が「方可二千里、戶三萬」とは書いていない。
当然「高句麗」の説明。
また「奴國」が側副傍線行程国説明であり、魏使らは通っておらず、
「国内移動」をしていない。
>>181 そんな、安直なオウム返しで「否定反論」できるわけないでしょ
>>990 >旧唐書の大理ー安南間の、全解釈を
>>950に書いておいたよ<
大理であったとしても、
「通水陸行」ルートになる大理→昆明→南寧方向は、殆ど東行きであり、
「東安南」の「東」は殆ど間違っていなかったんだよ。
>大陸の史書は、方角を間違うときは間違う
「間違うはずがない」というのは論理学的に「偽」なんだよ<
これ「偽」ね。
大陸の史書も、方角を殆ど間違っておらず、
この・・・・男は、やっぱり「偽」だったんだな。
>>182 側副傍線行程国説明とか
ただ言い張るだけで
なんの根拠もないだろうに
>>991 >>居住外縁部間の距離、というのが人類の常識<
>その常識と「島巡り仮説」はどういう関係になるんだ?<
渡海の千余里は、出発港~到着港間の概数の里数。
その国の到着港~出発港の間が、それぞれの国内の見聞移動の概数里数。
矛盾しているのは理解できるか?<
>>186 ザラコクが自己矛盾しないことは、滅多にない
>>995 >白村江で唐と戦ったのは、(大和日本国ではなく)筑紫の倭国 <
>白村江どころか、倭の五王の遣使も
現在の奈良盆地と呼ばれる場所に存在した、稲荷山古墳から江田船山古墳に至る
範囲を勢力圏に収めた現皇統につながるオオハツセワカタケルの遣使だよ <
これ×ね。
大和日本国が、盟主になったのは、白村江の後の701年から。
また、倭の五王と大和の王らは、名前も年代も事績なども全く一致しない。
稲荷山古墳から江田船山古墳も、大和王らとは全く関係がない人物の話。
本当に、歴史を科学として論じることのできない、
大和説の、人種差別の殺戮戦争狂の国粋皇国史観右翼主義者は、
安部自民文部省や右翼マスコミや学会教育界と同じで、
価値観が違うわ。
>>188 このように
ザラコクは言い張るだけ
理由は言わない
変に政治思想に凝り固まった人間が歴史に口を出すと、ろくなことがない
独善的で、攻撃的で、ひとの話を聞かない
>>62 >邪馬台国はヤマト国、葛城山系以東の奈良盆地一帯です。邪馬台は単なる地名です。<
「邪馬台国」なんて存在しませんから、この男は、嘘つき騙しです。
>ヤマトの地が卑弥呼を共立した勢力に征伐され、都が置かれました。纒向の外来系土器、円形周溝墓などがその証です。殉葬などそれ以前になかった風習が持ち込まれたことも、新しい別の勢力がヤマトの地を支配した傍証になります。<
大和は、筑紫倭國の東征毛人55国の一つであり、都ではありませんから、
この男は、嘘つき騙しです。
>女王国、大和朝廷を作ったのは、<
大和は、女王國ではないし、朝廷などでは当然ありませんでしたから、
この男は、嘘つき騙しです。
>出雲など山陰の勢力、尾張三河など東海の勢力、阿波、宮崎や遠賀川の石神など、縄文系勢力と縄文系勢力に半分乗っ取られた古い海神。
畿内や九州北部の渡来人系勢力はこれらの勢力に征伐されました。<
逆です。九州北部の勢力が「東征毛人55国」をしたのですから、この男は嘘つき騙しです。
>魏志倭人伝当時、狗奴国の版図であったなにわの地は陥落しています。
魏志倭人伝当時の狗奴国は邪馬台国ヤマト国の南。和泉と河内です。<
狗奴國は北部九州の女王國の南ですから、これも×であり、
この男は、嘘つき騙しです。
>>184 もう一つ、大陸史書の方角の間違いの例を挙げてあげよう
新唐書 卷二百二十 列傳第一百四十五 東夷 日本
其「東」海嶼中 又有邪古波邪多尼三小王
この邪古が屋久島で、多尼が種子島だというのが定説
「その」っていうのが日本を指すのだから、
「東」は「南」の間違いだよな?
旧唐書で対馬からの「南」を「東」としたり、大陸史書の倭国(日本)に
関する記述では「南」と「東」の取り違えがちょろちょろ混じっている
その原因は、
魏志倭人伝で、九州に上陸してからの方角が90度狂っていたことが原因なのが一つと、
大陸の人が倭国に対して特に関心がないため、「東南」大海之中なら
「東」でも「南」でもどうでもいいと思っていた節があることが一つの
二つくらいが考えられる
>>76 >>「主行程」記載は、不彌國から「南至邪馬壹國、女王之所都」
>これ、ザラコクが 自分で書いた文だぞww<
不彌國まで来た主行程は、不彌國の次が「南至邪馬壹國、女王之所都」になっている、
という意味。
>自分で『「主行程」記載は、不彌國から』と書いておいて
『「從郡至倭~女王之所都」の日数説明の文だ』とかよく書けるよな<
この男の曲解捏造の騙し。
当然 、
「主行程」記載の、不彌國からの続きが「南至邪馬壹國、女王之所都」だ、
という意味。
>>82 >畿内説は実は東遷説だな。 【畿内説の主張のまとめ】 (奥山氏
>>1の発言をまとめたもの)
「伊都国の太陽祭祀を継いだ卑弥呼が、瀬戸内海勢力の実力を背景として、総花的に纏向で共立された」
「首長のいない広域政治集団が発生したが、圧力が高まって、急激な首長権が確立した」
「弥生中~後期に隆盛を誇った伊都国は、蝋燭の最後の輝きをはなって音もなく衰退した」<
これは、反論済みですね。
>>171 >「陽苴咩城は今の大理」が断定出来ない。
「陽苴咩城」でググってみなよ
ウィキペディアの中国語のページが最初に出てきて
「羊苴咩城,又称“阳苴口芊城”、“阳苴咩城”、“苴咩城”,
位于今天的『云南省大理白族自治州大理市』」って書いてあるだろ?
これは、新唐書のあとの史書にも出てくるから、比定地ではなく確実に「大理」だよ
ザラコクは、ここからなっていない
>大理だとしても、そこからハノイは「東南」よりも少し北であり、
>大理→昆明→南寧方面の水陸行は、更に「東」方向に近くなって、殆ど「東」。
グーグルマップで測った大理ー安南間の角度 方角 : 131.001°
135度が南東だから、4度しかずれてないよな?
これが、「ほとんど東」だったら、南東という方角はないわ
>つまり、「東至安南如至成都通水陸行」は、殆ど間違っておらず、
何度「地図を見ろ」といっても見ないで適当なことを書いてるやつに議論に参加する資格はないんだよ
こっちは実際の角度の実測地を「根拠」として出してるんだから、地図で確認できるだろ?
>この男の「旧唐書が東南と東を間違った」説は、成り立たない。
残念でした
完璧に「旧唐書が東南と東を間違っている」ことが論証できているだろ
陽苴咩城は大理で確定
大理から安南への方角は真北から時計回りに131度の南東
間違いを認めて、今後「論証抜きの南≠東」を書くなよ
私が男だとどこに書いてある?
エクアドルのバルディビア土器片と阿高式土器の文様が似ているのを
約3500年前の南米インディオのミイラからズビニ鉤虫の卵が検出されたから
縄文土器ではないかという話が
南米で縄文土器が出たから縄文人がズビニ鉤虫を海洋ルートで持ち込んだという話に
変わってしまっている
>>177 >もしそうであれば、また、書紀のインチキがバレた事になる。
「もしそうであれば」だと?
この程度の常識すらなくて、古代史の議論に参加するなよ
無能丸出し
日本書紀巻第一 神代上
廼生大日本 「日本、此云耶麻騰。下皆效此」
「日本」の初出のところの読み方の註がついていて
「日本、これを耶麻騰(ヤマト)と云う。以下みなこれにならう」
そして、ここの大日本がオオヤマト=大倭=大和な訳だ
少しは調べて「典拠」を示すってことを覚えなよ
日本人ならな
日本人じゃないなら、できなくてもしょうがないがな
特に日本国籍を持たない儒教道徳者なら、日本語を使っていたとしても
日本人とは価値観を共有していないから、できなくてもしょうがない
さあ、ザラコクはどうする?
>>179 >新大陸の南米のエクアドルで見つかったのをどう説明するのか?
それ、縄文土器じゃないんだよ
バルディビア土器って書いてあるだろ
文様が「似てる」と感じた人がいるだけ
>>85 >>「大和が筑紫倭國から別れた別種の旧小国」
という史料事実や史料実態を隠蔽したウソ論理であったから<
>そんな史料事実は無くて捏造だから、×。<
旧唐書:
倭國・・・者、古倭奴國也。・・・
日本國者、倭國之別種也。・・・或曰、倭國自悪其名不雅、改爲日本。
或云日本舊小國、併倭國之地。
新唐書:
日本、古倭奴也。・・・其王姓阿毎氏、 自言初主號天御中主、至彦瀲、凡三十二世、皆以尊爲號、居筑紫城。
彦瀲子神武立、更以天皇爲號、徙治大和州。・・・
次用明、亦曰目多利思比孤、直隋開皇末、始與中國通。
>>87 >>成都の西南2400里の地であれば、そこから安南は東~東南東であり、<
>現実の地理はまったく無視か・・・。<
お前の言う大理からでも、
大理→昆陽→南寧が、東~東南東の通水陸行路になる。
さすが嘘つき騙しの大和説 。
>>184 >大理であったとしても、
大理であることは195で確認済み
>「通水陸行」ルートになる大理→昆明→南寧方向は、殆ど東行きであり、
>「東安南」の「東」は殆ど間違っていなかったんだよ。
これも同じくグーグルマップで測ると
方角 : 117.181°
八方位の場合、「東」となるのは90±22.5度の範囲(67.5~112.5)だから
117度は東の範囲に入らず、南東だな
どうやっても間違ってるんだよ
そして、如至成都は距離
通水陸行 はソンホン側沿いの経路
大陸史書の地理・旅程記事は、基本的に直線方向・距離で示されている
で、間違うときは間違うんだよ
間違いを認められない、儒教道徳者は大変だねww
「方位が間違うはずがない」は「偽」が確定
二度と「論証なしの『南≠東』」を書くなよww
>>88 >この時代の情勢を抜きにしては正しいことは分かる筈がない。
まず、方形周溝墓を墓制とし、絵画土器を威信材する勢力が日本の広範囲を支配下に収めてた。
それが和国大乱によって分裂した。 以下は勝手に考えてみてくれ<
「和国大乱」なんて存在しない。
あったのは、倭國の「東征毛人五十五國」だ。」
>>186 >渡海の千余里は、出発港~到着港間の概数の里数。
>その国の到着港~出発港の間が、それぞれの国内の見聞移動の概数里数
国内移動は記載されないって書いてたのはザラコクだよな?
そして、「その国の到着港~出発港の間」は、陸行なのか水行なのか、どっちだ?
「見聞移動の概数里数」これ、初見なんですが?ww
また新概念を「思いついた」のか?
「島巡りが記載されている、大陸史書の別の例を一つでも挙げて見せてくれ」って
いうのは、どうなった?
一つも見つけられないのか?ww
「出発港~到着港間の概数の里数」と「国内の見聞移動の概数里数」は
足すのか足さないのかどっちだ?ww
もう、バカすぎww
>>203
>「和国大乱」なんて存在しない。
あったのは、倭國の「東征毛人五十五國」だ。」
東征毛人五十五國 =近畿以東(北関東含む)
西服衆夷六十六國 =西瀬戸内・九州
渡平海北九十五國 =東瀬戸内・山陰・北陸
これ全部、倭国(阿波)から進出した忌部一族の開拓地域なんですよ。 @阿波 >>94 >>「至」と書いていないのに?。<
>至るって書いてなくても経るって書いてあるだろ?<
「至」なら、到着をはっきり示すが、
「經」では、「通り過ぎました」という意味が強く、
「到着上陸」の意味が非常に少ない、というのは、常識だろ?。
>>207
>阿波にはそんなに人はいない
「そんなに」ってなんのこと? @阿波 >>95 >単純に対句になってるのが分かるだろ?
そして、「到」と「至」に意味の差はない<
いや、同じような意味であっても、
「到」は「至って立つ」という文字だから、
「(立派に)目的地に立った」という意味が強いが、
「至」は、普通に「目的地に着いた」というような意味で、
少し、使い分けがある。
>傍線行路だの主線行路だのの区別はないんだよ<
アホは、筆者が表現を「書き分けた意図」が判らないから、読めない人種。
>>201 >大理→昆陽→南寧が、東~東南東の通水陸行路になる。
地図を見ろって!
それに、ザラコクのいう「出発方向」で見たら、
大理から出て行く道はさらに南になるぞ
方角 : 151.713°
南東の135度から、さらに16度、南よりになる
ますます「東」じゃないだろ!
適当なこと書いてないで、グーグルマップで測ってごらん!
一発で「ザラコクが間違っている」ことが自分でも分かるから!
>>198 >日本書紀巻第一 神代上
>「日本」の初出のところの読み方の註がついていて
>「日本、これを耶麻騰(ヤマト)と云う。以下みなこれにならう」
少し前に書かれた古事記だと、ほぼ同じ文面で、倭と書いてヤマトと読むと書いてある。
そして、大陸の史書では倭は九州北部のこと。
記紀の神代は九州倭国の時代のこと。
【倭国】
紀元前に博多湾沿岸に倭国が成立して漢と国交を持ち、後漢の頃には漢委奴国王印により倭国王に冊封された。後漢書では、倭国は朝鮮半島南岸から九州北岸までの、対馬海峡の海洋国家として書かれている。
対馬海峡における貿易の権益が、天津神すなわち海の神を中心とした倭国の形成の原動力であったと考えることができる。
記紀の国生みは博多湾から始まる。伊奘諾が最初に手に入れた領土である淤能碁呂島は博多湾の小島である能古島のことである。
それに続きイザナギとイザナミの生んだ国(領土)のうち、天の冠詞がつく島である隠伎之三子島(天之忍許呂別)、伊伎島(天比登都柱)、津島(天之狭手依比売)、
女島(天一根、姫島)、知訶島(天之忍男、五島列島)、両児島(天両屋、男女群島)が天つ国の本来の領域である。
国産みにおける島々は九州北部沿岸の島を意味していたが、後に西日本全体の地名に拡大され再配置される。
博多湾岸を起点として対馬海峡から朝鮮半島南岸へ、日本海から山陰や北陸に広がる国が古代の倭国の姿である。
連合国家である倭国の盟主は筑紫であり、他に九州北部の倭国連合を構成する豊国、肥国がある。倭地とされた本州には出雲、越などがあった。
また、中国との交易は一貫して筑紫が独占していた。
筑紫の特に玄界灘周辺の勢力は、対馬海峡の権益を独占して力をつけ、海人の国、天津国と呼ばれ、その王族は天津神として九州や本州の王族である国津神と区別された。
九州で出土した副葬品の分布地図
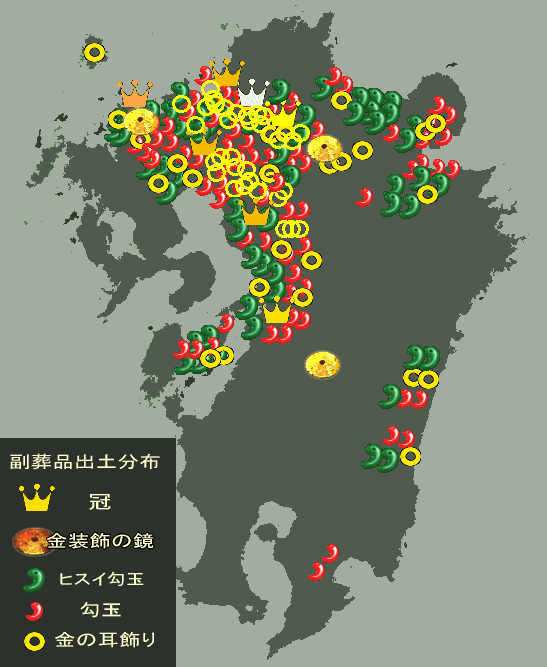
狗奴国(熊本)も元は卑弥呼と近い立場の同じ文化圏であり、卑弥呼共立をめぐって反対していただけである。
上記の地図は邪馬台国と狗奴国(熊本)を合わせた九州北部の国、倭国の中枢を示している。
実際にはこれに属州としての日本海沿岸、瀬戸内海沿岸の地域が付随する。
卑弥呼の時代の畿内は、奈良も京都も大阪もまだ沼地であり、特に奈良は主要交易路からはずれた名もなき辺境の沼地であった。
2世紀の倭国大乱後の女王の墓として3世紀に平原遺跡が作られた。
副葬された王位の証である八咫の鏡は、筑紫伊都国が王権の所在地すなわち倭国の王都であったことを示している。
>>209 >「到」は「至って立つ」という文字だから、
>「(立派に)目的地に立った」という意味が強いが、
>「至」は、普通に「目的地に着いた」というような意味で、
>少し、使い分けがある。
もとの
>>95で上げた
還「到」龍亢、士卒多叛。
「至」銍建平、復收兵得千餘人。
どちらも「目的地に着いた」という意味しかないぞ
「到」に「(立派に)目的地に立った」という意味があるなら、
「士卒多叛」(士卒の多く叛く)になった土地には使えないだろうに
使い分けなんてないんだよ
だから
>筆者が表現を「書き分けた意図」
これは、単なる九州説の「妄想」
そんな意図はない!
魏志倭人伝の邪馬台国までの里程
帯方郡(朝鮮北部)から狗邪韓国まで七千里、女王国まで一万二千里。
対馬海峡が三千里であり、帯方郡から九州上陸までで一万里となるので、邪馬台国の位置は九州北部になる。
魏志倭人伝の邪馬台国までの日程
帯方郡から邪馬台国まで水行10日、陸行1月(1日の誤りか)
ちなみに帯方郡から投馬国(宮崎都万)まで水行20日
後漢書における里程
大倭王は邪馬台国にいる。
楽浪郡の国境は、その国(邪馬台国)から一万二千里である。
倭国の西北界である狗邪韓國からは七千里である。
倭奴国は倭国の極南界である。
魏略逸文における里程
帯方(郡)より女(王)国に至る万二千余里。
邪馬台国時代の遺物の出土状況

>>209 単なる自分の独断を根拠もなく史料事実だと言い張る困った爺さんだな
>>206 >「至」なら、到着をはっきり示すが、
>「經」では、「通り過ぎました」という意味が強く、
>「到着上陸」の意味が非常に少ない、というのは、常識だろ?。
今、何を論じているか、分かってないだろ
別に「通り過ぎた」であっても、対馬を通り過ぎていれば
「經都斯麻國迥在大海中 又「東」至一支國又至竹斯國」
の「東」は「対馬から壱岐の方角」だろ
そして、現実に壱岐は対馬の「南」にあるのだから、「南」と「東」の
取り違えの確実な例になる訳だ
で、ザラコク理論だとこれは、位置説明なのかい?
それとも、移動説明?
考えたこともないだろ?
そんなものは、どこにもないからなww
>>214 そんなものが邪馬台国時代の遺物だと
認めてくれる学者は
いないよ
>>211 >ほぼ同じ文面で、倭と書いてヤマトと読むと書いてある。
「典拠」を示しなさい
>>96 >>邪靡堆<
>これ、なんて読む気だ?<
隋使の記録した文字を、魏徴らが隋書に書いた文字なのであり、
固有名詞であるから、勝手に書き換えず、そのまま読んで使っておくべき。
>これ、通な文字化け(?)で、邪摩堆のまちがいというのが通説 <
いや、判らんのなら、そのまま受け止めておくべき。
>これもヤマトって読むんだよ<
ほら、一度なん「勝手な読みを許可」したら、
こんな風に「こりゃ何でも有りなんだ」とばかりに、
全く有り得ない自分勝手な読みを造作する・・・・が発生するもの。
>伊都国あたりに「ヤマト」って読む地名ないだろ? もちろん、太宰府付近にもないぞ<
隋使が来た頃のタリシホコの都は、久留米であり、おそらく「古宮」遺跡だ。
>普通に伊都国=邪馬壹国なんてないからww<
ほら、この・・・・男は、一度史料事実の否定をしたら、何でもありになって、
嘘八百の言いっぱなしだ。
>>108 >このことばは日本人の日本人による生殖を示す。<
この男も、最後に突然変な事をしゃべった。
日本列島は、縄文の頃から、南洋や大陸からの流民が混合共存して来た、
という事を忘れて、
排他的(殺戮戦争的?)人種差別主義の宣伝をしている・・・・。
>>212もそうだが、九州説は遺跡や遺物の年代をメチャクチャに歪曲するなあ
>>211 >少し前に書かれた古事記だと、ほぼ同じ文面で、倭と書いてヤマトと読むと書いてある。
本当に適当なことを書いてるな
古事記では「倭」と書いて「ヤマト」と読むことは、「当然のこと」扱いで
一切注釈はないんだよ
読みを記すときは古事記でも
「訓常云登許(『常』のよみ(訓)は、とこ(登許)と云う)」という註が付くが
「倭」は初見の「神倭天皇」から、何の注記もない
確かめたかったら「古事記(原文)の全文検索」で「訓」で全文検索をかければいい
http://www.seisaku.bz/search4/searchk.php >>211みたいな嘘の書き込みではごまかせないよ
残念でした
>>219 >隋使の記録した文字を、魏徴らが隋書に書いた文字なのであり、
いやいや、版本の「邪摩堆」の「摩」の字の下の「手」の部分の縦線が
刷りの調子で二本に分かれてたんだよ
そうすると「手」が「非」に、「摩」が「靡」に化けるだろ
「隋使の記録した文字」じゃなくて、伝書の途中で化けたんだよ
>>219 >いや、判らんのなら、
いや、簡単に判読できるだろうが
この嘘の邪馬台国スレッドにも、謎の優れた考古学者達が現れて、邪馬台国纏向説を、蠅を叩き潰すようにして、叩き潰してしまったようだね。。。
せっかくだから、初心者にも説明すれば、良いのではないのかな。。。
http://2chb.net/r/history/1521001812/ >>122 いくら妄言を連呼しても、
大和は、筑紫倭國の「東征毛人五十五國」の一つであり、
筑紫倭國の文化を模倣継承するしかなかったのであり、
那珂八幡が同族の大和に模倣された、という事実は、
覆せないから。
>>219 >こんな風に「こりゃ何でも有りなんだ」とばかりに、
いや、「邪摩堆」は普通にヤマトって読めるだろ
「邪摩堆」はヤマイとは読めないけれど
こういうところからも、魏志倭人伝の現存本の
邪馬「壹」國は邪馬「臺」國の誤りだって判断できるんだよ
>>219 >隋使が来た頃のタリシホコの都は、久留米であり、おそらく「古宮」遺跡だ。
それのどこが、「ヤマトと読む地名」だ?
久留米は山門から遠いぞww
>>227 >さいきん岡上が本格的におかしい
せっかくのニセスレが、ずいぶん減ってきたからなのかもね
でも、また新しく迷惑スレを立ててるんだけどさ
>>226 とうとうザラコクも筑紫に畿内の同族が進出していたことを認めるようになったな
いい傾向だ
>>114 >魏志だけでも、「丹木」や「鉛丹」が書かれており、
「丹木」や「鉛丹」は「丹」ではないから、「丹木」とか「鉛丹」と書かれるんだよ
この場合の丹は、「赤い」という形容詞
>おそらく「ベンガラ」も丹であった。
ベンガラは「丹」ではないから、「丹土」って書かれるんだよ
意味は単なる「赤い土」
仙薬たる「丹=水銀朱」とはまったくの別物
こんがらがる スレだな
誰が誰にモノ言ってるのか
5ちゃんの典型的なスレだな
スレは進めど反感分子のほうが頭脳明せき
これまでに挙げた、大陸史書での方角の間違いは
1.末慮国から伊都国 北東なのに南東 魏志倭人伝
2.対馬から壱岐 南なのに東 隋書
3.大理から安南 南東なのに東 旧唐書
それぞれの原因を考えると
1.は後漢代の末慮国から筑紫平野に抜ける道の「古い記録が混入」した
2.は撰者の認識(裴世清の報告で魏志倭人伝の間違いが分かった)により
魏志倭人伝からの引用時に修正しすぎた
3.は想定される地図が間違っていた
と思って探してみたけれど、旧唐書の頃の古地図でうまく参照できるのが見つからないな
>>226
>大和は、筑紫倭國の「東征毛人五十五國」の一つであり、
じゃあさ、筑紫に倭国があったとして、
「西服衆夷六十六國」はどこに入るんだい?
筑紫の西側には、そんな土地はないぞww
これ一つで、倭王武が九州王朝の王ではないことが丸分かりww
>>233 >スレは進めど反感分子のほうが頭脳明せき
反感分子って、畿内説側かい?
それとも九州王朝説側かい?
後者だと思ってるなら、やばいよww
>>1=2314
ザラコクと>>1だけでは??
衝撃的な畿内説論者を待つ????無理無理」
ムリを承知なんだ こんなところに本物の畿内説論者来るはずもない
だからこのスレは畿内説だが
ここで 遊びましょう 遊びましょう 畿内説のスレとしてはお粗末
ニュー速においで 九州さん
>>239 ザラコクをニュー速で引き取ってくれたら、めちゃ感謝するよ
がんばって勧誘して
ザラコクも、新しい布教の地平が開けるから、ぜひ行っておいで
帰ってこなくていいし
日本国が、古代に「倭=ヤマト」と呼ばれたのは、倭国(イ国)が伊都国から始まったから始まったからです。伊都国は現在の九州北部の糸島市です。
日本最初の王国の倭国=イ国=伊都国の王城の伊都城は高祖山の山城でした。高祖=天照大御神です、そして高祖山は日本中に糸島半島の高祖山しかありません。
国王が居城する伊都城が、高祖山の山城としてあったことによって、その山城は「山都(ヤマト)」と呼ばれたのです。これがヤマトの語源・始まりです。
糸島市や福岡市西区には、「山門(やまと)」などの地名があって、高祖山を登っていけば伊都城に至ります。
>>199 「感じた」じゃねえよ。お前の勝手なフィーリングと同一視するな。
研究者の分類の結果だボケ
>>241 >福岡市西区には、「山門(やまと)」などの地名があって
どこにあるんだい?
正確な住所で教えてくれるかな?
>>246 >研究者の分類の結果
分類の結果が「バルディビア土器」だろ?ww
縄文土器じゃ「ない」
その辺が理解できてないやつが何を言うんだか
がらが悪いし
やまとは山外なのにね~
こんな単純なこと普通に認めたらいいのに。
やまと至上主義は害でしかない
伊都国っていうのは、イズコクもしくはイドゥコクって読むのが正しそう。
日向の伊東氏、伊豆、伊豆の伊東、渭津(徳島の旧名)とも関係が有りそうだし広域国家だったんじゃないかな。
日向の伊東氏の居城は飫肥城だったことからして、飯富氏や愛知の大府とも関係が深そう。
>>250 >やまとは山外なのに
そんな地名はないようだね
一番近いので「岡山県美作市山外野」
どうして、こういう嘘捏造を平気で書くかねぇ
>>253 おまえは話をすりかえるくそ。
奈良の地がやまとと呼ばれるようになった由来の話。
やまとの意味
>>255 根拠あろうがなかろうが、話をすりかえる意図は?
何か邪な考えがあるからだろう。
>>254は
>>246と同じ人?
>>256も同じ人だね!
>奈良の地がやまとと呼ばれるようになった由来の話。
>やまとの意味
固有名詞の意味って考えてもあまり意味ないよ
奴国の「奴」の意味ってなんだと思う?
で、バルディビア土器が縄文土器じゃないのは確認できたかな?
邪馬台と書いてヤマトと読む。
倭と書いてヤマトと読む。
つまり邪馬台国とは倭国と同義で、訓読みにさらに漢字を当てただけ。
魏志にある女王国もまた同義である。
卑弥呼の称号は邪馬台国の女王ではなく、倭国女王(親魏倭王)である。
倭国は稲作伝来の地である玄界灘沿岸に成立し、対馬海峡の交易により発展した海洋国家であり、海人の国を意味する「天津国」とも呼ばれた。
生活の基盤が次第に漁撈から稲作と交易にシフトすると博多がその中心として発展したが、卑弥呼の時代には王都は博多からやや離れた伊都国に置かれた。
倭国の都は紀元前から一貫して筑紫、現在の福岡県にあった。
漢の時代に金印を授かり冊封され、女王卑弥呼の時に魏から冊封された。
倭国においては筑紫の他に、豊国、肥国などの有力な国があり、魏志によると東の海を渡ったところにも倭種つまり出雲や近江、越など日本海沿岸に国が続いていた。
畿内は京都も大阪も奈良も、沼地であった。
ところがどっこい、倭国の都は近江→濃尾→大和だったんだよねー
>>259 >邪馬台と書いてヤマトと読む。
これは正しい
>倭と書いてヤマトと読む。
ここが既に正しくない
倭はもともとwaとかuiaのような発音
倭人が漢字を習得して自分の国を大陸が倭國と表現しているのを知ってから
ヤマトの音を当てただけ
山と書いて日本語では「やま」と読むけど、もともと中国人が「やま」とは読まないのと同じ
>つまり邪馬台国とは倭国と同義で、訓読みにさらに漢字を当てただけ。
だからここから先は見当違い
倭は、倭人が住む範囲だよ
そこで成立した国が倭國
北部九州も倭の範囲内で倭國の一員
奴国が女王国の傍国に上げられているからね。
女王国の傍にある国。
傍の字義通りなら、奴国は女王国に含まれない。
>>258 別人じゃい
そしてバルディビア土器は縄文土器
>>264 >奴国が女王国の傍国に上げられているからね。
其餘旁國の最後の奴国を伊都国の隣の奴国のことだと考えるのは間違いだと思うぞ
北から順に国の名前を挙げていくっていう体裁なのに、最後の国が邪馬台国より
北にあったらおかしいだろう
奴国の王家も女王国についた勢力に滅ぼされたのかもね。
一大卒の管轄下に入ったと。
奴国内で下剋上があった可能性もあるな。
>>265 >別人じゃい
匿名掲示板では何でも言えるけど、それを信じて貰えるわけじゃないんだよww
「文は人なり」って言葉、知ってるかい?
>バルディビア土器は縄文土器
じゃあスミソニアン博物館に行って、展示名が間違ってますよって言って来なよ
これは縄文土器ですよってww
>>267 >奴国の王家も女王国についた勢力に「滅ぼされたのかもね」。
>奴国内で下剋上があった「可能性もあるな」。
日本史板は学問板なので、推測・想像ではなく、「根拠」や「理由」を
はっきりしたソースで示せる形で議論を進めた方がよいと思う
なぜ奈良に3Cの巨大古墳が???? → 邪馬台国があったから。
なぜ沼津に3Cの巨大古墳が???? → 狗奴国があったから。
>>268 分類上の話なのに何故そうなるの?バカなの?
つーかそんなに気になるならID導入しろやカス
>>268 そして俺の文体が
>>254 と同一のものに見えているなら義務教育からやり直せ
知ったか太郎
ヤマタイではなく、ヤマダイらしいね。
必ず濁るんだって。中国人の学者が言ってた。
おそらく山田のことだろう。
>>271 >分類上の話なのに
分類上の話だから、「バルディビア土器」と「縄文土器」とは
「違う名前の別の土器」だってことだろ
別人なら他人の話に口をはさむなや
しかも自分の手柄としてww
言葉が悪い人は、たいてい余裕のないやつだよ
271が誰でもいいけどさ、
>>164のこれに答えてあげなよ
「エヴァンズ夫妻以外に、エクアドルで縄文土器が見つかっていると言ってる人は?」
>>130 >距離が国と国の間だけで国内距離はないとか、<
国内距離は、里の記載の最小単位が百里だから、
50里以下にしかならない区間は記録されていない。
>位置説明と移動説明が違うとか<
使い分けるのがのが、陳寿や人類の常識的説明法。
>出発方向が書いてあるだけとか、<
紀行文での説明においては、
「出発説明+途中説明+到着説明」の順に説明する事が、全ての人類の常識。
>末慮国から伊都国は、どうやっても北東で90度回っている<
「東南」は、出発時点の出発方向であり、
太陽の動きや日の出日の入りなどで東西南北を計測して来た人類は、
90度も間違えない。
>>130
>現在の唐津港から海岸沿いに出発方向だから南東という主張は
1.移動は国の外れからというザラコクの主張と矛盾する<
「国の外れ」なんて言っていない。
原則は、「居住外縁部だろう」と言っている。
>末慮国の中心は<
末盧國の中心を通った、という主張が、そもそも何の根拠もない。
上陸地が、末盧國の中心でない場合など、幾らでも有り得る。
>現在の唐津港より東側にあるので、「ザラコクの主張が正しいとしても」
出発位置にはならない <
上陸地は、当然一大國からやって来て、上陸するに安全な場所を選択するものであり、
松浦川河口の東に上陸するのなら、始めから浜崎やそれ以東の伊都国に直行する事を選択事になる。
>2.当時の末慮国の港は現唐津港の位置にはなく松浦川河口近くの潟湖 <
「松浦川河口近くの潟湖}の存在や安全性の確認が困難。
>現唐津港付近には弥生時代の遺跡がない<
以前から旧知の港でなければ、国鉄が「西唐津」にまで延伸して駅を造る必要がない。
>松浦川河口の潟湖が港湾として優れているし、潟湖が港になっている例は多い
港を出発地とするという「ザラコクの主張が正しいとしても」そこから
海岸沿いに出発なら「東」方向で、魏志倭人伝の「東南」はそれでも間違いになる<
現唐津駅付近からでも、出発方向は、「東南」になる。
魏使らは、東西南北を計測する方法を知っていたから、「東と東南」を間違えるような失敗もしない。 >>131 >隋書の対馬から壱岐~筑紫が「東」になっているのを、<
「度百濟、行至竹島、南望身冉羅國、經都斯麻國、迥在大海中。又東至一支國」は、
竹島から一支國へは、「東」へほぼ一直線。
「壱岐~筑紫」は、「東」とは書かれていない。
>「經」都斯麻國だから対馬は通ってないとか言っているが、「經」は経由の経だからしっかり通ってるぞ<
「至」は、到着そのものを直接示すが、「經」は、「通り過ぎる」事が中心的な意味。
>三國志の「經」の実例 三國志卷一/魏書一/武帝紀第一
引軍出盧龍塞、塞外道絕不通、乃塹山堙谷五百餘里、「經」白檀、歷平岡、涉鮮卑庭、東指柳城。
軍勢を率いて盧龍塞を出たが、塞外の道は断絶して不通であったため、山を壍って谷を堙ぐこと五百里余り、
白檀を「経過」し、平岡を通過し、鮮卑の地を渉り、東へと柳城を目指した。<
これも、「經」は、(至って訪問したのではなく)単に「通り過ぎた」事を意図し、
「歴」は 、「歴韓國」と同じく「歴訪」した事を示し、
(通り過ぎたのではなく)至って訪問するような実態があった事を示すから、
はっきり区別されている。
>そして、旧唐書の大理-安南間は、前スレの950で詳解してある
この三ヶ所はどうやっても「大陸の史書の方位の間違い」なのは確定<
旧唐書でも、方位を殆ど間違っていなかった、という事で確定していた。
>「大陸の史書は方位を間違うはずがない」というのは、複数の反例によって否定される
従って論理学的に「偽」だ<
「大陸の役人たちが実際に確認した方位記録は、ほぼ間違えない」
というのは、この・・・・男が提示した複数の例によっても肯定された。
>>276 >以前から旧知の港でなければ、国鉄が「西唐津」にまで延伸して駅を造る必要がない。
弥生時代に港があったから国鉄が駅を作ったとでも?
ww ww ww
>>276 >現唐津駅付近からでも、出発方向は、「東南」になる。
現唐津駅付近から、虹の松原はほぼ真東
前原は北東
>>263 倭地と倭国は違う。
倭人が住む地域の中で、女王に従っているのが倭国、九州北部。
それ以外の地域は中国に接触していない。
>>281
>倭人が住む地域の中で、女王に従っているのが倭国、九州北部。
>それ以外の地域は中国に接触していない。
阿波はどうなの? @阿波 >>280 あるけど?
テンプレにも詳しく書かれてる
>>283
>倭人が住む地域の中で、女王に従っているのが倭国、九州北部。
>それ以外の地域は中国に接触していない。
畿内はどうなの? @阿波 >>281 こういう、根拠なき言い張りオンリーが、九州説だな
>>147 >>韓国に入ってからは、「歴韓國乍南乍東」の陸行だった、と書かれている。<
>トンデモ古田本にか? w <
やっぱり、文部省や学会教育界の教科書の魏志には、
「歴韓國乍南乍東」なんて書かれておらず、
書かれてあっても、「南→東」の嘘つき騙しと同じように、
「歴韓國乍南乍東」が「水行」だ、と書いているのかい?。
>>286 「水行歴韓國乍南乍東」と書いてあるな。
>>151 >「輪」は「和」であり、平和を意味し、
聖徳太子の十七条の憲法「和を以て尊しとなす」の隠し暗号である。<
書紀に書かれた厩戸は、
善光寺との往復書簡の、
「命長七年丙子二月十三日」 進上 本師如来寶前 斑鳩厩戸勝鬘 上」
の「命長七年」が646年であった事で、
書紀の聖徳太子の死亡後20年以上生存していた事になり、
だから、書紀の「聖徳太子」は、書紀の造作捏造人物であった事になった。
>このことばは日本人の日本人による生殖を示す。<
この男は、
書紀の聖徳太子の「和を以て尊しとなす」の憲法思想と全く違反して、
排他的人種差別の「日本人以外とは和を以たない」という、
殺戮戦争的な思考を持った、・・・・人種である事を示す。
>>154 >北部九州が「会稽東治之東」だなんて、九州説は方向オンチだね <
いや、北部九州も、
会稽東治の海岸から、「東~東北東」の間のなっているから、
「之東」に、ほぼ一致しており、
陳寿の位置推定は間違ってはいない。
>>290 >会稽東治の海岸から、「東~東北東」の間のなっているから、
それは真っ赤なウソでしょう
なんの証拠も無いし
致命的な指摘を食らって
なにも証拠のない言い訳しかできない
九州説って、もう
風の前の塵じゃ
ありませんか
>>157 >それ、ちいさな方墳ですけど<
祇園山は、
国内で唯一、「大作冢、徑百餘歩、jun葬者奴婢百餘人」を満たし得る、
普通のサイズの、四隅円弧の不定形の「高冢」古墳だよ。
>>158 >>「畿内」なんて存在していなかった。<
>当時まだ北京がなくても誰もが普通に「北京原人」と言うし、
誰もそれを変だとは思わない<
北京は、普通の首都の地名に過ぎないが、
「畿内」や「朝廷」は、明らかに「皇帝や天子や天皇」の存在や居地を示すので、
そのような思想宗教的な「刷り込み宣伝の騙し文言」である事になり、
倭国の別種の旧小国で「東征毛人55国」の一國である大和に関して使用する事は、
黙過し難い。
>>162 >そもそもヤマトだったら、邪馬臺って書かれるだろ? <
邪馬臺に「ヤマト」という音韻はないよ。
>>164 >エヴァンズ夫妻以外に、エクアドルで縄文土器が見つかっていると言ってる人は?<
そりゃ、エヴァンズ夫妻の研究室にいた学者らや、
論文を採用掲載した学会誌の職員や、
古田説派の人々や、
mutouha氏らの九州説学者らが言っている事になる。
>>165 >で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、<
魏略~太平御覧や通鑑前編の中国史書や、松野氏姫氏系図や新撰姓氏録や、
倭人伝の「大夫」の記録や、甕棺や支石墓の存在。
>その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と中粒種のイネは?<
稲に関しては、mutouha氏が論証していた。
>>166 >で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したと言っているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?<
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した、
という事を否定している「反共戦争思想宗教的な国粋皇国史観」の、
サギ考古学者の氏名と所属団体は?。
ザラコクって思想統制やりたいスターリン崇拝者かなんか?
>>168 >「南≠東」が立証できないので
>>167は×です<
「南=東」も「南→東」も、この男は立証出来ないので、
この大和説男も、×人間です。
>>305 そういう中傷しか出来ない事実が
九州説の惨敗を証明している
>>277 >「壱岐〜筑紫」は、「東」とは書かれていない。
「經都斯麻國迥在大海中 又「東」至一支國又至竹斯國」
東に向かうと壱岐、それから筑紫に至るんだよ
そのまま東に進んでる
「竹島から東で壱岐が正しい」と言い張るなら、どうしてそこから筑紫への
「方向転換が書いてない」んだ?
海の上だから「ザラコク理論(笑)」の「海岸沿いだから書かなくても分かる」も
通用しないぞww
どうやっても隋書のこの部分の「方位は間違ってる」んだよ
漢文の読めないやつは大変だな
まともに読めないから、正しく解釈できずに珍文漢文なんだろ?ww
九州説はこんなのばっか
>>298 んなこと聞いてねえ。
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と中粒種のイネは?
.
>>300 んなこと聞いてねえ。
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
.
>>169 >神武系は近江王朝なんだよ <
近江王朝は、出雲や越系と、筑紫倭国の「東征毛人55国」の妥協的融和王朝。
>南九州は交流した地域 <
南九州は、東テイ人地域であったが、
宮崎は、倭奴國の阿毎氏系のウガワフキアエズらの植民地の投馬國になっていたようであり、
鹿児島の東テイ人の本拠は、後漢最末期に後漢に朝貢したのを最後に、
卑弥呼の頃に投馬國の中に含まれたようであった。
>北九州の奴国が脅威だったため、日向王朝をつくった<
その日向王朝と言うのが宮崎の事であったんなら、
伊都国系の阿毎氏と東テイ人系との混合王朝。
大和や近畿を意図したのであれば、×。
>>172 相変わらず、一つも直接的証拠を出せずに、分裂幻覚の妄想ばかりの大和説。
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>174 >>魏使らが(方四千余里の)對海國の国内移動を記録し、
(方三百里の)一大國の国内移動を記録し、<
>飼ってに「国内移動」って言い張ってるけど なんの根拠もないよね<
国内見聞移動やその記録があった事が、史料事実であり、史料実態。
>逆に、ほかの国で「国内移動」が無いなら 支離滅裂だよ<
50里以下位の「国内移動」は、記録されていない、
という事が、
史料事実であり、史料実態。
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>176 以上、この男は、
史料事実の否定曲解や、無史料実態無視などの嘘吐き騙しを、言い張るばかりであり、
分裂幻覚の妄想の×人間。
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>185 >側副傍線行程国説明とか ただ言い張るだけで なんの根拠もないだろうに<
出発と到着の間に、途中の移動などの説明があったのか?、
という史料事実や史料実態の存在が、根拠。
>>333 曲解だ嘘だと叫ぶばかりで、その証拠が出せないのは
負けて悔しいぃぃ、と喚いているのと同じ
>>329 >50里以下位の「国内移動」は、記録されていない、
おいおい、自分が短里を主張してるってこと忘れてないか?
「九州説のいう短里」はだいたいが70メートルくらいだろ?
50里って3.5キロだぞ?
狭すぎるとは思わないのかい?
それ以下の国内移動しかないって主張するのって、意味がないと思わないのかい?
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>187 「南→東」などの嘘吐き騙しの・・・・大和説者の論理が、
自己矛盾していないことは、滅多にない。
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>338 >出発と到着の間に、途中の移動などの説明があったのか?、
いや、途中の移動の説明なんて、倭人伝のどの国の記述にもないだろう
あると言い張っているのはザラコクだけで
古田武彦氏もそんなことは言ってないぞ
九州王朝教の教祖の説を、弟子が勝手に修正してはいけないだろう?
儒教道徳の基礎に悖るぞ!
>>338 途中の移動などの説明がどうだこうだ
と言う理由がまるで無いので
無根拠ザラコクは独善幻覚の妄想の×人間
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>342 という証拠は?
証拠もないのに、また中傷ですか?
>>189 このように、
「南→東」などの嘘吐き騙しの大和説者らは、
もなく史料事実根拠も言わず、
根拠もなく言い張るだけ 。
理由は言わない。
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>348 「もなく」って、何がないの?
畿内説の者が、そんなことをしたって証拠は?
またも只のデッチ上げ中傷かな?
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.html
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>300 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
.
>>298 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
.
>>192 >もう一つ、大陸史書の方角の間違いの例を挙げてあげよう
新唐書 卷二百二十 列傳第一百四十五 東夷 日本 其「東」海嶼中 又有邪古波邪多尼三小王
この邪古が屋久島で、多尼が種子島だというのが定説 「その」っていうのが日本を指すのだから、 「東」は「南」の間違いだよな?<
新唐書は、当然唐会要倭國伝の、
「倭國東海嶼中野人。
有耶古,波耶,多尼三國。
皆附庸於倭。
北限大海、西北接百濟、正北抵新羅。
南與越州相接」の文の紹介引用。
これは当然「東西南北」の方向の説明文であり、
「倭國東海嶼中、野人」で、東の本州や四国に「野人」あり、という意味であり、
その次に「有耶古,波耶,多尼三國」で、薩南諸国を指している。
その野人とは、当然、倭国の「東征毛人55国」や、元の侏儒國地域を含む事になる。
そして、新唐書の、
「其東海嶼中又有邪古、波邪、多尼三小王、北距新羅、西北百濟、西南直越州、有絲絮、怪珍云」
は、唐会要情報からの「明らかな誤引用」である事になる。
だから、「東は南の間違い」であった事にならず、
この「大和説にとっては都合の悪い事は何でも間違いだ」とする・・・・大和説男が、分裂幻覚の妄想のアホ詐欺師であった、という事をしめす。
>>359 >南與越州相接
ってことは、倭國はベトナムと接するほど南にあるって唐会要でも
考えられてたってことだよな
会稽東治の東が九州だなんてとんでもない
もっとずっと南まで倭国が続いてると考えられていた訳だ
「その認識に合わせるため」に、魏志倭人伝撰述時に、投馬国行きと邪馬台国行きが
「南」とされたんだよ
言い訳をするたびに、持論の足場を切り崩す、そんなスタイル
そして、唐会要の引用だろうがなんだろうが、新唐書の 其「東」海嶼中の
「東」が「南」の間違いであることにはなんの変わりもない
ザラコクの書いたことは
「理由があれば、大陸史書の方角は間違いを冒す」
という説明にしかなっていない
つまり、「大陸史書の方角が間違うはずがない」は
論理学的に「偽」だ
ザラコクの大好きな「論証抜きの南≠東」には何の意味もない
二度と書くなよ
自分で論証したんだからな
「唐会要の引用という理由があれば
新唐書の方角は間違うのは当たり前」って
>>195 >「陽苴咩城」でググってみなよ ウィキペディアの中国語のページが最初に出てきて
「羊苴咩城,又称“阳苴口芊城”、“阳苴咩城”、“苴咩城”,
位于今天的『云南省大理白族自治州大理市』」って書いてあるだろ?
これは、新唐書のあとの史書にも出てくるから、比定地ではなく確実に「大理」だよ<
何だ?。
やっぱり現代中国政府や学者らの「推定」ではないか。
それに、旧唐書には、もう一つの「南去太和城十餘里」の太和城があり、
陽苴咩城との関係も不明だな。
>>大理だとしても、そこからハノイは「東南」よりも少し北であり、
大理→昆明→南寧方面の水陸行は、更に「東」方向に近くなって、殆ど「東」。<
>グーグルマップで測った大理ー安南間の角度 方角 : 131.001°
135度が南東だから、4度しかずれてないよな?
これが、「ほとんど東」だったら、南東という方角はないわ <
大理ー安南は、相当な山越えであり、
だから、「通水陸行」コースは、
南寧方面を経由する「殆ど東コースだ」ったんだろう、と言っている。
つまり、「東至安南如至成都通水陸行」は、殆ど間違っていない。
南は間違いない。
ただ、会稽云々の件があり、短里で書かれた報告を長里だと思い込んでしまっただけ。
それを、南を東に勝手に言い換える根拠としようなど、詐欺まがいだな。
>>196 >エクアドルのバルディビア土器片と阿高式土器の文様が似ているのを
約3500年前の南米インディオのミイラからズビニ鉤虫の卵が検出されたから
縄文土器ではないかという話が
南米で縄文土器が出たから縄文人がズビニ鉤虫を海洋ルートで持ち込んだという話に
変わってしまっている<
「約3500年前の南米インディオのミイラからズビニ鉤虫の卵が検出」は、
当然、ズビニ鉤虫があった縄文人の「太平洋横断の往復渡航」の証拠になるから、
日本の(反古田や反九州説の)通説大和説者が、
「太平洋横断ではなく、シベリア~アラスカ経由だ」という反論をしたので、
九州説者から、ズビニ鉤虫は、摂氏21度以下では生育出来ない、という反論があったもの。
>>198 >>もしそうであれば、また、書紀のインチキがバレた事になる。<
>日本書紀巻第一 神代上 :廼生大日本 「日本、此云耶麻騰。下皆效此」
「日本」の初出のところの読み方の註がついていて
「日本、これを耶麻騰(ヤマト)と云う。以下みなこれにならう」<
バカじゃねえの?。
筑紫倭國が中国に「日本」と名乗ったのは、晋の惠帝への遣使の時。
大和日本国が「日本」と名乗ったのは、隋の初代文帝への小野妹子が最初。
そして、(書紀が依存史書であった)古事記は、
一貫して「日本」とは書かずに、「倭」を使った。
それを、書紀は「日本」と書き変えた。
それが、史料事実であり、史料実態。
だから「廼生大日本 「日本、此云耶麻騰。下皆效此」」という書紀は、
古事記の「倭」を「日本であった」というインチキをした、
という事であった訳。
>そして、ここの大日本がオオヤマト=大倭=大和な訳だ<
嘘を付いて騙すなよ。
「耶麻騰」には、「大」なんて付いていないよ。
大和には古くからの「ヤマト」という呼称があった、というだけだ。
筑紫倭国が植民地を拡大したので大倭と呼ばれるようになった。
ヤマトに大和を当てたのは、ヤマトが筑紫倭国を併合して大倭の支配権を得たから。
>>199 >>新大陸の南米のエクアドルで見つかったのをどう説明するのか?<
>それ、縄文土器じゃないんだよ<
そりゃ、列島の縄文土器も「皆完全に一致」ではないよ。
要は、何故同じような形態の土器が造られたのか?、という事が問題。
>バルディビア土器って書いてあるだろ 文様が「似てる」と感じた人がいるだけ<
模様だけではないんだろうねえ。
やはり、海上や砂漠のような地域での長距離や長日数移動では、
「水」を確保する容器の携帯が不可欠だった、
という必要の問題。
「月の砂漠」の「王子様とお姫様」も、
それぞれのラクダに「甕」を持ってそれを繋いでいた!。
水を失えば死ぬ、って事を知っていたんだよ。
>>363 ズビニ鉤虫が摂氏21度以下で生存できないのは九州説とか関係ないから。科学的事実。
それなのに畿内説がさも生きられるように言い張っていると。
バルディビア土器と九州の曽畑式、阿高式土器は器形がぜんぜん違う
曽畑式、阿高式土器は朝鮮半島の櫛目文土器と文様も滑石を混ぜる製法も共通した土器
櫛目文土器はバルト海沿岸、フィンランド、ボルガ川上流、南シベリア、バイカル湖周辺、
モンゴル高原、遼東半島から朝鮮半島に分布する
ズビニ鉤虫がバルディビア遺跡で検出されたのではない
>>202 >>「通水陸行」ルートになる大理→昆明→南寧方向は、殆ど東行きであり、
「東安南」の「東」は殆ど間違っていなかったんだよ。<
>これも同じくグーグルマップで測ると 方角 : 117.181° 八方位の場合、「東」となるのは90±22.5度の範囲(67.5~112.5)だから
117度は東の範囲に入らず、南東だな どうやっても間違ってるんだよ<
おや?、「大理→昆明→南寧方向」の通水陸行コースを採っていないな。
「大理→昆明→南寧方向」なら、「通水陸行」だし、方向も見ただけで、「東~東南東」方向だよ。
それに、「大理→安南」の移動であれば、
安南は当然「安南の居住外縁部」までの移動であり、
安南の外縁部は、当然南シナ海沿いの方になり、南寧方面になるんだよ。
勿論、大理→安南の直行方向では、巨大な高山越えになってしまい、
「通水陸行」なんて、全く不可能なんだよ。
>そして、如至成都は距離 <
「距離なら里数を記載」する筈であるから、×。
「如至成都」は、
成都へ至る行程と同じような「通水陸行」行程である、という意味。
>通水陸行 はソンホン側沿いの経路<
直ぐにかなりの巨大な山越えにぶつかってしまうから、×。
>大陸史書の地理・旅程記事は、基本的に直線方向・距離で示されている <
旧唐書も、地理説明と移動説明を、はっきり書き分けていた、という事になった。
>で、間違うときは間違うんだよ<
旧唐書も間違っていなかった。
>>204 >>渡海の千余里は、出発港~到着港間の概数の里数。
その国の到着港~出発港の間が、それぞれの国内の見聞移動の概数里数<
>国内移動は記載されないって書いてたのはザラコクだよな?<
そんな事は、書かないねえ。
国内移動は記載されている場合もあれば、記載されていない場合もある。
>そして、「その国の到着港~出発港の間」は、陸行なのか水行なのか、どっちだ?<
その国内の見聞移動の記載があれば、陸行であり、
なければ水行だろう、と思うよ。
>「見聞移動の概数里数」これ、初見なんですが?ww また新概念を「思いついた」のか?<
大和説の・・・・アホに、曲解されないような書き方をして置いただけだ。
>「島巡りが記載されている、大陸史書の別の例を一つでも挙げて見せてくれ」って
いうのは、どうなった? 一つも見つけられないのか?ww<
中国史書群に、海外の「山島國」への旅程の記載があったのか?、も知らんよ。
>「出発港~到着港間の概数の里数」と「国内の見聞移動の概数里数」は
足すのか足さないのかどっちだ?ww<
・・・・アホには判らんらしいけど、
50里以下の短距離は、足していないんだろうなあ。
>>205
>東征毛人五十五國 =近畿以東(北関東含む)
西服衆夷六十六國 =西瀬戸内・九州
渡平海北九十五國 =東瀬戸内・山陰・北陸
これ全部、倭国(阿波)から進出した忌部一族の開拓地域なんですよ。 @阿波<
倭王武がいた倭国は、南≠東によって、(阿波ではなく)筑紫の倭国なんだよ。 >>210 >>大理→昆陽→南寧が、東~東南東の通水陸行路になる。<
>地図を見ろって! <
地図で「大理→昆陽→南寧」ルートを見ろ、って。
>それに、ザラコクのいう「出発方向」で見たら、
大理から出て行く道はさらに南になるぞ<
「通水陸行」は文字通り、(位置説明の中にあっての)、途中移動の説明だよ。
>>213 >>「到」は「至って立つ」という文字だから、 「(立派に)目的地に立った」という意味が強いが、
「至」は、普通に「目的地に着いた」というような意味で、 少し、使い分けがある。<
>還「到」龍亢、士卒多叛。 「至」銍建平、復收兵得千餘人。
どちらも「目的地に着いた」という意味しかないぞ <
還「到」龍亢、は、(努力して)還り来て龍亢に到り立った、という強調する意図が強いが、
「至」銍建平、は、普通に銍建平に至った、と区別している。
>「到」に「(立派に)目的地に立った」という意味があるなら、
「士卒多叛」(士卒の多く叛く)になった土地には使えないだろうに
使い分けなんてないんだよ <
「至」の場合の「復收兵得千餘人」では、「努力」した形跡が少ない。
倭人伝の場合も、狗邪韓國と伊都国に「到」を付けており、それぞれ、
倭地の入り口にようやく着いた、という事や、
倭國の中心の一大率の国にようやく着いた、という意味合いが強い。
>>361 >それに、旧唐書には、もう一つの「南去太和城十餘里」の太和城があり、
>陽苴咩城との関係も不明だな。
本当に、何も知らないまま思いつきだけで反論を書いてるなぁ
だめ人間の極致
前スレの950にきちんと書いてあるだろうが
「牟尋は南詔国の第三代国王の異牟尋 都を太和城から北方の陽苴咩城に遷都した
陽苴咩城は今の大理 」
太和城は前都で、今も大理市内に遺跡があるよ
陽苴咩城が、今の大理故城よりも北の位置で、大理市外からは外れる
>大理ー安南は、相当な山越えであり、
ソンホン川の源流沿いに行けば、川の水が下るように、ずっと下り坂で
山越えなんてないぞ
地図を見ろって言ってるだろうが!
>南寧方面を経由する
「南寧」ってどこだよ! そんな地名はないぞ!
地名まで捏造するって、どこまで追い詰められてるんだよww
>>363 >ズビニ鉤虫があった縄文人の「太平洋横断の往復渡航」の証拠になるから、
ならないんだよww
論理の分からない人には理解できないかもしれないが、それが成り立つためには
当時、縄文人以外がズビニ鉤虫を持っていないことを論証しないといけない
そして、ズビニ鉤虫の蔓延地の広さから、それを言うのは無理
>>215 >単なる自分の独断を根拠もなく史料事実だと言い張る困った爺さんだな <
中国人は、
「形状や意味が類似している文字」も、全く同じである、というのではなく、
微妙な意味合いの違いを知っていて、使い分けていたんだな?、
という事が史料事実であり、史料実態。
>>364 >バカじゃねえの?。
バカはザラコクww
日本という国号を作った政権が編纂した史書だから日本という表記を使ってるんだぞ
そして、大王位に関わりのないところでは、倭(やまと)の表記も残っている
「爲椎根津彥(椎此云辭毗)此卽倭直部始祖也」とかな
>古事記の「倭」を「日本であった」というインチキをした、
>という事であった訳。
そう思わないとやってられないんだろうけれど、
古事記のもととなった国記が推古朝に作られ、その時(というかその前からずっと)
倭国の代表は「現在の奈良盆地に中枢を持つ現皇統につながる王権」で
その王権の人物である天武・持統朝に、日本という国号をその王権自ら作った
それだけのことだよ
>嘘を付いて騙すなよ。
>「耶麻騰」には、「大」なんて付いていないよ。
日本書紀程度の漢文さえ読めないんだなww
廼生大日本 「日本、此云耶麻騰。下皆效此」 って書いてあるだろうが
大日本の「日本」を「耶麻騰=ヤマト」と読むんだから、その前に大が付いてるだろ?
大日本=大ヤマトっていう関係だぞ?
漢文読めなくても、文字だけ追えば分かるだろうに
>大和には古くからの「ヤマト」という呼称があった、というだけだ。
そうだよ?
それがどうかしたか?
その「ヤマト」が、大陸の人に音訳で「邪馬臺」と記されたってことだ
>>365 >ヤマトが筑紫倭国を併合して大倭の支配権を得た
そのとおりだろ?
後漢書の時点で大倭とあるんだから、
卑弥呼の頃には、ヤマト=畿内王権が北部九州まで範囲で祭祀を統一して
倭国の代表になっていた訳だ
何も問題ないじゃん
>何故同じような形態の土器が造られたのか?、という事が問題
土器を作るときに、誰でも思いつくような文様が一致しているってだけだぞ
画像検索してみてみなよ
>模様だけではないん「だろうねえ」。
はい、「根拠」 なしww
>>367 >ズビニ鉤虫が摂氏21度以下で生存できない
中米にもアフリカにもズビニ鉤虫の蔓延地があるんだから、わざわざ太平洋を
渡るルートに限定する必要はどこにもないだろ?
>>216
>>「至」なら、「到着した」事までをはっきり示し、その先は主張していないが、
「經」では、「通り過ぎて、その先へ行きました」という意味が強く、
「到着上陸」の意味が非常に少ない、というのは、常識だろ?。<
>別に「通り過ぎた」であっても、対馬を通り過ぎていれば
「經都斯麻國迥在大海中 又「東」至一支國又至竹斯國」
の「東」は「対馬から壱岐の方角」だろ<
「明年、上遣文林郎裴清使於倭國。度百濟、行至竹島、
南望身冉羅國、經都斯麻國、迥在大海中。又東至一支國・・・」
だから、(その前に至った)竹島から、その次の「至」の壱岐へは、
ほぼ「東」にまっすぐだ。
>そして、現実に壱岐は対馬の「南」にあるのだから、「南」と「東」の
取り違えの確実な例になる訳だ <
都斯麻國には寄港も上陸もせずに、「竹島→一支國」に東に向かって行った事になり、
「対馬から南」なんて関係もないし、
散り違えもなかった、という事になる。
>で、ザラコク理論だとこれは、位置説明なのかい? それとも、移動説明?
考えたこともないだろ? <
始めから書いておいたように、
竹島→一支國の移動説明。 >>373 >「大理→昆明→南寧方向」
だから、「南寧」ってどこだよ
安寧って書いてる場所もあるし
安南は今のハノイだ!
そして、現在でも中国との内陸貿易は、ソンホン側沿いの経路で行われている
>安南の外縁部は、当然南シナ海沿いの方になり、南寧方面になるんだよ。
その南寧って本当にどこだよww
架空の地名なら確認されないから論破できないだろうってことか?ww
>勿論、大理→安南の直行方向では、巨大な高山越えになってしまい、
大理が既に山岳地帯だって分かってるか?
>>221 お前もそうだが、
「南→東」の嘘つき騙しの大和説者は、
文献解釈や、遺跡や遺物の年代をや、メチャクチャに歪曲するなあ。
>>373 >「距離なら里数を記載」する筈であるから、×。
距離の記載がなければ、地理・旅程記事にならないんだよ
そして、里数に限らず、日数で書いたり、同じ距離を示したりしてあるところもある
>>373 >旧唐書も、地理説明と移動説明を、はっきり書き分けていた、という事になった。
なってない
成都に行く経路は、「地理説明」と「移動説明」のどっちだ?
それにまた、新しい用語を作ってるし
「地理説明」って何だよww
最初は「四至説明」って言ってて
次に「四至説明的な位置説明」とか言い出して
今度は「地理説明」かよww
本当に「何の裏づけもない思いつき」をよくもまあ、堂々と書けるよな
最初から最後まで「根拠」がないしww
>>374 >国内移動は記載されている場合もあれば、記載されていない場合もある。
その「記載されている場合」がどこにあるかと訊いてるんだが?
>>374 >なければ水行「だろう、と思う」よ。
はい、また「根拠」なしの妄想
>>374 >大和説の・・・・アホに、曲解されないような書き方をして置いただけだ。
大和説のザラコクアホに ってひどいことを書くなぁww
曲解されないようにもくそも、何の説明もないから、理解のしようもないぞ
ザラコクの頭の中はザラコクだけのものだから、他人には理解できないんだよ
>>374 >中国史書群に、海外の「山島國」への旅程の記載があったのか?、も知らんよ。
漢籍電子文獻資料庫で全文検索をかけても、「山島國」なんて国は
中国の史書には1ヶ所も出てこないね
島巡り仮説など、妄想にすぎないということだ
>>374 >50里以下の短距離は、足していないん「だろう」なあ。
「根拠」のない「ザラコクのザレゴト」は書くなよ!
>>376 >「大理→昆陽→南寧」ルート
南寧なんて場所はないんだから、確かめようがないだろ?
>「通水陸行」は文字通り、(位置説明の中にあっての)、途中移動の説明だよ。
これまで移動説明は出発方向だって、末慮国のところでさんざん自分で言ってたよな?
大理から出る道は基本的に南方向で、東から南東どころかさらに方角がずれる
最終的に「通水陸行」するのは、誰がなんと言おうと、「ソンホン側沿い」
それが、中華王朝の内陸部から安南(ハノイ)に抜けるメインルートで
現在も利用されている
そして、移動説明だというなら、まさにここが移動部分で「南東方向」
どう言い逃れようとしても、ムダだよ
>>377 >還「到」龍亢、は、(努力して)還り来て龍亢に到り立った、という強調する意図が強いが、
元いた場所に還えるんだから、努力する必要はないだろ?
>「至」銍建平、は、普通に銍建平に至った、と区別している。
新しく到達した場所だから、多くの将兵を得ることができたんだぞ
本当に、意味の通らないことしか書けないな、ザラコクは
>「至」の場合の「復收兵得千餘人」では、「努力」した『形跡が少ない』。
そんなのザラコクが決めることじゃないだろww
本当に「根拠なし」の「ザラコクのザレゴト」 ww
>>377 >倭人伝の場合も、狗邪韓國と伊都国に「到」を付けており、
それに特別な意味はないっていう話なんだが?
伊都国が大陸の史書に出てくるのは、あと、北史と梁書にあるが、
どちらも「至」を使ってるぞ
北史/ 列傳 凡八十八卷/ 卷九十四 列傳第八十二/ 倭
「一海千餘里,名末盧國。又東南陸行五百里,『至』伊都國」
梁書/列傳 凡五十卷/卷五十四 列傳第四十八/諸夷/東夷/倭
「一海千餘里,名未盧國。又東南陸行五百里,『至』伊都國」
到と至に特別な使い分けはないよ
>>385 >始めから書いておいたように、
>竹島→一支國の移動説明。
移動説明なら、經都斯麻國で、対馬を通ったのは確実だよな?
だって、「対馬を経由した」って「移動経路を説明」してるんだから
で、対馬に来て、そのまま東に行ったら壱岐には着かないだろ?
本当に、自分の書き込みでどんどん矛盾していく芸風だねぇ
海幸彦山幸彦の神話は何なんだろう。津波を思わせる記述もあるし。
南海トラフ地震は津波の堆積物でいつ頃あったか分かっている。紀元前後、次は二世紀半ば。
海幸彦山幸彦については色々伝承があるが、例えば、
潮嶽神社
ヒコホホデミノミコト(山幸)に追われたホデリノミコト(海幸)がこの地にたどり着き、居を構えたと伝えらています。
神話、海幸彦、山幸彦では山幸彦の影に隠れ、山幸彦ほど有名ではありませんが、海幸彦は隼人(南九州に居住する氏族)の祖といわれております。
隼人の祖は海幸彦。
海幸彦と山幸彦は対立していた。
海幸彦は内陸へ追いやられたとある。
>>223 >>隋使の記録した文字を、魏徴らが隋書に書いた文字なのであり、<
>いやいや、版本の「邪摩堆」の「摩」の字の下の「手」の部分の縦線が
刷りの調子で二本に分かれてたんだよ そうすると「手」が「非」に、「摩」が「靡」に化けるだろ
「隋使の記録した文字」じゃなくて、伝書の途中で化けたんだよ <
ダメだよ。
版刻では、(活版のように一文字ずつハンコをつくるのではなく)、
底本写本や前版本を版板に貼り付けて、文字線を浮かし彫りにして、版板を造る筈だから、
「一本線」を「二本線」に間違うような事は、殆どないし、
「刷りの調子」なども、全く関係がないし、そんな確率は非常に低い。
確率の非常に低い推定など、何の価値もない妄想でしかない。
そんな事なら、版本の事実の通りに受け止めておいて、その上に立っての論をしておいた方が、
はるかに確率が高い。
数年前の話、
世界最高尊厳が何やらと言って
怒っていた人物がいたみたいなんだけど
『宜子女王』の話?
『天津狐』画像をググると、鳩の画像が出てきて・・・
>>382 >後漢書の時点で大倭とあるんだから、
後漢書が書かれた5世紀の時点では、まだ九州の方に主権があったが、筑紫倭国が畿内も植民地化していたので、大倭で間違いない。
畿内が九州を逆に併呑したのは白村江の戦いをきっかけとして。
>>400 またも「筈だ」と妄想を語る無根拠ザラコク
>>224 >>いや、判らんのなら、<
>いや、簡単に判読できるだろうが<
いや、魏徴らは「邪靡堆」として記載した、という確率が非常に高い。
また、後代史家やお前や大和説者らの「勝手な自己判断に拠る書き換え」など、
そんな勝手な事を許せば、何でもありになって、
分裂幻覚妄想の・・・・の世界になってしまうから、許すわけにはいかない。
「天津狐」・・・「平安時代」と書かれたイラストが出て来たり
どうなっているんだろう、
本当にポケモンのように地方へ行ったのかな?
あの伊達郡川俣町という掲示板
奈良、平安時代?の話をしている人がいたり、
家も、むかーし、その周辺に住んでいたと言っている
あの葱の華・・・写真の家
>>228 >>こんな風に「こりゃ何でも有りなんだ」とばかりに、<
>いや、「邪摩堆」は普通にヤマトって読めるだろ<
読めない。
後代史書の北史が書き換えた「邪摩堆」なら「ヤマタイ」であり、
「ヤマト」なんて読めない。
こんな・・・・がいるから、原本通りに読んで置くことが必要になるのだ。
>「邪摩堆」はヤマイとは読めないけれど<
魏志の邪馬壹(ヤマイ)は、大野~大宰府付近の呼称であったのであり、
後漢書の邪馬臺(ヤマダイ)は、久留米~八女付近の呼称であった、というだけだ。」
>こういうところからも、魏志倭人伝の現存本の
邪馬「壹」國は邪馬「臺」國の誤りだって判断できるんだよ <
出来ない。
魏志の邪馬壹國と、後漢書の邪馬臺國は、場所も大きさも違う別物。
だから、分裂幻覚の・・・・の妄想は、許しておけば無限に広がって、
オームなどのように、あっという間に殺人や戦争を引き起こしてしまうもの。
住んでいるところは川崎市の川崎区なんだけど、
どういう事だと思う
>>402 >「一本線」を「二本線」に間違うような事は、「殆どない」し、
>「刷りの調子」なども、全く関係がないし、そんな確率は「非常に低い」。
でも、あることはザラコクでも認めてるじゃん
そして、期待値って言葉があって、文字一つあたりの確率は低くても
それが多くの文字に対してであれば、当然間違う期待値は大きくなる
例えば、一文字あたりの間違う確率が1万分の一であっても、
5万字の書物であれば、一回の書き写しで5文字間違うことになる
それに、版本は間違う確率が低いって、一生懸命言ってるけれど
いつ頃から版本になったかなんて分からないだろ?
手書きで写していた頃は、もっと普通に間違うし
魏志倭人伝しか頼るもののない九州説は、とにかく間違いはないにだって
言いたいのは分かるけれど、それは無理筋の強弁だよ
「期待値」っていうのは、統計学の用語だからな
念のため
>>404 >いや、魏徴らは「邪靡堆」として記載した、という確率が非常に高い。
いやいや、それ、なんの「根拠」もないから
そもそも、日本人なら「邪靡堆」に当たる地名なんて日本のどこにもないし、
日本語の語感としてもありえないことはすぐに判断できるだろ?
まあ、ザラコクさんは漢文が読めないだけではなく、日本語も不自由そうに
使っているから分からないのかもしれないけれどさ
>>407 >後代史書の北史が書き換えた「邪摩堆」なら「ヤマタイ」であり、
>「ヤマト」なんて読めない。
ヤマタイならヤマタイでもいいよ
それこそ、初出の魏志倭人伝が「邪馬臺」だったことの証拠にしかならないし
>>229 >>隋使が来た頃のタリシホコの都は、久留米であり、おそらく「古宮」遺跡だ。<
>それのどこが、「ヤマトと読む地名」だ? <
「ヤマト」なんて、読まない。
隋使や魏徴らは「邪靡堆」と記録記載した事になるから、
読むとすれば「ヤビタイ」だな。
>久留米は山門から遠いぞww<
「古宮」遺跡付近の600年頃の呼称は、後漢書の「邪馬臺」とも違うので、
「邪靡堆」としか残っていないことになる。
『何者にもなれない お前たち』
キュウリの画像も出てくるでしょ、
蚕を飼ったり、機織りをしていたと言っていたんだけど
>>407 >魏志の邪馬壹(ヤマイ)は、大野~大宰府付近の呼称であったのであり、
その辺にそんな地名はないって何度言えばいいんだよ
そんな地名があるなら教えてくれって言ってるのに、何一つ挙げられないじゃないか
>後漢書の邪馬臺(ヤマダイ)は、久留米~八女付近の呼称であった、というだけだ。
その辺にそんな地名はないって何度言えばいいんだよ
そんな地名があるなら教えてくれって言ってるのに、何一つ挙げられないじゃないか
ついでに言えば、普通の九州説で「邪馬壹(ヤマイ)」を主張するやつは、
ヤマイ=八女に当てるんだぞww
でも「イ」はどこから来たんですかと訊くと、たいてい答えがないww
>>407 >魏志の邪馬壹國と、後漢書の邪馬臺國は、場所も大きさも違う別物。
魏志倭人伝「邪馬壹國、女王之所都」
後漢書「大倭王居、邪馬臺國」
どちらも王都だと書いてあるね
そして、どちらも同じ倭王だし遷都したとは書いてない
同じ場所だろ?
字を間違えているだけで
>>413 >読むとすれば「ヤビタイ」だな。
そんな地名は、日本語にはないと何度言えばww
>「古宮」遺跡付近の600年頃の呼称は、後漢書の「邪馬臺」とも違うので、
>「邪靡堆」としか残っていないことになる。
王都の地名が現在に痕跡すら残っていないなんてことは、この日本ではないよ
邪靡堆もヤビタイも、日本にはない地名だ
この時点で、ザラコクのいっていることはただのザレゴト
>>231 >とうとうザラコクも筑紫に畿内の同族が進出していたことを認めるようになったな
いい傾向だ<
この男は、また何か?を、分裂幻覚妄想の曲解捏造をしたらしいなあ?。
いずれにしても、大和は、
筑紫城の倭奴國の阿毎氏から別れた別種同族の旧小国であって、
筑紫倭國の「東征毛人五十五國」の一つの国あったのであり、
東征将軍らに拠って、筑紫倭國の文化が伝えられて、模倣した、
という事になるだけだ。
>>418 九州説はよく「東征毛人五十五國」を書くけど
「西服衆夷六十六國」はどうするんだ?
九州の西に「六十六國」の入らないぞww
ついでに、水行は海か大河のみで、玄界灘、響灘に面した福岡平野あたりから
南へ水行するのは不可能
この時点で、魏志倭人伝の旅程記事は間違いがあることが確定
というか、もとから、そのまま行ったら日本のどこにも行き着かないんだから
間違いがないと言い張るやつがおかしいんだけどな
>>232 >>魏志だけでも、「丹木」や「鉛丹」が書かれており、<
>「丹木」や「鉛丹」は「丹」ではないから、「丹木」とか「鉛丹」と書かれるんだよ
この場合の丹は、「赤い」という形容詞 <
「丹」の元々の意味は、おそらく「赤い顔料」。
>>おそらく「ベンガラ」も丹であった。<
>ベンガラは「丹」ではないから、「丹土」って書かれるんだよ
意味は単なる「赤い土」<
「赤い顔料」であれば、丹。
>仙薬たる「丹=水銀朱」とはまったくの別物<
そんな物を顔料や仙薬に使っていたら、その内水銀中毒で死んでしまうよ。
天武の時代に作られた記紀。
その記述の通りなら天武は山幸彦の子孫ということになる。
天武の時代に隼人の乱が起きたのは当然といえる。
ミミ、本当に恐ろしい存在だわい。
どんなけ各地で暴れ回ったのか。
>>422 >そんな物を顔料や仙薬に使っていたら、その内水銀中毒で死んでしまうよ。
水銀朱、硫化水銀は、水に不溶だから毒性はないんだよ
どうもこの辺を理解していない人が多い
>>234
>これまでに挙げた、大陸史書での方角の間違いは
1.末慮国から伊都国 北東なのに南東 魏志倭人伝
2.対馬から壱岐 南なのに東 隋書
3.大理から安南 南東なのに東 旧唐書<
いずれも、殆どか、全くには間違いにはなっていなかったものばかり。
この男は、いずれも、曲解捏造した解釈で「間違いだ」と言っている、
分裂幻覚妄想の・・・・詐欺師。 >>422 >「丹」の元々の意味は、おそらく「赤い顔料」。
「おそらく」ってww
ザラコクのあて推量には何の意味もないって、何度言えばいいんだろうww
>「赤い顔料」であれば、丹。
意味のない推量をもとに何かを言っても、当然意味がないww
>>426 >いずれも、殆どか、全くには間違いにはなっていなかったものばかり。
その論証をすればいいのにww
言い返したつもりになっているだけで、何一つ否定できてないぞww
追加の新唐書「其「東」海嶼中 又有邪古波邪多尼三小王」も入れて4つだな
>>426 >分裂幻覚妄想の・・・・詐欺師
「ザラコク詐欺師」なんて、ひどいことを書くなぁ
このスレでは「・・・・」=「ザラコク」ww
>>235 >>大和は、筑紫倭國の「東征毛人五十五國」の一つであり、<
>じゃあさ、筑紫に倭国があったとして、 「西服衆夷六十六國」はどこに入るんだい?
筑紫の西側には、そんな土地はないぞww<
「征=征伐する」や「平=平定する」はいずれも他動詞であったが、
「服=服属する」は元来自動詞であるから、
「西の衆夷六十六國は既に服属している」という意味になり、
「六十六國」は、九州付近全域になる。
これ一つで、倭王武が九州王朝の王ではないことが丸分かりww
>>430 >「六十六國」は、九州付近全域になる。
九州の西に「六十六國」は入らないことは認めるんだな?
その時点で、倭王武は九州王朝じゃないぞww
>>430 >いずれも他動詞であったが、
>元来自動詞であるから、
漢文が読めないのに、無理をして見当違いのことを書いているのが笑える
問題はそこじゃなくて、倭王武の本拠地が、
東に55国、西に66国あるような、倭国の地理的な中心に近い所だってことだ
九州王朝ではムリポ
彦火火出見の王宮は倭国の都である伊都国の高祖宮だよ。
ミミは倭国の王族の称号で、特に彦火火出見は日向王家の伝統の名前だね。
実は神武のフルネームにも彦火火出見が入っている。
>>251 いや、史料を否定曲解する奴や、事実や史料事実の根拠を出さない大和説の奴が、
害だの。
要するに、記紀も倭人伝も、倭国の都が伊都という前提で書いているんだよ。
>>260 >ところがどっこい、倭国の都は近江→濃尾→大和だったんだよねー <
「南≠東」に拠って、×ね。
記紀に出てくる芦原中津國とか食国がどの辺りの地域を指すかだな。
>>261 >>邪馬台と書いてヤマトと読む<
>これは正しい<
正しくない。
「邪馬台」なんて存在しないし、
「邪馬壹」も「邪馬臺」も「ヤマト」とは読めない。
>倭はもともとwaとかuiaのような発音
倭人が漢字を習得して自分の国を大陸が倭國と表現しているのを知ってから
ヤマトの音を当てただけ <
いや、違う。
周初期に暢草を献じた時や、燕の南にいた頃から、
既に「倭」と呼ばれて記録されていた。
そして、列島に来てから「倭」を「ヤマト」なんて音をあてた、
てなことは全くない。
大国主とスクナヒコナが完成させたクニ、芦原中国、芦原中津國。
国津神が治める国。芦原中津國。
津ツはのという意味。
クニの神。
クナの神。
クナトの神。
邪馬台国、ヤマトの南にある狗奴国。
官は狗古智卑狗、コウチヒコ、河内彦かな。
壬申の乱で負けた難波は奈良時代は寂れていた。
古代の難波はどういう場所だったのか?
下の長唄は、なにわの地が芦原中津國や食国と認識されていたのが伺える。
それを前提に記紀を読み直すと面白い。
聖武天皇の難波行幸に従駕した笠朝臣金村(かさのあそみかなむら)の詠んだ一首
押(お)し照(て)る 難波の国は 葦垣(あしかき)の
古(ふ)りにし郷(さと)と 人皆の
思(おも)ひ息(やす)みて つれも無く ありし間(あひだ)に積麻(うみを)なす
長柄(ながら)の宮に 真木柱(まきばしら) 太高(ふとたか)敷きて 食国(をすくに)を 治めたまへば 沖つ鳥
味経(あぢふ)の原に もののふの 八十伴(やそとも)の緒(を)は 廬(いほり)して 都(みやこ)なしたり 旅にはあれども
>>263 >倭は、倭人が住む範囲だよ そこで成立した国が倭國
北部九州も倭の範囲内で倭國の一員<
いや、やはり少し違う。
当初倭人は、海峡海峡両岸~九州北半分に渡来して来ていて、
南の東テイ人や侏儒國人や、在地であった毛人(猿田彦や出雲や越や蝦夷)とは区別されており、
しかし、倭人の天孫族らの東征で、出雲や瀬戸内~近畿東海が倭人と共存状態になっていて、
卑弥呼の頃には、それらの共存人が「倭種」と呼ばれたらしい。
>>264 >奴国が女王国の傍国に上げられているからね。 女王国の傍にある国。
傍の字義通りなら、奴国は女王国に含まれない。<
これも少しダメ。
女王國とは、一応共立に同意した諸国全部である事になり、
倭国内で賛成しなかったらしい国としては、狗奴國の名前しか挙げられておらず、
だから、その他の29国は、共立に賛成する度合いには強弱があったとしても、
一応賛成派であった事になり、
だから二つの奴國はどちらも共立賛成派国。
そして、女王國と東方の倭種は、確実に書き分けられているから、
東方の倭種は、一応女王共立国にも倭國にも入らず、
倭国の半独立国的な附庸國であった事になる。
>>270 >なぜ奈良に3Cの巨大古墳が???? → 邪馬台国があったから。<
「邪馬台国」なんて存在していないし、
奈良の巨大古墳は、
石塚から(勿論箸墓も)、
既に那珂八幡などの筑紫の前方後円墳の模倣になっているんだから、
3世紀末以後になり、
倭国の「東征毛人五十五國」のお手伝いでのおこぼれで、巨大古墳を造れた、
という事になる。
>>270 >なぜ沼津に3Cの巨大古墳が???? → 狗奴国があったから。<
「南≠東」に拠って、×。
>>279 >>現唐津駅付近からでも、出発方向は、「東南」になる。<
>現唐津駅付近から、虹の松原はほぼ真東<
現唐津駅付近の海岸線も、北西→南東方向。
もしかして、
本当に嘘の系図などを作成しているのかな、
何かの本物と思われる家の人は何をしているの?
学校も行っていないし、
仕事もしていないと言っている人がいたような気がするんだけど
仕方なく、捏造?のような事をしているのかな、
断絶、絶家とか
>>283 >あるけど? テンプレにも詳しく書かれてる <
テンプレなんて、長過ぎて、読めたものではない。
どうしても言いたいんなら、該当部分を示すなり、
転写して。
数年前の、とあるスレ、本人の書き込みではないと思うんだけどw
「僕が虐められるわけがない」
このような謎の書き込みがあったり、その人物に向けての書き込みだと思う、
本人が、スレを観ている事を知っていて、誰かが、そういう書き込みなどをしていた
>>284
>>倭人が住む地域の中で、女王に従っているのが倭国、九州北部。
それ以外の地域は中国に接触していない。<
>畿内はどうなの? @阿波<
畿内なんて、存在しないよ。
そして、近畿も倭種か、東征支配の旧小国になるから、
中国との接触があったとしても、筑紫倭國を介しての、「間接的」。 >>285 こういう、「口先言葉尻での誹謗」の根拠なき言い張りオンリーが、大和説だな。
>>287 >「水行歴韓國乍南乍東」と書いてあるな。<
幾ら都合の悪い「循海岸」を隠して「水行歴韓國乍南乍東」として誤魔化しても、
普通の「水行」では、「歴韓國乍南乍東」が全く出来ないし、ならないし、
里数も全く合わないから、
×だよ。
何か、おかしいんだよな
数年前の△メーソンというスレ
川崎が良くならないと日本は・・・良くならない、
このような事を言っている人がいたり、
家も川崎に住んでいるんだけど
>>288 「南→東」などの嘘つき騙しのトンデモの大和説は、
都合の悪い史料事実を無視してばかりだね 。
>>292 致命的な指摘を食らって なにも証拠のない言い訳しかできない大和説って、
もう 風の前の塵じゃ ありませんか ?。
それと日本昔話 姥清水
十▢の歳に神隠し?にあわされ、
あれは現代の話じゃないの?
姥清水というのは福島県(出身。または関係者。)の話で、
1990年代に制作された?
1990年頃に神隠し(不明)にあわされた・・・?
>>301 >>我國は太古から連綿と連なる世界唯一にして萬葉一統の国家なのであります<
日本は、太古の昔から、ネアンデルタールや、南洋や大陸からの、
「いろんな沢山の遺伝子能力」を持った流民たちが流れてきて、
共存協調混血して、いろんな工夫をして、
高い文化や文明を持てた幸福な国であったのですが、
一部の(精神病的なタカ派の高慢で強欲な)暴力団のような人種が、
支配者になって、国民を戦争に引っ張り出して死なせて、
自分らは栄耀栄華をは貪ろう、として、
国民を不幸にしよう、としているのです。
>>306 史料事実などでの反論が出来ず、
そういう口先言葉尻に対する誹謗中傷しか出来ない事実が、
大和説の惨敗を証明している。
姥清水に出てくる母親
「神も仏もない」と言っていたり、どういう事なんだろう
老婆の話によると
むかーし寺院に通っていた。
いまの福島県、伊達郡・・・川俣町のほう。
>>307 >>「壱岐〜筑紫」は、「東」とは書かれていない<
>「經都斯麻國迥在大海中 又「東」至一支國又至竹斯國」
東に向かうと壱岐、それから筑紫に至るんだよ そのまま東に進んでる<
いや「東」が書かれていないから、「そのまま東」にはは進んでいない。
>「竹島から東で壱岐が正しい」と言い張るなら、どうしてそこから筑紫への
「方向転換が書いてない」んだ?<
「東南」方向になって、「東」にはならなかったから、「東」を外した。
じゃ、なんで東南と書かないの?
言ってることが支離滅裂だ
>>308 >んなこと聞いてねえ。<
この投稿子のような、
中国人差別のように見える極右の・・・・なんかと議論など、
全く時間の無駄になるだけだから、
する気もしない。
私は、世間の人々に「私の判断」を説明しようとしているつもり。
>で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と中粒種のイネは?<
もう答えて上げたし、それ以上の事はもう知らんし覚えてないし、
探して思い出して上げる気もしない。
雲太、和ニ、京三
仮説だが、
邪馬台国女王国、初期の大和朝廷は、雲太と和ニの国かもしれない。
>>468 まともなことは解答不能で、ただ独断を言い張るだけなんだね
>>468 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の氏名と所属団体は?
早く言えよおまえ。
宮都一覧

>>340 >>50里以下位の「国内移動」は、記録されていない、<
>おいおい、自分が短里を主張してるってこと忘れてないか?
「九州説のいう短里」はだいたいが70メートルくらいだろ? 50里って3.5キロだぞ?
狭すぎるとは思わないのかい?
それ以下の国内移動しかないって主張するのって、意味がないと思わないのかい?<
思わない。
唐津港~唐津駅位でも3.5km位になるようだし、
吉野ヶ里ですら、長径が2km位あったように見えたし。
>>344 >>出発と到着の間に、途中の移動などの説明があったのか?、<
>いや、途中の移動の説明なんて、倭人伝のどの国の記述にもないだろう
あると言い張っているのはザラコクだけで <
對海國と一大國と末盧國にある。
>>345 途中の移動などの説明がない、
と叫ぶ理由がまるで無いので、
この大和説投稿子も、独善幻覚の妄想の×人間。
森友ノロウイルス焼肉スイッチ押死テ昔カラ戦争シテルンデシタッケ忘レテマ死多世モヤシテ殺ッテマス100麻薬王薬害盗難ケタチガイ違反重々振戦
http://2chb.net/r/welfare/1443184621/ >>351 >「もなく」って、何がないの?
畿内説の者が、そんなことをしたって証拠は?<
「畿内」なんて文言も存在しないの。
>またも只のデッチ上げ中傷かな? <
また、中国人批判らしい変な・・・・男と同じように、
でっち上げの貼り付け中傷なのかな?。
台与の息子

>>477 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよおまえ。
>>382 >卑弥呼の頃には、ヤマト=畿内王権が北部九州まで範囲で祭祀を統一して
畿内説って、全く根拠のない妄想を書き殴るだけだよな。
>>360 >>南與越州相接<
>ってことは、倭國はベトナムと接するほど南にあるって唐会要でも
考えられてたってことだよな <
いや、唐会要は、「北限大海、西北接百濟、正北抵新羅」というように、
大海を隔てて離れた百済に対しても「接」を使い、
新羅に対しては「抵」を使って区別しているので、
「接」を仲が良い関係に使い、「抵」を関係が敵対的である場合に使って、使い分けているので、
越州の場合の「接」も、地理的に接しているのではなく、
関係が仲良しである、という意味で使っている事になる。
纒向の祭祀系の遺物を見ると諏訪大社と似ている気がするんだな。卑弥呼の鬼道。
今の神道、烏帽子、鳥の格好で舞う、鐸を鳴らすのとは少し趣きが違う気がする。
魏志倭人伝の邪馬台国までの里程
帯方郡(朝鮮北部)から狗邪韓国まで七千里、女王国まで一万二千里。
対馬海峡が三千里であり、帯方郡から九州上陸までで一万里となるので、邪馬台国の位置は九州北部になる。
魏志倭人伝の邪馬台国までの日程
帯方郡から邪馬台国まで水行10日、陸行1月(1日の誤りか)
ちなみに帯方郡から投馬国(宮崎都万)まで水行20日
後漢書における里程
大倭王は邪馬台国にいる。
楽浪郡の国境は、その国(邪馬台国)から一万二千里である。
倭国の西北界である狗邪韓國からは七千里である。
倭奴国は倭国の極南界である。
魏略逸文における里程
帯方(郡)より女(王)国に至る万二千余里。
邪馬台国時代の遺物の出土状況

>>445 だから、天皇家も筑紫の日向、伊都国にいた倭王の末裔。
その証拠は、伊都国の王墓から発掘された皇位の象徴である八咫の鏡。
天皇家は紀元前のクニトコタチと血のつながりがある
直系ではないけど
女系、傍系も含めれば血はつながっている
いきなり何の関係も無い人物が天皇になる事は無い
直系は記紀と違い何度も途切れたが、必ず傍系でつながっている人間が皇位を継承している
自称保守は、この傍系や女系を否定するから話が回りくどくなる
>>455 >幾ら都合の悪い「循海岸」を隠して「水行歴韓國乍南乍東」として誤魔化しても、
>普通の「水行」では、「歴韓國乍南乍東」が全く出来ないし、ならないし、
>里数も全く合わないから、
おいおい、ザラコクが勝手に「陸行」にしてるから
「水行」と書いてあるね、って教えてくれただけだろうが
「南→東」よりも、「水行」と書いてあるのに「陸行」と謎解釈する方が
修正の程度として酷いぞ
まあ、儒教道徳では間違いを認められないんだろ
そういうところが日本人と価値観が違うよな
>>490 記紀も王統の入れ替わりは記載しているのだけどね。
応神はなんだか必死に隠しているけど。
>>492 記紀ができたのは天武の時代だからな。
応神は天武にとってかなり都合の悪い血だったんだろう。
応神が生まれて喜ぶのはスクナヒコナ、天武派にとってギリギリの表現だったんじゃないかな。
魏志倭人伝
邪馬台国の官
官は伊支馬有り。次は弥馬升と曰う。次は弥馬獲支と曰う。次は奴佳鞮。
伊支馬は生駒。生馬。火の神。
弥馬升は三見宿禰、出雲醜大臣の子。
弥馬獲支はミミ鷲、日鷲。
奴佳鞮は中臣。
邪馬台国の官は、大和朝廷の官と瓜二つ。
出雲地方には生馬神が祀られているんだな。
生馬神社境内には「牛荒神の大木」と呼ばれる木があり木に藁が巻き付けられている。
出雲風土記かな、生馬神の子は、もう荒ぶらないと言ったとか。
ヤマトの地名と出雲の集落名、共通点が多い。
邪馬台国の官の筆頭
伊支馬。これがどういう勢力か解明できれば、邪馬台国卑弥呼に近付ける気がする。
伊支馬、生駒、生馬、伊熊、猪熊などの地名が、ヤマト、出雲、三河、遠賀川に見られる。
何か関係あるのか?
伊支馬の正体が超重要、記紀でも省かれている。
纒向の外来系土器で一番多いのは、尾張三河東海系。
これが邪馬台国初期の大和朝廷の中心じゃないかな。
伊支馬は尾張のトップな気がするんだな。
私の大好きな「おもしろそう紀」住吉十楽では、
隠されているのは五百城入彦皇子の即位だって書いてあった
応神はイザナギ系だろうが、尾張系はカグツチ系で根本的に別勢力のように思える。
尾張一宮、元々主祭神は国常立神だったのに、なぜ火明命に変えたのか?
東海は秋葉権現、火の神、が多いのは元々火の信仰があったのでは?
東海の焼畑遺跡の分布が気になる。
神武東征ヤマト征伐に関する、タケミカヅチ、フツヌシ。誕生のエピソードはカグツチ由来。
邪馬台国女王国初期の大和朝廷は、カグツチに関する勢力の政権の可能性が高い。
イザナギへの復讐で結びついた勢力とも言えるのではないかな。
根本的に応神以降と応神より前の勢力は別物かもしれない。
>>501 ただ、豪族層は応神前後で変化はないんだよな
その意味でヤマトの朝廷はそのまま存続している
継体天皇の時も豪族は変わらないんだけれど
継体の時は、先代と10親等離れて相続していることが記載されている。
仮に応神が仲哀の子ではなく武内宿禰の子でも、武内宿禰が孝元の孫とされているので、10親等の相続になるが、記紀はそれを認めていない。
ではなぜ神功応神が特別扱いなのか。
もう一つの理由があるのではないか。
例えば、神功が応神の実子を暗殺していること。
例えば、武内が孝元の孫ですらない可能性。
そしてもう一つが、この時に王朝全体の交代があった可能性。
神功は田湯津姫、羽白熊鷲という敵を倒している。
田湯津姫は神夏磯姫の末裔(孫?)と伝えられている。
神夏磯姫は、筑紫の梟師という称号を持ち、八咫の鏡を含む三種の神器を保有し、景行天皇と共闘している。
つまり、卑弥呼以来の筑紫倭国の女系王朝が田湯津姫の時に滅亡して、応神朝が成立したのではないか。
景行は九州征伐以来、筑紫倭国の外戚であったが、そのさらに遠戚である武内が筑紫倭国の宗家を滅ぼしたのなら、筑紫倭国にとっては田湯津姫と武内など、想像もつかないくらいの遠い関係となってしまう。
神功と武内は、卑弥呼王統と景行王統(タラシ朝)の両方を滅ぼして応神朝につなげたのでろう。
>>494 南九州以外の西日本だから中途半端だろ
ホアカリは徐福の海部名
ニギハヤヒ(饒速日)は徐福の物部名
徐福は、出雲王家の女性をふたり妻にして、
その子がイソタケ(五十猛)とホオテミ(火火出見)
イソタケの子のアメノムラクモ(天村雲)が
初代ヤマト王になった
(中略)
689 己丑 飛鳥浄御原令施行
法令の上で「日本」という国号、
「天皇」という地位・称号が公式に設定された
建国は689年
670 庚午 新羅を訪問した安曇連頬垂
(アヅミノムラジツラタリ)が「日本國」を名乗った
羽白熊鷲は当時の筑紫倭国の有力者だが、実名ではないだろう。
熊と鷲が部族のトーテムだとすると、熊は筑紫倭国の中の肥国王家(国津神)、鷲は筑紫王家(天津神)であり、双方の後継者であった可能性がある。
田湯津姫ももちろん同じ家系だが、決戦の地が有明海沿岸であったことを考慮すると肥国王家に近かったのだろう。
筑紫倭国と便宜的に読んでいるが、実際は肥国王家が女王を輩出していた。
神功を支持したのは、筑紫王家の伊都高祖宮(怡土県主)と豊国王家の岡田宮(崗県主)である。
後醍醐天皇の側近だった北畠親房の書いた『神皇正統記』の
【異朝の一書の中に日本は呉の太伯が後也といへり。返すがえすもあたらぬことなり。
『昔日本は三韓と同種なり』と云事のありし、かの書をば桓武の御代に 焼きすてられしなり。
天地開て後、すさのをのみこと韓の地にいたり給きなど云事あれば、彼等の国々も神の苗裔ならん事あながちにくるしみなきにや。それすらも昔よりもちゐざることなり。
天地神の御すゑなれば、なにしか代くだれる呉太伯が後にあるべき。】
平安時代に『昔日本は三韓と同種なり』と書いた本があり、桓武天皇が焼き捨てたと言うのだ。
書いた人間は天皇を神と崇める北畠親房だ。
それに加えて風土記が紛失したからという理由で各地方に再提出させたという記録もある。
松本清張は日本書紀の内容に合わせて風土記を書き直させたのだろうと言っている。
この時代に大規模な歴史改竄が行われたのではないか?
風土記にも『三韓と同種』を疑わせる記述が複数あったのではないか?
そこでその風土記を燃やして都合の悪い部分を書き直させて提出させた。
そして、焚書の件が桓武紀ではなく『応神紀』に記載されていた事を考えると、応神天皇が三韓の子孫であると書かれ
ていたと考えるのが正しいだろう。
旧唐書日本伝
日本国は倭国の別種である。
その国は日の昇る方にあるので、「日本」という名前をつけている。
あるいは「倭国がみずからその名前が優雅でないのを嫌がって、改めて日本とつけた。」ともいう。
またあるいは「日本は古くは小国だったが、倭国の地を併合した。」とも。
日本は古くは小国ってのは日向族だな
東征記以外で南九州の伝承がまるでないのは全く倭国とは無関係だったんだろう
ヤマトタケルの熊襲征伐が出てくるぐらいで、薩摩隼人は異族ながらも大和とは親和性が高いポジションだった
東征をした豪族は北九州からたくさんいて、日向族は行幸だったというね
記紀はこれを統合して、神武東征などと勇猛な話に仕上げたわけだ
>>360 >そして、唐会要の引用だろうがなんだろうが、新唐書の 其「東」海嶼中の
「東」が「南」の間違いであることにはなんの変わりもない<
勿論、唐会要の後代史書である新唐書である新唐書も、実地の確認もせずに、
前代史書記載に関する「自己解釈に拠る内容説明的書き変え」をやってしまって、
失敗引用になってしまう事はあるさ。
そして要は、そのような「実地確認のない伝聞的な引用や書き換え情報」には、
方向を間違える場合もあり得る、という事だな。
>>365 >筑紫倭国が植民地を拡大したので大倭と呼ばれるようになった。<
古事記の「大倭」は、欠史八代の中の4人にも冠せられているから、
当然の、魏志の、「倭國の地方の市を監督」する「大倭」職」であった事を示すもの。
後漢書の「大倭王」や「倭国大乱」の「大」は、
本来は「天子に関わる事象」を示す文言であったものを、
范曄が、自己に特有な「誇大的な表現」使用によるもの。
>ヤマトに大和を当てたのは、ヤマトが筑紫倭国を併合して大倭の支配権を得たから。<
それが、白村江の後の「大和が倭国を併合吸収継承した」時に起こった。
>>370 >畿内説は学界で通説ですが、何か?<
学会は、「畿内」という存在もしなかった文言を使う嘘つき騙しの「会」であり、
「南→東」という史料事実の否定曲解をする嘘つき騙しのインチキの「会」ですが、
何か?。
>>378 >前スレの950にきちんと書いてあるだろうが
「牟尋は南詔国の第三代国王の異牟尋 都を太和城から北方の陽苴咩城に遷都した
陽苴咩城は今の大理 」
太和城は前都で、今も大理市内に遺跡があるよ
陽苴咩城が、今の大理故城よりも北の位置で、大理市外からは外れる<
また、何か?変な事を言ってるな?。
「太和城は前都で、今も大理市内に遺跡がある」では、(陽苴咩城=大理ではなく)
太和城=大理だという事になってしまうではないか。
>>大理ー安南は、相当な山越えであり、<
>ソンホン川の源流沿いに行けば、川の水が下るように、ずっと下り坂で
山越えなんてないぞ 地図を見ろって言ってるだろうが!<
大理から直接東南へ行けば、地図では、猫頭山?とかの相当な山塊が続いており、
ソンホン川の源流に達するのも困難なようだ。
>>南寧方面を経由する
>「南寧」ってどこだよ! そんな地名はないぞ!
地名まで捏造するって、どこまで追い詰められてるんだよww<
地図では、昆明から南シナ海へ抜ける途上の町だ。
>>372 >ズビニ鉤虫があった縄文人の「太平洋横断の往復渡航」の証拠になるから、<
>ならないんだよww
論理の分からない人には理解できないかもしれないが、それが成り立つためには
当時、縄文人以外がズビニ鉤虫を持っていないことを論証しないといけない <
南米にズビニ鉤虫は存在するには、
旧大陸のどこかから人間が運び込まなくてはならず、
北米には見つからないのであれば、シベリア→アラスカやグリーンランド経由が否定され、
アフリカ→南米も困難であるから、
結局、日本付近や南洋諸島から太平洋を横断するしかなくなってくる。
>そして、ズビニ鉤虫の蔓延地の広さから、それを言うのは無理 <
大西洋横断の痕跡がなければ、太平洋横断。
>>381 >日本という国号を作った政権が編纂した史書だから日本という表記を使ってるんだぞ<
筑紫倭国も「日本」と名乗っていたんだし、
百済本記には「日本国天皇・・・」の記録もあったんだし、
書紀には?、「任那日本府」?の記載もし、
しかし、孝徳紀などでは、地方の地名としての「倭國」の記載も残っているし、
「倭京」なんて表記もある。
>古事記のもととなった国記が推古朝に作られ、その時(というかその前からずっと)
倭国の代表は「現在の奈良盆地に中枢を持つ現皇統につながる王権」で
その王権の人物である天武・持統朝に、日本という国号をその王権自ら作った
それだけのことだよ<
古事記の建前も始めから、
筑紫倭国や卑弥呼や倭の五王などの存在などの否定や、歴史の抹殺であり、
半分×史書。
そして、大王位に関わりのないところでは、倭(やまと)の表記も残っている
「爲椎根津彥(椎此云辭毗)此卽倭直部始祖也」とかな
>>381 >日本という国号を作った政権が編纂した史書だから日本という表記を使ってるんだぞ<
筑紫倭国も「日本」と名乗っていたんだし、
百済本記には「日本国天皇・・・」の記録もあったんだし、
書紀には?、「任那日本府」?の記載もし、
しかし、孝徳紀などでは、地方の地名としての「倭國」の記載も残っているし、
「倭京」なんて表記もある。
>古事記のもととなった国記が推古朝に作られ、その時(というかその前からずっと)
倭国の代表は「現在の奈良盆地に中枢を持つ現皇統につながる王権」で
その王権の人物である天武・持統朝に、日本という国号をその王権自ら作った
それだけのことだよ<
古事記の建前も始めから、
筑紫倭国や卑弥呼や倭の五王などの存在などの否定や、歴史の抹殺であり、
半分×史書。
そして、大王位に関わりのないところでは、倭(やまと)の表記も残っている
「爲椎根津彥(椎此云辭毗)此卽倭直部始祖也」とかな
>>521 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
早く言えよおまえ。
>>521 >筑紫倭国も「日本」と名乗っていたんだし、
また結論先にありき・・・かぁ
>>518 >大理から直接東南へ行けば、地図では、猫頭山?とかの相当な山塊が続いており、
>ソンホン川の源流に達するのも困難なようだ。
?
ソンホン川の源流は大理市内ですけど?
???
大理古城より成都城市之心まで
方角は北から33度49分
正北東45度よりだいぶ北寄りで、これを東と強弁するのは無理すぎる
大理古城よりハノイ昇竜皇城遺跡まで
方角130度35分
正東南135度より僅かに東寄り
東南と呼ぶのにふさわしい方位
縄文時代の九州人が太平洋横断して南米に土器を持ち込んだというのは
南米の先住民が土器文様を生み出すはずがない
という蔑視と単一史観が基礎にある
なんでズビニ鉤虫なんかの話してんの?
九州に多い HTLV-1ウイルスが南米にも存在して、
しかも遺伝子型が共通しているという話じゃなかったっけ?
九州縄文土器の発展途中のと同じ様式の土器
同じ遺伝子型のHTLV-1ウイルス
が南米エクアドルに存在するから、
破局噴火で海に逃げた九州縄文人がエクアドルまで辿り着いた、
という論調だったと思うが。
逃げたんじゃなくて漂流したんだろ。
奇跡的に生きたまま漂着したんだよ。
鬼界カルデラというのは鹿児島の南にあるから
くまもつ県民は北に逃げたほうがいい
>>518 >また、何か?変な事を言ってるな?。
>「太和城は前都で、今も大理市内に遺跡がある」では、(陽苴?城=大理ではなく)
>太和城=大理だという事になってしまうではないか。
地図一つ見ないやつが何を言ってもムダ
「南去太和城十餘里」
唐里で10里しか離れてないんだよ
たった5キロちょいの距離
今の大理市の大きさの中に入ってしまうんだよ
バルディビア土器の話題を出したのは九州説なんじゃないの?
>>521 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよおまえ。
南米の人類の歴史はまだよく解明されていない
ブラジル北東部のセラ・ダ・カピバラ遺跡では
6万年前に遡る3万点の線刻岩絵群と洞窟壁画が見つかっている
最後の氷河期以前に絶滅した動物などが描かれている
壁画には、世界で最古の船も描かれている
>>518 >地図では、昆明から南シナ海へ抜ける途上の町だ。
やっと見つけたよ、南寧
でも昆明から安南に向かうのに、南寧を通ることはないし、
最初から史書に出て来ない地名を持ち出すってことは、
この件に関してはもうインチキをしないと反論一つできないってことだな
そして昆明から、安南に向かうにしても南寧に向かうにしても、
まず紅河ハニ族イ族自治 に向かうことになる
この方角を計ると 方角 : 156.424° で八方位だと南だな
旧唐書に南寧は邕州として記載されている
舊唐書/志 凡三十卷/卷四十一 志第二十一/地理四/十道郡國 四/
嶺南道/邕管十州/邕州下都督府
邕州下都督府 隋鬱林郡之宣化縣。武德四年,置南晉州,領宣化一縣。貞觀六年,改為邕州都督府。
天寶元年,改為朗寧郡。乾元元年,復為邕州。上元後,置經略使,領邕、貴、黨、橫等州。後又罷。
長慶二年六月,復置經略使,以刺史領之。刺史充經略使,管戍兵一千七百人,衣糧稅本管自給。
舊領縣五,戶八千二百二十五。天寶後,戶二千八百九十三,口七千三百二。
至京師五千六百里,至東都五千三百二十七里。東南至欽州三百五十里,東北至賓州二百五十里,
西南至羈縻左州五百里。
安南は欠片も出て来ないぞ
南寧経由の安南行きなんてのは想定されていない
そもそも大理ー安南の記述は大理(陽苴?城)の位置を示す記述で、
直線方向と距離で示しているのだから、昆明すら関係ない
>>519 >大西洋横断の痕跡がなければ、太平洋横断。
順序が逆
ズビニ鉤虫がいたから、それが太平洋横断の痕跡とされているのであって、
大西洋横断の痕跡としても何の問題もない
南米諸族がグレートジャーニーの結果のモンゴロイド系なこともあって、
アジア太平洋側とのつながりが想定しやすいってのもあるだろう
この辺は、太平洋の海洋民族の航海能力は想定以上に高かった可能性を示唆するだけで
「そんなこともあったかもしれないね」程度のこと
これを、魏志倭人伝に書かれている侏儒國、裸國、黒齒國が南米のことだとか、
トンデモを言い出すやつがいるからおかしな話になるんだよ
>>527 >九州に多い HTLV-1ウイルスが南米にも存在して、
>しかも遺伝子型が共通しているという話じゃなかったっけ?
HTLV-1は母子感染が主で、グレートジャーニーで説明できるから、
低温域を通過できないズビニ鉤虫の方が九州説のお気に入りらしいよ
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm1952/46/6/46_6_908/_article/-char/ja/ 現代なら母子感染かもしれんが
古代なら入れ墨感染じゃないの?
胎生期の感染も否定できないし、産道感染もある
母乳感染も込みで、母子感染としたんだが、
歴史板なんだしそこまで厳密じゃなくても許してくれ
>>518 >大理から直接東南へ行けば、地図では、猫頭山?とかの相当な山塊が続いており
せっかく地図を見たなら、きちんと見なよ
ソンホン川の源流は大理市内にあって、猫頭山の西側を南に近い南東方向に流れ下るんだよ
HTLV-1は性行為感染症の側面もあるけれど、ほぼ男性から女性の一方方向で、
感染確率は高くない
>>544 盆地はどこ行くにも峠越えがあって当然だよね
それより、最初は出発方向だというのがウソと判明したのは大きいかな
大理は洱海の西岸だからね
>>381 >日本という国号を作った政権が編纂した史書だから日本という表記を使ってるんだぞ><
何を言いたいんだい?。
筑紫倭國は、晋の惠帝に日本国を名乗り、
ヤマトは、開皇末に、小野妹子が隋の文帝に日本国を名乗って叱られ、
唐の武徳中になって、唐に日本国を承認して貰い、
その後は、日本国を名乗ったのが倭国と大和の二つあった時代が続いたんだよ。
>そして、大王位に関わりのないところでは、倭(やまと)の表記も残っている
「爲椎根津彥(椎此云辭毗)此卽倭直部始祖也」とかな <
書紀の孝徳紀付近には、いくつか「倭」という文字が使われているんだよ。
>古事記のもととなった国記が推古朝に作られ、その時(というかその前からずっと)
倭国の代表は「現在の奈良盆地に中枢を持つ現皇統につながる王権」で
その王権の人物である天武・持統朝に、日本という国号をその王権自ら作った
それだけのことだよ <
大和は、筑紫城の倭奴國の阿毎氏から別れた別種の旧小国であったんだから、×。
>日本書紀程度の漢文さえ読めないんだなww
廼生大日本 「日本、此云耶麻騰。下皆效此」 って書いてあるだろうが
大日本の「日本」を「耶麻騰=ヤマト」と読むんだから、その前に大が付いてるだろ?
大日本=大ヤマトっていう関係だぞ?
漢文読めなくても、文字だけ追えば分かるだろうに <
倭国の存在や歴史を抹殺盗用造作しようとした半分×書の書紀の記載は信用出来ないし、
「倭」や「日本」を「ヤマト」なんて読ませるのは、インチキそのものだよ。
>>382 >後漢書の時点で大倭とあるんだから、<
後漢書の「大倭」は、半分×人間の范曄の「誇大」表現であり、根拠にならず、
大和の「大倭」は、倭国の地方の市を監督する「大倭」職の事。
>卑弥呼の頃には、ヤマト=畿内王権が北部九州まで範囲で祭祀を統一して
倭国の代表になっていた訳だ 何も問題ないじゃん <
「南≠東」だから×。
はいはい、ザラコクさんは自分の間違いを認められなくて、延々と
妄想を書き散らすだけの人ってはっきりしたので、あとはどこか
相手をしてくれる人を探してどっかにいってくださいな
しばらく前にニュー速に誘われてたじゃない
のぞいてきたら?
>>549 >「南≠東」だから×。
はいはい、自分の間違いが認められない人は惨めですね
何度も、そんなのは通用しないと突きつけられて
でも、自分のスタイルを曲げられない、惨めで悲しいザラコクさん
論理学的にはっきりと「偽」であることを示されても
儒教道徳的に自分の間違いを認められずに、思いつきの
その場しのぎを書き続けるしかない
論証抜きの「南≠東」はどこへ行っても通用しませんよ
>>548 ザラコクが信用しないなら
正しいことなんだよ
記紀なんて神代は出雲と筑紫と高天原ばかりじゃねえか。
大和なんて神武が到着してようやく登場だ。
>>556 それ、大和がヤマトであることと、なんか関係があるの?
>>383
>>(縄文土器)何故同じような形態の土器が造られたのか?、という事が問題<
>土器を作るときに、誰でも思いつくような文様が一致しているってだけだぞ
画像検索してみてみなよ<
模様には、いくつか種類があり
無文(むもん) :模様がない
隆起線文(りゅうきせんもん):細く盛り上がった線の模様
爪形文(つめがたもん) :爪で付けた模様
などがありました。 >>561
>無文(むもん) :模様がない
無紋土器が文様の一致に数えられてもなぁ バルディビア土器は九州の縄文時代の土器とは違う文様もたくさんある
そして器形がまったく違う
さて、大陸の史書(正史)における地理・旅程記事での「水行」が、
基本的に「海」の移動で、ガンジス川とソンホン川の二つの大河では、
例外的に「川の水行」が記されており、「小さな川の水行」がないことを
示していこうかな
律令制は全ての土地と人民は天皇に帰属するという制度だから
異人の土地を統治する正当性が必要だからな
まず、史記に出てくる「水行」は10件
陸行乘車,水行乘船,泥行乘橇 が3件
孟賁水行不避蛟龍,陸行不避兕虎 が2件
「陸行乘車,水行乘船,泥行乘橇」は、禹の治水の活躍を述べた部分で、
陸、水、泥、山を行くときのことを書いてあって、地理、旅程記事とは無関係
「孟賁水行不避蛟龍,陸行不避兕虎」は、孟賁(人名)が水を行くときは
蛟龍を避けず、陸を行くときは虎兕を避けず
孟賁の勇猛さを述べる文章で地理、旅程記事とは無関係
史記の「水行」の残り5件は
帝曰:「毋若丹朱傲,維慢游是好,毋水行舟,朋淫于家,用絕其世。予不能順是。」
[一五]【集解】鄭玄曰:「均,讀曰沿。沿,順水行也。」
[二]【集解】文穎曰:「共工,主水官也。少昊氏衰,秉政作虐,故顓頊伐之。本主水官,因為水行也。」
以處草莽,跋涉山林[五]【集解】服虔曰:「草行曰跋,水行曰涉。」
不用手足,雷電將之;風雨送之,流水行之。
>>384 >>ズビニ鉤虫が摂氏21度以下で生存できない<
>中米にもアフリカにもズビニ鉤虫の蔓延地があるんだから、わざわざ太平洋を
渡るルートに限定する必要はどこにもないだろ?<
中米のがどんな種類の鉤虫であったのか?が問題であるし、
アフリカ→中米の伝播を想定擦るなら、航海が可能か?の確認が必要。
太平洋には、倭人伝や海賦の記録があるし、
南洋島嶼の縄文土器や、長距離カヌー漁の能力がある。
最初の「毋水行舟」は、「水なき(毋)に船を行かしむ」で、
人に無理なことを強いる表現
次の3つが後世の注記で、史記の頃の言葉遣いじゃない
最後のは、「風雨はこれを送り、流水はこれを行く」で、
人の水行ではなく流水が主語の行く
史記には、地理、旅程記事で、「水行」の語を使っていない
南米より古いズビニ鉤虫卵は九州のどの縄文遺跡で検出されてるの?
後漢書の「水行」は6件
本主水官,因為水行也。
河水行塞外,東北入塞內
陸行載車,水行乘舟,泥行乘毳
師古曰:「此一害也。罷讀曰疲。」水行地上,湊潤上徹
轉粟西鄉,陸行不絕,水行滿河
水行不避蛟龍,陸行不避犲狼
後漢書6件のうち
本主水官,因為水行也。
陸行載車,水行乘舟,泥行乘毳
水行不避蛟龍,陸行不避犲狼
の3つは、史記を写したもの
残り3件は
河水行塞外,東北入塞內
河水は、黄河の流れのこと 地理・旅程記事ではない
師古曰:「此一害也。罷讀曰疲。」水行地上,湊潤上徹
この水行も、洪水の水が地上を行くという表現 地理・旅程記事ではない
轉粟西鄉,陸行不絕,水行滿河
陸を行く(者は)絶えずして、水を行く(者は)川に満つ
荷物を運ぶ人が、多い様の表現 地理・旅程記事ではない
三国志以前の史書には、地理旅程記事で「水行」の語を使った例はないことが分かる
地理・旅程記事で、「水行」「陸行」の語を使うのは、三国志の発明
>>568 >太平洋には、倭人伝や海賦の記録があるし、
それがあてにならないっていってるんだよ
倭人伝のは、淮南子や山海経からの転記だし
バヌアツの縄文土器片はK大がパリ人類博物館にプレゼントしたものだろ
>>386 >安南は今のハノイだ!
そして、現在でも中国との内陸貿易は、ソンホン側沿いの経路で行われている<
大理の南東には、最高峰が猫頭山(Maotou Shan=3,306m)の無量山脈があるらしい。
>>575 >大理の南東には、最高峰が猫頭山(Maotou Shan=3,306m)の無量山脈があるらしい。
万策尽きたかい?
大理から安南の経路は、どうやっても南東なんだよ
つまり、「東」至安南の記述は、方角の間違い
旧唐書は、×書にできないから諦めな
>>544の間違い訂正
ごめんなさい、この部分、一箇所間違い
「ソンホン川の源流は大理市内にあって、猫頭山の「西」側を南に近い南東方向に流れ下るんだよ」
正しくは
「ソンホン川の源流は大理市内にあって、猫頭山の「東」側を南に近い南東方向に流れ下るんだよ」
ザラコクは、猫頭山を大理の南東って言ってるけど、八方位で言えばむしろ南だよな
その東側をソンホン川の源流は、南東の安南(ハノイ)に向かって流れていくんだよ
>>388 >>「距離なら里数を記載」する筈であるから、×。<
>距離の記載がなければ、地理・旅程記事にならないんだよ
そして、里数に限らず、日数で書いたり、同じ距離を示したりしてあるところもある<
位置説明で、「方向」だけの場合がある。
例えば、唐会要の、
「西北接百濟、正北抵新羅、南與越州相接」。
わるのは
686日本@名無史さん2018/03/16(金) 20:51:44.09
その
>>389 >>旧唐書も、地理説明と移動説明を、はっきり書き分けていた、という事になった<
>なってない
成都に行く経路は、「地理説明」と「移動説明」のどっちだ? <
「通水陸行」は、「移動説明」による「位置説明」だ。
833日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:56:25.35
貼ってまわって
>>390 >>国内移動は記載されている場合もあれば、記載されていない場合もある。<
>その「記載されている場合」がどこにあるかと訊いてるんだが?<
對海國と一大國と末盧國だ。
>>580 >位置説明で、「方向」だけの場合がある。
>「西北接百濟、正北抵新羅、南與越州相接」。
これは「接」「抵」が距離を示しているんだよ
ザラコクはまた変な誤読をしてるけどさ
漢文を読めないやつが、誤読曲解で何を書いてもムダだよ
>>393 >>中国史書群に、海外の「山島國」への旅程の記載があったのか?、も知らんよ。<
>漢籍電子文獻資料庫で全文検索をかけても、「山島國」なんて国は
中国の史書には1ヶ所も出てこないね
島巡り仮説など、妄想にすぎないということだ<
じゃ、對海國と一大國の記載は、「孤立情報」であった訳で、
記載そのものの存在が根拠だ。
>>587 >「通水陸行」は、「移動説明」による「位置説明」だ。
これまで、「移動説明」と「位置説明」は違う、区別できるっていう
主張だったのに一緒になっちゃったねぇ
つまり、「移動説明」も「位置説明」も、定義すらできない適当な
ザラコク表現な訳だ
>>592 >對海國と一大國と末盧國だ。
言い張るだけじゃなくて「典拠」を示して、どこがどうなのか説明しないと
意味がないよ
>>394 >>50里以下の短距離は、足していないん「だろう」なあ。<
>「根拠」のない「ザラコクのザレゴト」は書くなよ! <
記載された里数の最小里数が、100里だから。
>>594 >じゃ、對海國と一大國の記載は、「孤立情報」であった訳で、
>記載そのものの存在が根拠だ。
「じゃ」じゃねーよ、「じゃ」じゃww
とうとう、降参だね
ザラコク理論は、一切典拠がなく、説明もできない妄想だと確定しました!
>>597 >記載された里数の最小里数が、100里だから。
四捨五入して50里以下じゃなかったのか?ww
そんな小さな国はないよ
>>395 >大理から出る道は基本的に南方向で、東から南東どころかさらに方角がずれる <
無量山脈越えになる。
>最終的に「通水陸行」するのは、誰がなんと言おうと、「ソンホン側沿い」
それが、中華王朝の内陸部から安南(ハノイ)に抜けるメインルートで
現在も利用されている <
無量山脈越えよりは、昆明方向へ行く。
それが「通水陸行」であり、ほぼ東方向。
>>396 >>還「到」龍亢、は、(努力して)還り来て龍亢に到り立った、という強調する意図が強いが、<
>元いた場所に還えるんだから、努力する必要はないだろ?<
反乱が起きた所だから、必死で到った。
>>397 >伊都国が大陸の史書に出てくるのは、あと、北史と梁書にあるが、
どちらも「至」を使ってるぞ
北史/ 列傳 凡八十八卷/ 卷九十四 列傳第八十二/ 倭
「一海千餘里,名末盧國。又東南陸行五百里,『至』伊都國」
梁書/列傳 凡五十卷/卷五十四 列傳第四十八/諸夷/東夷/倭
「一海千餘里,名未盧國。又東南陸行五百里,『至』伊都國」<
梁書と北史は、元々、前史記載を「自己解釈に拠る内容説明的書き換え」が多い書。
>>398 >>>竹島→一支國の移動説明。<
>移動説明なら、經都斯麻國で、対馬を通ったのは確実だよな?
だって、「対馬を経由した」って「移動経路を説明」してるんだから<
都斯麻國は、「至」ではなく「經」ではなくだから、寄港せずに通り過ぎた。
>で、対馬に来て、そのまま東に行ったら壱岐には着かないだろ?<
竹島からまっすぐ東に向かって、都斯麻國には寄らかったから、
(東のままで)一支國に着いた。
>>402 >後漢書が書かれた5世紀の時点では、まだ九州の方に主権があったが、
筑紫倭国が畿内も植民地化していたので、大倭で間違いない。<
中国では「大」は、
「大乱」が天子の支配を覆すような乱である事を示しているように
「天子や皇帝に関係がある事を示す」大義名分的な文字としても使用され、
後漢書の范曄は、それを知らず?、
倭王が複数以上の国を支配している事を知って、
「大倭王」という文言を使ってしまった。
>>409 >例えば、一文字あたりの間違う確率が1万分の一であっても、
5万字の書物であれば、一回の書き写しで5文字間違うことになる<
実際に、魏志倭人伝の2000字位の中で、
宋明清代の写本や版本の校勘対象や問題になったのは、
「都支國」と「郡支國」、
「黄幢」と「黄憧」位であり、
「對海國」と「對馬國」は、
「對馬國」が後代の呼称での書き換えであった事がはっきりしていたから、
始めから否定されたの。
>>600 ザラコクさん、あなたは周回遅れだからごまかせると思ってるかもしれないけれど
ソンホン川の源流に出るのに、無量山脈を越える必要は全くないんだ
その山脈の東側を川沿いに行けるんだよ
>無量山脈越えよりは、昆明方向へ行く。
昆明行きの場合大理から出る道は南向き
大理から昆明方向も南東であって東ではない
>それが「通水陸行」であり、ほぼ東方向。
これがまるっきりの嘘
全然東じゃないのはすでの地図上で方角を測った値を示してある
九州説の人は、といって悪ければ、ザラコクは
嘘をつくことにまったく抵抗感や罪悪感を感じないようだ
>>601 >反乱が起きた所だから、必死で到った。
反乱が起きたんじゃなくて、地元だから家に帰っちゃったんだよ
原文は「還「到」龍亢、士卒多叛」叛いた=ついてこなくなった
必死に到ったとか、本当に適当に書くよな
>>411 >>いや、魏徴らは「邪靡堆」として記載した、という確率が非常に高い。<
>いやいや、それ、なんの「根拠」もないから
そもそも、日本人なら「邪靡堆」に当たる地名なんて日本のどこにもないし、<
これは、「對海國」と「對馬國」の問題と同じ。
後代に「対馬」という呼称が存在したから、
後代に「對海國→對馬國」の書き換えをしたアホ史家がいた、んだろうという事。
「邪靡堆→邪摩堆」も同じ。
後漢書に「邪馬臺國」があるから、
北史の筆者が「邪靡堆は邪摩堆の間違いだ」として書き換えたもの。
実際には、7世紀の「古宮」遺跡が、何という文字呼称であったのか?は、
全く残っておらず、不明なまま。
>>602 >梁書と北史は、元々、前史記載を「自己解釈に拠る内容説明的書き換え」が多い書。
都合の悪いのは、「あーあー見ない聞こえない」だから
チェリーピッカーって言われるんだよ
>>412 >>後代史書の北史が書き換えた「邪摩堆」なら「ヤマタイ」であり、
「ヤマト」なんて読めない。<
>ヤマタイならヤマタイでもいいよ
それこそ、初出の魏志倭人伝が「邪馬臺」だったことの証拠にしかならないし<
後代史書の「書き換え」は、証拠にならない。
>>603 >都斯麻國は、「至」ではなく「經」ではなくだから、寄港せずに通り過ぎた。
寄港しなくてもいいけど、対馬まで来てるんだよ
だから
>竹島からまっすぐ東に向かって、都斯麻國には寄らかったから、
>(東のままで)一支國に着いた。
これは成りたたない
残念だがザラコク理論は通らないんだ
>>605 >「對馬國」が後代の呼称での書き換えであった事がはっきりしていたから、
これの根拠は?
ほんっとうにいい加減なことを平気で書くよなぁ
>>415 >>魏志の邪馬壹(ヤマイ)は、大野~大宰府付近の呼称であったのであり、<
>その辺にそんな地名はないって何度言えばいいんだよ
そんな地名があるなら教えてくれって言ってるのに、何一つ挙げられないじゃないか<
(郭務ソウ)の報告にあって、それで李賢が後漢書に注をした「邪摩惟=ヤマイ」。
>>後漢書の邪馬臺(ヤマダイ)は、
久留米~八女付近の呼称であった、というだけだ。<
>その辺にそんな地名はないって何度言えばいいんだよ
そんな地名があるなら教えてくれって言ってるのに、何一つ挙げられないじゃないか<
久留米の近くに「臺」という地名がある。
>ついでに言えば、普通の九州説で「邪馬壹(ヤマイ)」を主張するやつは、
ヤマイ=八女に当てるんだぞww
でも「イ」はどこから来たんですかと訊くと、たいてい答えがないww <
「邪馬壹(ヤマイ)」は「福岡平野の中程~筑紫平野、およびその周辺丘陵地域」。
「女王之所都」は、おそらく安徳台。
>>612
ザラコクに餌を与えないでください
ザラコクに構わないでください 危険です >>608 >実際には、7世紀の「古宮」遺跡が、何という文字呼称であったのか?は、
>全く残っておらず、不明なまま。
いろいろ書いてるけど、結局根拠のない思いつきだってことじゃないか
ザラコクの妄想につきあう気はないよ
>>416 >>魏志の邪馬壹國と、後漢書の邪馬臺國は、場所も大きさも違う別物。<
>魏志倭人伝「邪馬壹國、女王之所都」 後漢書「大倭王居、邪馬臺國」
どちらも王都だと書いてあるね <
時期も違う。
>そして、どちらも同じ倭王だし遷都したとは書いてない 同じ場所だろ? 字を間違えているだけで <
聖徳太子伝暦が、
久留米付近の都が、317年頃と517年頃と617年頃に移転があった、
というような事の伝承を記録している。
邪馬壹は女王国南限の邪馬国(山門)に在った女王の砦の王宮=壹
邪馬は和音の固有名詞で壹は臺で表意文字の楼閣
梯儁は金印紫綬で卑弥呼の王宮を見ているのでこれを命名した。
梯儁の説明以外で邪馬台国という地名は存在しない。
肥築の堺辺りに人命尽くしの神がいて、ツクシの由来になったと言われているが、誰なんだろうか?
日本建国は、記紀の定義に合わせるならば、西暦195年になるであろうが、国号が公式のものとなった西暦689年とされるであろう。
https://twitter.com/syk_ysn/status/975331217292709888 >>616 >久留米付近の都が、317年頃と517年頃と617年頃に移転があった、
それ、原典を示してね
ザラコクの思い込みには「何の意味もない」
>>620
ザラコクに餌を与えないでください
ザラコクに構わないでください 危険です >>419 >九州説はよく「東征毛人五十五國」を書くけど 「西服衆夷六十六國」はどうするんだ?
九州の西に「六十六國」の入らないぞww<
何度も説明している。
「服=服従する」は自動詞的文字であり、「衆夷六十六國は既に服属している」であり、
九州付近の事。
>>421 >ついでに、水行は海か大河のみで、玄界灘、響灘に面した福岡平野あたりから
南へ水行するのは不可能<
「南に水行」は、不彌國からの側副傍線國の投馬國の位置説明であるから、
不彌國から一旦玄界灘へ出て、東廻廻りでも西廻り廻りでも良いから、
海岸沿いに九州を回って、水行二十日位行ったところ。
>>623 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
早く言えよおまえ。
>>617 八女にあった王宮で邪馬台か。
ふむふむ。
>>622 >何度も説明している。
>「服=服従する」は自動詞的文字であり、「衆夷六十六國は既に服属している」であり、
>九州付近の事。
すげえなザラコク
何の説明にもなってないのに
それを繰り返して「何度も説明している」って!
>>623 >不彌國から一旦玄界灘へ出て、
それだと出発方向の西なり東なりの方角が書かれなきゃいけないんじゃないのか?
ザラコク理論では
そういって伊都国の南東が間違ってないっていってたんだから
>>622 >何度も説明している。
>「服=服従する」は自動詞的文字であり、「衆夷六十六國は既に服属している」であり、
うそ
「以力服人者、非心服也」(孟子)
>>425 >>そんな物を顔料や仙薬に使っていたら、その内水銀中毒で死んでしまうよ。<
>水銀朱、硫化水銀は、水に不溶だから毒性はないんだよ
どうもこの辺を理解していない人が多い<
いずれにしても、水俣の有機水銀と同じく、
微量の摂取の蓄積が神経毒になっていくんだろうなあ。
>>429 「中国人が、南と東などの方向を間違う」なんて、ひどいことを書くなぁ。
このスレでは「・・・・」=「大和説者の学会教育界や文部省や右翼マスコミ」ww。
>>430の訂正。
これ一つで、倭王武が九州王朝の王ではあることが丸分かりww 。
>>431 >九州の西に「六十六國」は入らないことは認めるんだな?
その時点で、倭王武は九州王朝じゃないぞww <
「征=征伐する」や「平=平定する」はいずれも他動詞であったが、
「服=服属する」は元来自動詞であるから、
「西の衆夷六十六國は以前に服属している」という意味になり、
「六十六國」は、九州付近全域になり、
当然、その中に西九州も含む事になる。
九州の西に「六十六國」は入らないことは認めるんだな?
その時点で、倭王武は九州王朝じゃないぞww
>>432 漢文が読めないのに、無理をして見当違いのことを書いているのが笑える。
問題は、倭王武の本拠地が、 元々西の66国の中にある、ってことだ。
大和は、倭国から別れた別種の旧小国であった事からも判る。
大和ではムリポ 。
>>440 >国津神が治める国。芦原中津國。 津ツはのという意味。
クニの神。 クナの神。 クナトの神。<
「南≠東」に拠って、
狗奴國は、大国主や少彦名の支配下の国ではなく、
×。
>>442 >芦原中津國はクナ、狗奴国かもしれないな。<
「南≠東」に拠って×。
>邪馬台国、ヤマトの南にある狗奴国。 官は狗古智卑狗、コウチヒコ、河内彦かな。<
「邪馬台国」なんて存在もしないから、×。
>>443 >壬申の乱で負けた難波は奈良時代は寂れていた。
古代の難波はどういう場所だったのか?・・・<
元は出雲系であったが、筑紫倭国の東征で、筑紫倭国の直轄的な地になり、
更に筑紫倭国の「分都の倭京の一つ」のようになっていた。
>>467 >(一支國→竹斯國)じゃ、なんで東南と書かないの?
言ってることが支離滅裂だ <
一支國→竹斯國は、肉眼で見えていて、記載する必要がなかった。
魏志でも、
狗邪韓國→對海國と、一大國→末盧國は、肉眼で見えたから方向の記載がなかったが、
對海國→一大國は、肉眼では見えなかったから、
出発方向の「南」を記載する必要があった。
>>469 >雲太、和ニ、京三 仮説だが、
邪馬台国女王国、初期の大和朝廷は、雲太と和ニの国かもしれない。<
「邪馬台国」なんて存在しないし、「初期の大和」は、倭国の別種の旧小国であったのだし、
「朝廷」なんて存在もそなかったから、
これも×。
>>470 まともなことには解答不能なのであり、
ただ、「南→東」などの嘘吐き騙しの分裂幻覚妄想の独断を言い張るだけなんだね?。
>>481 >卑弥呼の頃には、ヤマト=畿内王権が北部九州まで範囲で祭祀を統一して
>根拠は前方後円墳なんだが <
だから、列島の前方後円墳も那珂八幡などがの先行していて、
石塚も箸墓も、那珂八幡の模倣にしかならないんだが。
>>638 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系耕作用農具と中国系住居と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよこの法螺谷法螺男。
>>483 >纒向の祭祀系の遺物を見ると諏訪大社と似ている気がするんだな。卑弥呼の鬼道。
今の神道、烏帽子、鳥の格好で舞う、鐸を鳴らすのとは少し趣きが違う気がする。<
「卑弥呼の鬼道」は、「南≠東」などに拠って×。
>>486 >天皇家は紀元前のクニトコタチと血のつながりがある 直系ではないけど <
紀元前には「天皇」なんてなかったし、
列島住民は、元々全て「治のつながり」がある。
>>488 >普通は天皇家はイザナギ~応神の系譜と考えるが<
古代においては、「天皇」なんていなかったから、×。
>>645 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
早く言えよこの法螺谷法螺男。
>列島住民は、元々全て「治のつながり」がある。
ないよw
>>491 >>幾ら都合の悪い「循海岸」を隠して「水行歴韓國乍南乍東」として誤魔化しても、
普通の「水行」では、「歴韓國乍南乍東」が全く出来ないし、ならないし、
里数も全く合わないから、<
>おいおい、ザラコクが勝手に「陸行」にしてるから
「水行」と書いてあるね、って教えてくれただけだろうが
「南→東」よりも、「水行」と書いてあるのに「陸行」と謎解釈する方が
修正の程度として酷いぞ<
常識的には、郡→狗邪韓國は、
倭王武の「自昔・・・道kei百濟、裝治船舫」のように、
「陸行」であったから、記載する必要がなく、
しかし、魏使らは郡出発が「循海岸水行」という特異な出発であったから、
記録したの。
勿論、郡の中国船に拠る沖合洋上航行であったんなら、
途中で遠回りして狗邪韓國に寄港するなどの寄り道もする必要がなく、
筑紫へ直行して行けば住むにだが、
それも魏志の「持衰」の同乗の件で否定される。
2013年のあの日以来、小汚く年老いた奈良の自称考古学者が、優秀な若い古代研究家たちに、無茶な自説をゴリ押すための工作やパワーハラスメントを仕掛けることが多くなってきたが、良識ある若者たちは結束して、真実を次世代に伝えようとしている。。。
すなわち、巻向は邪馬台国とは無関係であると、、、
>>645 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよこの法螺谷法螺男。
(ダブったかも知れないが投稿しておく)
>>421 >ついでに、水行は海か大河のみで、玄界灘、響灘に面した福岡平野あたりから
南へ水行するのは不可能<
(不彌國から)南にある投馬國への側副傍線行程の説明であったから、
不彌國から、一旦玄界灘へ出て、九州の海岸沿いを、
(東回りでも西周りでもよいから)大回りして、不彌國の南の地に行ければよい。
>>494 >大和朝廷の始まりは卑弥呼、台与だけどね。<
「大和朝廷」なんてなかったし、「南≠東」に拠っても×。
>>629 >いずれにしても、水俣の有機水銀と同じく、
>微量の摂取の蓄積が神経毒になっていくんだろうなあ。
ならねぇよ
水に不溶ってことは、人体に入らないってことだ
消化管の中は人体の外だからな
ザラコクは、理系も文系も科学をまったく理解してないんだから
いい加減に、考えるのはやめな
イオン化しても、原子核の崩壊確率は変わらないっていう単純なことすら
理解できないんだから
>>633 >問題は、倭王武の本拠地が、 元々西の66国の中にある、ってことだ。
はい、この時点で、漢文の読み方として破綻しています
つまり、倭王武が九州王朝の王であることを自ら否定ww
ザラコクのやることはいつもこんなもの
>>495 >魏志倭人伝 邪馬台国の官<
「邪馬台国」なんて存在しないから×。
>官は伊支馬有り。次は弥馬升と曰う。次は弥馬獲支と曰う。次は奴佳鞮。
伊支馬は生駒。<
「南≠東」に拠って×。
>>637 >一支國→竹斯國は、肉眼で見えていて、記載する必要がなかった。
対馬から壱岐も、壱岐から筑紫も肉眼で見えてるんだよ
でも、魏志倭人伝ではいちいち南って書いてあるよな?
肉眼で見えるかどうかは、史書を読む人には関係ない
途中で方向転換が記載していなければ、読む人に地理は伝わらない
だから、末慮国ー伊都国間も海岸沿いだから出発方向だけでいいなんていうのは
ありえない暴論
まあ、その辺が理解できないからザラコクなんてやってるんだろうけれど
>>496 >纒向の外来系土器で一番多いのは、尾張三河東海系。
これが邪馬台国初期の大和朝廷の中心じゃないかな。<
「邪馬台国」も「朝廷」も存在していなかったから、×。
>伊支馬は尾張のトップな気がするんだな。<
「南→東」などの分裂幻覚妄想の嘘つき騙しだから、×。
>>648 >道遥百濟裝治船舫
まさか、ここの「道」一字で陸行だって主張してるのか?
「海道」って言葉知ってるか?
裝治船舫って書いてあるのは無視か?
船でどうやって百済を陸行するんだよ?
>>500 >邪馬台国女王国初期の大和朝廷<
「邪馬台国」や「朝廷」なんて存在していなかったし、
「女王国」も、「南≠東」に拠って、×。
>>502 >ただ、豪族層は応神前後で変化はないんだよな
その意味でヤマトの朝廷はそのまま存続している<
「 ヤマトの朝廷」なんて、存在していなかったから、×。
>継体天皇の時も豪族は変わらないんだけれど <
「天皇」も、まだ存在していなくて、
継体も、越~摂津や大和の豪族。
>>662 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
早く言えよこの法螺谷法螺男。
>>633 >漢文が読めないのに、無理をして見当違いのことを書いているのが笑える。
>問題は、倭王武の本拠地が、 元々西の66国の中にある、ってことだ。
東征毛人五十五國
西服衆夷六十六國
これって自分が中央だって意識そのものでしょ
倭王武の本拠地の本拠は西でも東でもない
自動詞だ云々という主張も、無学丸出し
「服」が動詞で「衆夷六十六國」が目的語なのは誰にでもわかる
明らかに、漢文が読めないのは自分でしょ
>>508 >670 庚午 新羅を訪問した安曇連頬垂
(アヅミノムラジツラタリ)が「日本國」を名乗った<
670年なら、
唐会要倭國伝の「倭國使が日本国を名乗った」記録の年でもあるし、
安曇は、筑紫だから、この話も、筑紫倭国の話であった可能性もあるね。
2世紀末から4世紀にかけて刀を貰った人物は卑弥呼しかいない。
だから、中平銘鉄刀の発見者であり、先日お亡くなりになられた金関 恕さんは、
1年前の考古学雑誌に卑弥呼の五尺刀だと書いておられる。
仮にそうであるとして、謎の豪族・和邇氏と卑弥呼がどう繋がるかが誰も解けない。
解いたのはわしだ、ほれ。和邇氏はトヨから始まります。
事代主
┣━━━━━━━┓
天日方奇日方(鴨王) ヒメ踏鞴━━神武
┣━━━━━━┓
建飯勝 渟名底仲媛━━ 安寧
┃ ┃
建甕尻 息石耳 ※ヒメ踏鞴(248年没)
┃ ┃
豊御気主 トヨ津
┃ ┃
大御気主 孝昭
┃ ┃
阿田賀田須 天足彦国押人命
┃
和邇日子押人命
┣━━━━━━━┓
彦国姥津命 姥津媛(開化天皇妃)
┏━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━┓
伊富都久命 彦国葺命 小篠命 乙国葺命
┏━━━━━━┳━━━━━━━┫ 【丈部氏祖】 【吉田氏祖】
彦忍人命 建耶須禰命 大口納命 【飯高氏祖】
(武社国造) ┃ ┣━━━━━━━┳━━━━━━━┓
八千宿禰命 難波根子武振熊命 彦汝命 真侶古命
(吉備穴国造) 【和邇氏祖】 【葦占氏祖】 (額田国造)
邪馬台国論争は終了です、邪馬台国はヒメやトヨが住んだ葛城。
>>523 >>筑紫倭国も「日本」と名乗っていたんだし、<
>また結論先にありき・・・かぁ<
釈日本紀に書かれた「晋の惠帝への日本国の名乗り」は、
晋書側の記録では、(大和の事ではなく)、筑紫の倭國の事になるから。
>>666 >670年なら、
>唐会要倭國伝の「倭國使が日本国を名乗った」記録の年でもあるし、
これも全くのウソ
唐会要倭國伝で670年には「倭國使が日本国を名乗った」りしていない
>>662 >>668 九州王朝なんてない
拠ってザラコクは始めから×
>>668 >釈日本紀に書かれた「晋の惠帝への日本国の名乗り」は、
>晋書側の記録では、(大和の事ではなく)、筑紫の倭國の事になるから。
これもまた、ひたすら結論先にありきか・・・
だから九州説は非論理的だと言われるのだ
>>524 >>大理から直接東南へ行けば、地図では、猫頭山?とかの相当な山塊が続いており、
ソンホン川の源流に達するのも困難なようだ。<
>? ソンホン川の源流は大理市内ですけど? ???<
大理にほぼくっついている北の「ジ海」から流れ出す河は、下流をたどれば、
メコン川(やメナム川?)方面に下っているぞ?。
>>672 >大理にほぼくっついている北の「ジ海」から流れ出す河は、下流をたどれば、
>メコン川(やメナム川?)方面に下っているぞ?。
ザラコクの大好きな猫頭山の東側を流れている川をたどってごらん
>>525 >大理古城より成都城市之心まで 方角は北から33度49分
正北東45度よりだいぶ北寄りで、これを東と強弁するのは無理すぎる<
誰がそんな「強弁」をしたの?。
私は「如至成都」でそんなことを」でいう筈がないし、
「東至安南」とか「通水陸行」とかを書いたのは旧唐書。
>大理古城よりハノイ昇竜皇城遺跡まで 方角130度35分
正東南135度より僅かに東寄り 東南と呼ぶのにふさわしい方位<
旧唐書は、
「陽苴咩城,南去太和城十餘里,東北至成都二千四百里,東至安南 如至成都,通水陸行」
と書いたのだから、
安南へは、方向が「東南~東南東」であっても、
東へ「 如至成都,通水陸行」すれば至る、
と書いた、という事だ。
>>674 さすがのザラコクも意味のあることは書けなくなったな
まあ、最初から意味のあることなんて書いたためしがないとも言えるが
>東へ「 如至成都,通水陸行」すれば至る、
成都に向かうのは「『東北』至成都二千四百里」と書いてあるとおり、東北で
東へ向かうのは「如至成都」にならない
そして、この辺がザラコクの漢文に対する無知から来ているんだが、
「通水陸行」は「東至安南」にしかかからず、成都は無関係
「如至成都」は、大理から安南までの距離
まあ、何度教えても「見ない聞こえない」を貫くだろうけれど、
何度でも突きつけてやるよ
ザラコクは自分の間違いを認められない一般の日本人とは
価値観が違う儒教道徳を信奉する卑怯者だって
>>526 >縄文時代の九州人が太平洋横断して南米に土器を持ち込んだというのは <
持ち込んだ、というのではなく、航海のために「水を溜め容器」が必要であったのだ。
必要は、発明の母だ。
>南米の先住民が土器文様を生み出すはずがない という蔑視と単一史観が基礎にある<
「水などの貯蔵用の容器」であればよかったのであり、
それが形や模様まで大体同じようなものにした、という事は、
同一部族であった可能性が高い、という事だ。
>>676 >それが形や模様まで大体同じようなものにした
形が違うんだよ
文様の一致も、無紋土器まで「無紋という文様」の一致と数えている
>>674 >旧唐書は、
>「陽苴咩城,南去太和城十餘里,東北至成都二千四百里,東至安南 如至成都,通水陸行」
>と書いたのだから、
>安南へは、方向が「東南~東南東」であっても、
>東へ「 如至成都,通水陸行」すれば至る、
>と書いた、という事だ。
つまり旧唐書は方位を間違って書いてるんだよね
東に行ったら絶対に安南には着かないのだから
>>676 >「水などの貯蔵用の容器」であればよかったのであり、
そういう用途には桶をつかうよ
軽量で運びやすく、素焼甕のように水が漏らず、割れない
>>533 >>また、何か?変な事を言ってるな?。
「太和城は前都で、今も大理市内に遺跡がある」では、(陽苴?城=大理ではなく)
太和城=大理だという事になってしまうではないか。<
>「南去太和城十餘里」 唐里で10里しか離れてないんだよ たった5キロちょいの距離
今の大理市の大きさの中に入ってしまうんだよ<
「今の大理市の大きさ」なんて、関係がないだろ?。
旧唐書時代には、陽苴咩城と太和城があって、陽苴咩城の場所の話をしているんだから、
陽苴咩城の位置説明が問題。
>>537 >南米の人類の歴史はまだよく解明されていない
ブラジル北東部のセラ・ダ・カピバラ遺跡では
6万年前に遡る3万点の線刻岩絵群と洞窟壁画が見つかっている
最後の氷河期以前に絶滅した動物などが描かれている
壁画には、世界で最古の船も描かれている<
成程。
>>538 >そもそも大理ー安南の記述は大理(陽苴?城)の位置を示す記述で、
直線方向と距離で示しているのだから、昆明すら関係ない <
「陽苴咩城,南去太和城十餘里,東北至成都二千四百里,東至安南如至成都通水陸行」
だから、
「東至安南」に関しては「如至成都通水陸行」の場所だ、という説明をしており、
昆明は、その「如至成都通水陸行」の東行の方向にある。
>>680 >「今の大理市の大きさ」なんて、関係がないだろ?。
>旧唐書時代には、陽苴咩城と太和城があって、陽苴咩城の場所の話をしているんだから、
>陽苴咩城の位置説明が問題。
>>518で
>「太和城は前都で、今も大理市内に遺跡がある」では、(陽苴?城=大理ではなく)
>太和城=大理だという事になってしまうではないか。
こう書いているのがザラコク
ていうか自分でも再引用しているのに見えてないのかな?
太和城も陽苴咩城も大理市内なんだよ
だって、5キロしか離れてないんだから
そして、大理っていうのは「今の地名」で説明しているんだから
むしろ「今の大理市の大きさ」しか関係ない
本当に、脳軟化症なんじゃないか?
自分の書き込みの意味が理解できてないだろう?
卑弥呼は巻向と箸墓だよ
コウゲン天皇に仕えた
初代コウゲンは橿原市
コウレイまでがクニタチの系譜
コウゲンはウナベ、オワリ、モノノベといった豪族だろう
【Jap安倍降ろし】 キッシンジャーは田中を「ジャップ」と呼び捨て、官僚とマスコミは田中を葬った
http://2chb.net/r/liveplus/1521427443/l50 >>680 >旧唐書時代には、陽苴咩城と太和城があって、陽苴咩城の場所の話をしているんだから、
>陽苴咩城の位置説明が問題。
どっちにしろ洱海の西岸にあるんだから
東方向に「出発」することは無い
>>682 >「東至安南」に関しては「如至成都通水陸行」の場所だ、という説明をしており、
>昆明は、その「如至成都通水陸行」の東行の方向にある。
再度書き下し
皋は遂に巡官崔佐時に命じて牟尋の都する所、陽苴咩城に至らしむ
南へ去ること太和城へ「十餘里」
東北へ成都に至るに「二千四百里」
東へ安南に至るに「成都に至るが如し」、水陸行を通ず
さらに、現代文にすると
「皋」はすぐさま巡官「崔佐時」に命じて「牟尋」の(遷都した)都である陽苴咩城に行かせた
(陽苴咩城は旧都の)太和城は南に「十餘里」のところで
成都は東北方向に「二千四百里」 行ったところ
安南は東方向で距離は成都までと同じくらいで、水陸行で行ける
となる
昆明なんて出てこないし、そもそも漢文の書き方として
「南去」太和城十餘里,
「東北至」成都二千四百里,
「東至」安南如至成都,通水陸行
方角で区切られたところごとに独立だぞ
成都に行くのに通水陸行なんかしない
そして、地図を確認すれば分かることだが成都に行くときこそ、昆明を通ることになる
でも、成都へは「東北」と直線方向が書かれていることが分かる
安南へも直線方向なんだよ
そして、実際の安南へは誰がなんと言おうと「南東」、でも「東」と書いてあるから明確な方角の間違い
正史の地理・旅程記事は、方角を間違うときは間違う
方位を間違うはずがないというのは、論理学的に「偽」
だから「論証抜きの南≠東」には何の意味もない
それを書き続けるザラコクは、頭おかしい
>>539 >>(エクアドルの縄文やズビニ鈎虫など)大西洋横断の痕跡がなければ、太平洋横断。<
>順序が逆 ズビニ鉤虫がいたから、それが太平洋横断の痕跡とされているのであって、
大西洋横断の痕跡としても何の問題もない <
順序が全く逆。
魏志や海賦に「太平洋横断を示す記載」があって、
それの証拠になるような痕跡があった、という話。
>南米諸族がグレートジャーニーの結果のモンゴロイド系なこともあって、
アジア太平洋側とのつながりが想定しやすいってのもあるだろう<
当初は、グレートジャーニーを想定していた訳ではなかった。
>この辺は、太平洋の海洋民族の航海能力は想定以上に高かった可能性を示唆するだけで
「そんなこともあったかもしれないね」程度のこと <
魏志の裸國黒歯國の記録は、事実であったらしい、という事。
>>540 >>九州に多い HTLV-1ウイルスが南米にも存在して、
しかも遺伝子型が共通しているという話じゃなかったっけ?<
>HTLV-1は母子感染が主で、グレートジャーニーで説明できるから、
低温域を通過できないズビニ鉤虫の方が九州説のお気に入りらしいよ <
両方とも、縄文人や倭人の太平洋横断の根拠になる事が、
大和説者は、事が気に入らんらしいよ。
>>542 >HTLV-1は母乳感染<
、
ウイルスなら、(風疹ウイルスのように)、胎盤通過が有り得る筈だが。
>>544 >>大理から直接東南へ行けば、地図では、猫頭山?とかの相当な山塊が続いており <
>ソンホン川の源流は大理市内にあって、猫頭山の西側を南に近い南東方向に流れ下るんだよ<
私の見た地図では「ジ海」はメコン川方面に繋がっていて、
安南方面に繋がっているようには見えなかったが。
>>545 >HTLV-1は性行為感染症の側面もあるけれど、ほぼ男性から女性の一方方向で、
感染確率は高くない<
遺伝子に組み込まれたウイルスだ、という話があった?と思うから、
やはり遺伝的だったんだろう。
>>547 >盆地はどこ行くにも峠越えがあって当然だよね
それより、最初は出発方向だというのがウソと判明したのは大きいかな <
判っちゃいないんだな?。
「陽苴咩城,南去太和城十餘里,東北至成都二千四百里,東至安南如至成都通水陸行」
なんだから、
「東至安南如至成都通水陸行」も安南の位置説明であり、
そこへの「通行」路を「如至成都通水陸行」と説明しているんであり、
筆者は、
(行程や旅程などのような)実際の安南への移動、を説明、しているんではないんだよ。
>大理は洱海の西岸だからね <
これもまだおかしな事を言っている。
陽苴咩城の「南去太和城十餘里」のに太和城もある、といな置関係なんだから、
陽苴咩城が、ジ海の西岸か東岸か?も、
まだ判らんではないか。
>>693 何をどう見た?
誰が安南方面に繋がっているなんて言った?
また妄想?
>>551 >>「南≠東」だから×<
>はいはい、自分の間違いが認められない人は惨めですね
何度も、そんなのは通用しないと突きつけられて
でも、自分のスタイルを曲げられない、惨めで悲しいザラコクさん<
はいはい、いくら大和説者が難癖を付けようとしても、
「南=東」の確率は、ほぼ0%であり、
惨めで悲しいのは、文部省や右翼マスコミや学会教育界や大和説者さんら。
>>553 安部文部省や右翼マスコミや学会教育界ややくざ暴力団や大和説者が否定したら、
そりゃ逆に、殆ど正しい、ってことになるんだよ。
>>573 >>太平洋には、倭人伝や海賦の記録があるし、<
>それがあてにならないっていってるんだよ<
「南→東」などの嘘吐き騙しの大和説者のいう事は、当てにならない、って言ってんだよ。
>倭人伝のは、淮南子や山海経からの転記だし<
倭人伝のも、淮南子や山海経からの転記になっていないし、
そんな事がバレたら、魏使らの首が危ないんだし・・・。
>>1 >纒向遺跡の発掘状況等から、ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ女性であったと考えられる。
これについて、文句ある奴は手を挙げて文句を言え。
>>577 >>大理の南東には、最高峰が猫頭山(Maotou Shan=3,306m)の無量山脈があるらしい。
>万策尽きたかい? 大理から安南の経路は、どうやっても南東なんだよ
つまり、「東」至安南の記述は、方角の間違い 旧唐書は、×書にできないから諦めな <
万策尽きたんかい?。
「ジ海」の南岸付近から、安南への「通水陸行」道は、東の昆明方向しか残っていない、
という事で、
旧唐書も、方向を間違えていなかった、という事だよ。
>>1
>纒向遺跡の発掘状況等から、ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ女性であったと考えられる。
5chだからなにを書いてもいい だが、よそでは言うな >>758 >ザラコクは、猫頭山を大理の南東って言ってるけど、八方位で言えばむしろ南だよな
その東側をソンホン川の源流は、南東の安南(ハノイ)に向かって流れていくんだよ <
私が見た地図では、ソンホン川の源流は、「ジ海」には届いておらず、
「ジ海」から流れた水は、「ジ海」の西でメコン川方向に下っているように見えるんだよ。
>>596 >位置説明で、「方向」だけの場合がある。
「西北接百濟、正北抵新羅、南與越州相接」。<
>これは「接」「抵」が距離を示しているんだよ
ザラコクはまた変な誤読をしてるけどさ
漢文を読めないやつが、誤読曲解で何を書いてもムダだよ<
世間の皆様。
これが「南→東」などの嘘吐き騙しの大和説人種の正体なんですよ。
唐会要の「接」と「抵」の、どこが距離を表している事になるのやら?、ですよね?。
唐は、
倭國が百済と同盟して、唐と新羅の連合軍に敵対した事を、
当然熟知しているんですよね?。
>>595 >>「通水陸行」は、「移動説明」による「位置説明」だ。<
>これまで、「移動説明」と「位置説明」は違う、区別できるっていう
主張だったのに一緒になっちゃったねぇ
つまり、「移動説明」も「位置説明」も、定義すらできない適当な <
始めから、旧唐書のその部分は、三つとも位置説明である、と言っており、
「東至安南」の部分だけが「如至成都」の「通水陸行」の移動説明を伴っている、
という説明をしていた筈だ。
>>596 >>(国内移動説明が書かれているのは)對海國と一大國と末盧國だ。<
>言い張るだけじゃなくて「典拠」を示して、どこがどうなのか説明しないと
意味がないよ <
・・・・アホには、面倒だから転写だけ。
始度一海、千餘里至對馬國。其大官曰卑狗、副曰卑奴母離。
所居絶島、方可四百餘里。土地山險、多深林、道路如禽鹿徑。
有千餘戸、無良田、食海物自活、乘船南北市糴。
又南渡一海千餘里、名曰瀚海、至一大國、官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。
方可三百里、多竹木叢林、有三千許家。
差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。
又渡一海、千餘里至末盧國、
有四千餘戸、濱山海居、草木茂盛、行不見前人。
好捕魚鰒、水無深淺、皆沈沒取之。
ザラコクに餌を与えないでください
ザラコクに構わないでください 危険です
>>598 >>じゃ、對海國と一大國の記載は、「孤立情報」であった訳で、
記載そのものの存在が根拠だ。<
>「じゃ」じゃねーよ、「じゃ」じゃww とうとう、降参だね
ザラコク理論は、一切典拠がなく、説明もできない妄想だと確定しました!<
「南→東」などの史料事実を否定曲解する嘘つき騙しの・・・・大和説男は、
不可知部分が殆どである自然や歴史においては、孤立的な情報が幾らでも有り得て、
そのそれぞれが存在の事実証拠になる、」
という事が理解出来ず、
議論に負けて、誹謗中傷のヘイトスピーチを世間の人々に宣伝して、逃げました。
>>599 >>記載された里数の最小里数が、100里だから。<
>四捨五入して50里以下じゃなかったのか?ww そんな小さな国はないよ<
吉野ヶ里も2㎞位の広さだな?、と見えた。
>>603の訂正
都斯麻國は、「至」ではなく
「經」だから、寄港せずに通り過ぎた。
竹島からまっすぐ東に向かって、都斯麻國には寄らかったから、
(東のままで)一支國に着いた。
>>711 >竹島からまっすぐ東に向かって、都斯麻國には寄らかったから、
>(東のままで)一支國に着いた。
その論理だったら、都斯麻國の「前」に東って書かれなきゃいけないって
分からないんだろうな、ザラコクだから
>>710 >吉野ヶ里も2㎞位の広さだな?、と見えた。
「環濠だけ」が国の訳ないだろうがww
>>697 >「南=東」の確率は、ほぼ0%であり、
「ほぼ」?
ずいぶん軟化したなww
そろそろ自信がなくなってきたのか?ww
まあ、ザラコクが何を言っても現実や真実とは関係ないんだけどな
>>702 >「ジ海」の南岸付近から、安南への「通水陸行」道は、東の昆明方向しか残っていない、
だから、バカ扱いされるんだよ
洱海の南岸ら辺にあるのが、「太和城」
今問題にしている「陽苴咩城」は、もっと北で洱海の西岸にあるんだよ
だから東にいこうと思うと洱海に突っ込むことになるww
>>693 >私の見た地図では「ジ海」はメコン川方面に繋がっていて、
>安南方面に繋がっているようには見えなかったが。
ソンホン川だって何度も書いてるだろ
それは別の川
本当にザラコクの相手は大変
>>695 >「東至安南如至成都通水陸行」も安南の位置説明であり、
これがそもそも間違い
安南(もちろん成都も)はみんな知ってるから、
それを基準にした「陽苴咩城」の位置説明なんだよ
>そこへの「通行」路を「如至成都通水陸行」と説明しているんであり、
この部分だけはザラコクにしては奇跡的に正しい
>筆者は、
>(行程や旅程などのような)実際の安南への移動、を説明、しているんではないんだよ。
でも、移動するときの経路は説明しているんだよ
昆明なんかは関係ない
南寧はもっと関係ない
>>695 >陽苴咩城の「南去太和城十餘里」のに太和城もある、といな置関係なんだから、
>陽苴咩城が、ジ海の西岸か東岸か?も、
>まだ判らんではないか。
まだ分からんも何も、「陽苴咩城」の位置ははっきり分かってるんだよ
ちったあ調べなよ
まあ、漢文も読めないザラコクでは無理か
>>700 >倭人伝のも、淮南子や山海経からの転記になっていないし、
>そんな事がバレたら、魏使らの首が危ないんだし・・・。
相変わらずザラコクはバカだなあ
転記って言ってるけど、そのまま写したって話じゃないぞ
倭人は珠儒国・裸国・黒歯国など知らないって話
これの元ねたは「大陸側」にしかないんだよ
そして、魏志倭人伝に「珠儒国・裸国・黒歯国」を書いたのは陳寿
魏使の報告書にはそんなことはひと言も書いてない
>>702 >安南への「通水陸行」道は、東の昆明方向しか残っていない、
まだ言ってる
位置説明だから、直線方向なんだってば
でなければ、成都が北西にならないだろ?
それにザラコクのいう移動説明なら、昆明に行く道でも
大理からの出発方向は「南」だ
いちいち矛盾してるんだから、いい加減に自分がバカだって気づきなよ
>>704 >私が見た地図では、ソンホン川の源流は、「ジ海」には届いておらず、
>「ジ海」から流れた水は、「ジ海」の西でメコン川方向に下っているように見えるんだよ。
誰が、ソンホン川の源流が洱海だって言った?
勝手に勘違いして訳の分からないことを書いてもムダ
>>705 >唐会要の「接」と「抵」の、どこが距離を表している事になるのやら?、ですよね?。
漢文が読めないから、これがどれだけ恥ずかしいことを書いているのか
分からないんだよな、ザラコクは
本当に、病院に行けばいいのに
>>706 >始めから、旧唐書のその部分は、三つとも位置説明である、と言っており、
>「東至安南」の部分だけが「如至成都」の「通水陸行」の移動説明を伴っている、
>という説明をしていた筈だ。
「位置説明は、直線方向」だって自分で書いてたのをなかったことにしてるなww
移動説明だと出発方向だって言っていたじゃないか
末慮国から伊都国を東南にするための捏造ごまかしでさ
最初から位置説明なら、最初から直線方向だよな
そして大理から安南の直線方向は「南東」で「東」じゃない
そして、移動説明だというなら、ザラコク理論では出発方向を書いたことになるが、
大理から出て行く道は「南」方向で、「東」じゃない
今までザラコク自身が書いたことで、全部否定されるんだよ
本当に、思いつきだけで整合性のあることが書けないからな、ザラコクは
>>707 >・・・・アホには、面倒だから転写だけ。
本当に漢文一つ読めないやつは惨めだよな
自分の論旨の説明すらできない
まあ、九州説はザラコクに限らず、どれも同じだけどな
>>709 >「南→東」などの史料事実を否定曲解する嘘つき騙しの・・・・大和説男は、
>不可知部分が殆どである自然や歴史においては、孤立的な情報が幾らでも有り得て、
>そのそれぞれが存在の事実証拠になる、」
>という事が理解出来ず、
>議論に負けて、誹謗中傷のヘイトスピーチを世間の人々に宣伝して、逃げました。
はーい、何一つ根拠が書けず、適当なことを書くだけけしかザラコクでーす
孤立的な情報からできるのは、「憶測」だけ!
なんら根拠にはならないよ
>>606 >ソンホン川の源流に出るのに、無量山脈を越える必要は全くないんだ
その山脈の東側を川沿いに行けるんだよ<
ソンホン川は、「ジ海」に届いていない筈。
という事は、ソンホン川の源流に出るには、
大理の南に広がる巨大な大量山脈の山越えを先にしなくてはならず、
「通水陸行」の通水にならないから、×。
>昆明行きの場合大理から出る道は南向き<
いや「通水陸行」は途中の状況であって、出だな。発の方向を意味しない。
>大理から昆明方向も南東であって東ではない<
「東~東南東」方向だから、「ほぼ東」であり、
旧唐書は、方向を間違えていない、という事になる。
>>607 >>反乱が起きた所だから、必死で「到」った。<
>反乱が起きたんじゃなくて、地元だから家に帰っちゃったんだよ<
お前は、「地元だ」なんて書いていなかったよ。
それに、地元なら、ますます必死で「到り戻った」という事になり、
「ますます「到」で適切になっただけだ。
>原文は「還「到」龍亢、士卒多叛」叛いた=ついてこなくなった
必死に到ったとか、本当に適当に書くよな <
実際に、必死で還って来て到着出来た。
>>727 >実際に、必死で還って来て到着出来た。
憶測は根拠にならないよ
そんなんだからザラコク呼ばわりされるんだ
>>701 >
>>1 >>纒向遺跡の発掘状況等から、ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ女性であったと考えられる。
>
>これについて、文句ある奴は手を挙げて文句を言え。
完全な妄想だよ。
>>611 >寄港しなくてもいいけど、対馬まで来てるんだよ <
寄港する必要もないから、寄港もせずに通り過ぎた。
寄港しなくてもいいけど、対馬まで来てるんだよ
>>竹島からまっすぐ東に向かって、都斯麻國には寄らかったから、
(東のままで)一支國に着いた<
>これは成りたたない <
隋書に書かれたように、「又東至一支國」の記載に合っており、成り立つ。
>>726 >ソンホン川は、「ジ海」に届いていない筈。
無駄な抵抗してないで、もう一回地図を見てきな
大理の南に「巍山」ってところがあって、そこを流れているのがソンホン川の源流
アルファベット表記ならWeishanって所の脇を流れているから確認しなさい
ここまで書いてもらえば、ザラコクでも確認できるだろ?
まあ、もともとザラコクに議論する能力がないのは知っているけれど、
ここまで教えてもらって、それでも地図を確認できないなら本当に人間やめますかれベルだなww
>という事は、ソンホン川の源流に出るには、
>大理の南に広がる巨大な大量山脈の山越えを先にしなくてはならず、
だから地図を見ろってww
その山脈の手前に源流があるから
>「通水陸行」の通水にならないから、×。
何度も言うが、通水(水行)になるのは、中越国境を過ぎるあたりからだぞ
>>729 >完全な妄想だよ。
お前にはこんな妄想は書けまい
>>726 >いや「通水陸行」は途中の状況であって、出だな。発の方向を意味しない。
なら、なおさらだww
昆明に行くまでに水行区間はない
水行が混じるのはソンホン川の水行だけで「完全に南東方向」
本当に自分の論旨を自分で否定っていうのを繰り返しまくりww
本当にザラコクだな
>>726 >「東~東南東」方向だから、「ほぼ東」であり、
残念でした
昆明は関係ないし、その関係ない昆明方向ですら、南東方向
東南東じゃないよww
だからどうやっても「ほぼ東」にはならない
どうがんばっても、この部分の旧唐書の「方角は間違っている」
>旧唐書は、方向を間違えていない、という事になる。
本当に、嘘を百回書けば本当になる式のことをやってくるからな
九州説は
何度でも否定してやるよ
現実は、こちらの味方だ
>>730 >隋書に書かれたように、「又東至一支國」の記載に合っており、成り立つ。
漢文が読めないから気づいてないだろうが、竹島(珍島あたり?)から東なら
「対馬の前に東」って入らないといけないんだよ
これが、対馬のあとに「東至一支國」と書いてある時点で、漢文の書法からいって
「対馬から壱岐の方角が東」以外の読み方はありえない
>>726 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
早く言えよ法螺谷法螺男。
>>612 >>「對馬國」が後代の呼称での書き換えであった事がはっきりしていたから、<
>これの根拠は?<
「海と馬」とは、字形も意味も全く違うので「写し間違える文字ではない」から、
誰かが書き換えたものである事と、
後代には「対馬=ツシマ」という音韻名が伝わっておれば、
對馬國を對海國とするような書き換えをする事など起こり得ないが、
對海國であったのなら、それを對馬國とする書き換えは起こり得る、という事と、
そういうように、對海國の方が對馬國よりも「古形」であったんだ、という論理が成立し、
それが、張元済らの校勘の思想であった事。
>>726 >ソンホン川は、「ジ海」に届いていない筈。
あと、「巍山」の隣の谷の、紅岩鎮の谷筋もホンソン川の源流だから
確認しなよ
ここは、昆明に行くにも最初に通るところだから、山越えがどうたらって
いうのは意味がないぞww
>>737 >後代には「対馬=ツシマ」という音韻名が伝わっておれば、
対馬に住み続けている日本人に、対馬という音韻がずっと伝わっているぞ
この時点で、
「對海國の方が對馬國よりも「古形」であったんだ、という論理」は破綻している
本当に、日本人なら当たり前のことを簡単に無視するよな
ザラコクは
>>615 >>実際には、7世紀の「古宮」遺跡が、何という文字呼称であったのか?は、
全く残っておらず、不明なまま。<
>いろいろ書いてるけど、結局根拠のない思いつきだってことじゃないか
ザラコクの妄想につきあう気はないよ<
当然、不可知部分が殆どである自然や歴史において、
「邪靡堆」は、単独の孤立的史料事実であって、
そういう認識での受け止め方をすべきであり、
安易にそれを「間違いだ」とはすべきではない、という事。
>>740 >安易にそれを「間違いだ」とはすべきではない
安易じゃなくて、同じ典拠資料によると考えられる別の書で
はっきり「邪摩堆」って書いてあるんだから、いずれかの原因で
転記ミスが生じたと考えるのが当然だろう
>>620 >>倭國の都が、317年頃に久留米~八女付近に遷宮され、
更に517年頃と617年頃に移転があった、<
>それ、原典を示してね <
「此地帝都。近気於今。在一百餘歳。一百年竟。遷京北方。在三百年之後。」
『聖徳太子伝暦』推古二五年条
>>726 大理からハノイに行く道は誰が見ても南東なのに
関係ない昆明が「東~東南東」方向だから
という、わけのわからない理由で
「ほぼ東」なのだ
旧唐書は、方向を間違えていない
と言い張る神経がわからない
>>627 >>不彌國から一旦玄界灘へ出て、<
>それだと出発方向の西なり東なりの方角が書かれなきゃいけないんじゃないのか?
ザラコク理論では そういって伊都国の南東が間違ってないっていってたんだから<
いや、「出発+途中+到着」の書き分けは、
魏使らの「実際の移動があった行程記録」に於いて、であり、
投馬國は、途中移動が書かれておらず、魏使らの移動がないような「位置情報」説明、
であるから、
出発の記載をする必要がない。
>>740 >「邪靡堆」は、単独の孤立的史料事実であって、
>そういう認識での受け止め方をすべきであり、
>安易にそれを「間違いだ」とはすべきではない、という事。
単独の孤立的史料事実は
鵜呑みにすべきでない、というのが
世間の常識なんだがな。
>>628 >>何度も説明している。
「服=服従する」は自動詞的文字であり、
「衆夷六十六國は既に服属している」であり、<
>うそ 「以力服人者、非心服也」(孟子)<
?。何が言いたいの?。
その例でも、「服」は自動詞的な意味での使用だよ。
「力を以って人を服するは、心から服するに非ざるなり」。
>>742 >『聖徳太子伝暦』
はいはい、典拠を示せたのは進歩だけど、それ信用の置ける歴史書でないから
10世紀成立で、それまでの太子信仰を集大成したものだね
ブリタニカ国際大百科事典 より
「その記事は必ずしも『信をおきがたい』が,後世の太子信仰に及ぼした影響はきわめて大きい。」
九州説の出してくるものって、こんなんばっかだな
「松野氏姫氏系図」とかさ
>>632 >>「征=征伐する」や「平=平定する」はいずれも他動詞であったが、
「服=服属する」は元来自動詞であるから、
「西の衆夷六十六國は以前に服属している」という意味になり、
「六十六國」は、九州付近全域になり、
当然、その中に西九州も含む事になる。<
>九州の西に「六十六國」は入らないことは認めるんだな?
その時点で、倭王武は九州王朝じゃないぞww<
認めない。
倭国は、以前に、九州付近全域での支配を終わっていたことになる。
>>746 >?。何が言いたいの?。
いや、何がいいたいのか分かってないのはザラコクだろ?
>その例でも、「服」は自動詞的な意味での使用だよ。
自動詞「的」な意味とかないから
目的語があれば他動詞、なければ自動詞だぞ
>「力を以って人を服するは、心から服するに非ざるなり」。
そして、この場合
「人を」服する
の「人を」が目的語なんだから、ものすごく分かりやすい、
他動詞であることの例示じゃないか
漢文が本当に読めないのに、どうして嘘解釈を書いては恥をかくのかなぁ
本当にザラコクの価値観は、一般の日本人とは違うわ
>>748 >認めない。
ザラコクが認めないっていっても、
オオハツセ「ワカタケル」の音訳の「獲加多支鹵大王」を
金錯銘あるいは銀錯銘した鉄剣が、埼玉と熊本から出ているんだから、
熊本まで「獲加多支鹵大王」の勢力圏だろう
>倭国は、以前に、九州付近全域での支配を終わっていたことになる。
終わっていたところで、倭国の中心の都よりも東の国を
「西」服衆夷六十六國とは書かないだろ
倭の五王を九州王朝だと言い張るのは、どうやっても無理なんだよ
まあ、儒教道徳の徒としては、九州説創始者の古田説を曲げることは
できないんだろうけれど、それは歴史の真実とは何の関係もないよ
>>644の訂正
紀元前には「天皇」なんてなかったし、
列島住民は、元々ほぼ全て「血のつながり」がある。
>>743 >関係ない昆明が「東~東南東」方向だから
しかも、昆明であっても、東南東よりも南の南東なんだぜ
どうやっても無理なことを、「魏志倭人伝の方角が一切間違いない」と
言いたいためだけで、ごねて嘘を書き続けているのがザラコク
>>751 >紀元前には「天皇」なんてなかったし、
天皇号はなかったけれど、天皇につながる家系というか血統は
3世紀には成立してただろ
それを後付で天皇と呼んでいるだけだよ
まあ、「論証抜きでひと言書くだけ」の能力しかないザラコクさんには
理解できないかなww
>>753 >天皇号はなかったけれど、天皇につながる家系というか血統は
>3世紀には成立してただろ
邪馬台国とは関係ないだろ。
>>656 >>いずれにしても、水俣の有機水銀と同じく、
微量の摂取の蓄積が神経毒になっていくんだろうなあ。<
>ならねぇよ 水に不溶ってことは、人体に入らないってことだ
消化管の中は人体の外だからな<
元々、無機水銀であっても水銀化合物であっても、
そのままでも体液との接触がれば、組織内侵入が有り得、
細胞との接触があれば、ファゴサイトージスも起こり得る。
更に、経皮でも肺でも消化管でも、
体液との接触がある限り有機水銀化する事も事も当然あり得る。
>イオン化しても、原子核の崩壊確率は変わらないっていう単純なことすら
理解できないんだから<
この男も、
場の相互作用に拠って、全ての原子核にも崩壊半減期が必ず存在する、
という単純な事が判らない アホなんだから。
>>657 >問題は、倭王武の本拠地が、 元々西の66国の中にある、ってことだ。<
>はい、この時点で、漢文の読み方として破綻しています<
破綻していません。
倭王武は、「東征」や「渡平海北」の他動詞と、「西服衆夷」の自動詞とを、
きちんと書き分けている。
>つまり、倭王武が九州王朝の王であることを自ら否定ww <
否定していない。
倭国は、魏志から唐会要の「正北抵新羅」の証言に拠って、
新羅のほぼ真南の九州である事になり、
大和は、魏志の「倭種」の書き分けや、「南≠東」などに拠って、
倭国であった事が否定される。
>>659 >>一支國→竹斯國は、肉眼で見えていて、記載する必要がなかった。<
>対馬から壱岐も、壱岐から筑紫も肉眼で見えてるんだよ<
対馬→壱岐は、海岸での目の高さでは水平線の下になってしまって全く見えないし、
後ろの山に登っても年に数回かろうじて見える程度で、殆ど見えない。
>でも、魏志倭人伝ではいちいち南って書いてあるよな?<
魏志では、「狗邪韓國→對海國」と「一大國→末盧國 」には方向を書いておらず、
「對海國→一大國」は、見えないから、東南とは書けず、
出航時の「南」に向かって進む事の記載だけ。
>肉眼で見えるかどうかは、史書を読む人には関係ない
途中で方向転換が記載していなければ、読む人に地理は伝わらない <
見えれば、それに向かって行けばよいので、出発方向を記録する必要もないが、
見えなければ、出発方向を記録して残しておかなければ、
次の使節は当然遭難してしまう。
>だから、末慮国ー伊都国間も海岸沿いだから出発方向だけでいいなんていうのは
ありえない暴論 <
末盧國からも、途中に山があって目的地を確認が全くのように出来ないんだから、
出発の方向を示して、後は案内人や道標な道なり道に従って進むしかない。
>>758 現地を知らないでデタラメ言ってるでしょ
>>661 >>道遥百濟、裝治船舫 <
>まさか、ここの「道」一字で陸行だって主張してるのか?
「海道」って言葉知ってるか?<
倭王武は、「句麗無道」の説明をしようとしているのであり、
「海道」の道では、高句麗の 無道の影響を受けないから関係がなく、
陸路である事を示す。
>裝治船舫って書いてあるのは無視か? 船でどうやって百済を陸行するんだよ?<
裝治船舫は、百済の西海岸(おそらく牙山湾の入り口にある唐津の町)で、
南宋への大渡海の準備や装置を揃えておく事。
>>757 >倭王武は、「東征」や「渡平海北」の他動詞と、「西服衆夷」の自動詞とを、
>きちんと書き分けている。
「西服衆夷」の自動詞?
動詞「服」の目的語は「衆夷」だよね ?
>>665 >東征毛人五十五國 西服衆夷六十六國 これって自分が中央だって意識そのものでしょ
倭王武の本拠地の本拠は西でも東でもない <
いや、(東とは違って)「西」は以前に既に服属していた事を示すから、倭国の位置は西であった事になり、
更に「西」の九州であったから「渡平海北」とも書けた。
>>668 >邪馬台国はヒメやトヨが住んだ葛城。<
記紀や大和文書は、倭國の存在や歴史を隠蔽しようとしたきゃ主観的な半分×書であり、
客観性や信頼性の高い中国史書群の説明と一致しない部分は、根拠になりません。
そして、「邪馬台国はヒメやトヨが住んだ葛城」説は、「南≠東」に拠って×。
>>669 >670年なら、 唐会要倭國伝の「倭國使が日本国を名乗った」記録の年でもあるし、<
>これも全くのウソ
唐会要倭國伝で670年には「倭國使が日本国を名乗った」りしていない<
唐会要倭国伝:
「咸亨元年(670年)三月、遣使賀平高麗。爾後継來朝貢。
則天時、自言「其國近日所出、故號日本國。」蓋惡其名不雅而改之。」
新唐書日本伝:
「咸亨元年、遣使賀平高麗。後稍習夏音、惡倭名、更號日本。
使者自言、國近日所出、以爲名。或云日本乃小國、爲倭所并、故冒其號」
だから、そのまま受け止めれば、
咸亨元年には、倭国使節と日本使節とがどちらも唐へ遣使を派遣して、
どちらもが「日本国」を名乗り、
倭國の方は、則天の時に再度日本国を名乗った、
という事になる。
>>755 >邪馬台国とは関係ないだろ。
そう思いたいんだね
個人の思想信条の自由は認められているから
いい国だろ
>>756 >全ての原子核にも崩壊半減期が必ず存在する、
本当に理解してない返事だよなぁ
その各「核種に固有の崩壊半減期は、「原子核外の電子軌道上の状況には、
一切影響されない」っていってるんだよ
二重投稿ごめん
>>756 >全ての原子核にも崩壊半減期が必ず存在する、
本当に理解してない返事だよなぁ
その各「核種に固有」の崩壊半減期は、「原子核外の電子軌道上の状況には、
一切影響されない」って言ってるんだよ
>>763 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよ法螺谷法螺男。
>>760 >倭王武は、「句麗無道」の説明をしようとしているのであり、
>「海道」の道では、高句麗の 無道の影響を受けないから関係がなく、
>陸路である事を示す。
ザラコクは何を言ってるんだ
臣雖下愚忝胤先緒驅率所統歸崇天極「道」遥百濟裝治船舫
而句驪無「道」圖欲見呑掠抄邊隷虔劉不已
こっちが言ってるのは1行目の「道」
ザラコクの言ってるのは2行目の「道」
本当に見当違いな、何の言い訳にもならないことを書いてるだけ
船で陸路を行く訳がないだろ!
「道」遥百濟裝治船舫は
道百濟を遥(へ)て、船舫を裝治す。
当然に、道は「海道」、海路だよ
>>670 「南≠東」だから、倭國は九州にあり、つまり九州倭国(=九州王朝)は存在し、
大和は、倭國から別れた別種の旧小国であって、白村江の後で、倭国を併合吸収継承したんだから、
それまで九州王朝が存在した事になり、
拠って、「九州王朝は始めからない」といったこの大和説男は、
始めから嘘つき騙しの×人種。
>>770 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
早く言えよおまえ。
>>764 >だから、そのまま受け止めれば、
>咸亨元年には、倭国使節と日本使節とがどちらも唐へ遣使を派遣して、
>どちらもが「日本国」を名乗り、
>倭國の方は、則天の時に再度日本国を名乗った、
>という事になる。
いや、そのまま受け取れば、咸亨元年に来た使節が
日本国と倭国の二通りの書き方をされてるってだけだよ
>>770 >九州倭国(=九州王朝)は存在し、
九州王朝なんてない
拠って始めから×
>>673 >>大理にほぼくっついている北の「ジ海」から流れ出す河は、下流をたどれば、
メコン川(やメナム川?)方面に下っているぞ?。<
>ザラコクの大好きな猫頭山の東側を流れている川をたどってごらん<
私の見ている地図では、ソンホン川?の上流は、「ジ海」には達していないし、
大理と陽苴城や太和城の位置関係もはっきりしないし、
3000以上の猫頭山や1000mをはるかに越える無量山脈越えのルートでは、
急峻な峠道があるだけで、
「通水陸行」出来るようなルートが存在出来る筈もない。
>>675 >>(陽苴城から安南へは)東へ「 如至成都,通水陸行」すれば至る<
>成都に向かうのは「『東北』至成都二千四百里」と書いてあるとおり、東北で
東へ向かうのは「如至成都」にならない <
「如至成都」とは、「成都へ至るのと同じような通路で」という意味であり、
「通水陸行」路の状態を示しているのであり、
別に東北へ行け、とか、2400里行け、とかなど書かれていない。
>「通水陸行」は「東至安南」にしかかからず、成都は無関係<
当たり前。
「如至成都」は「通水陸行」路の説明だ、と言って来た。
だから、この男は、また、私の文を、
「曲解捏造してその捏造文に対して私を誹謗する」
という悪質なヘイトスピーチの詐欺宣伝をしている事になる。
>「如至成都」は、大理から安南までの距離<
そんな事は、どこにも書かれていないし、これもこの・・・・男の詐欺。
>>679 >>旧唐書は、
「陽苴咩城,南去太和城十餘里,東北至成都二千四百里,東至安南 如至成都,通水陸行」
と書いたのだから、 安南へは、方向が「東南~東南東」であっても、
東へ「 如至成都,通水陸行」すれば至る、 と書いた、という事だ。<
>つまり旧唐書は方位を間違って書いてるんだよね <
間違っていない。
東南へ直行したら、
まず急峻な山道の長距離の上り下りの繰り返しになってしまい、
「通水陸行」には全くならないが、
東へ「通水陸行」すれば、道なりに安南に行ける。
>東に行ったら絶対に安南には着かないのだから <
「通水陸行」の道なりで着ける。
>>776 >「通水陸行」の道なりで着ける。
「道なりで行くときは、出発方向で示す」ってザラコク自身が書いてたよな!
大理から出発するときは、「南」方向だぞ!
通水陸行する部分だけなら、どのルートでもソンホン川沿いの部分だけだから、
それこそ「南東」にしかならない
>>679 >>「水などの貯蔵用の容器」であればよかったのであり、<
>そういう用途には桶をつかうよ 軽量で運びやすく、<
小さくては、雨水も蓄えられず、枯渇すれば死が待っている。
>素焼甕のように水が漏らず、割れない<
桶では、それなりに、緻密な保水構造にしなければならず、
倭人の「沢山の瓢箪をぶら下げて新羅王になった」人のように、
緻密な一重な構造のものが必要になる。
>>683 >太和城も陽苴咩城も大理市内なんだよ
だって、5キロしか離れてないんだから<
旧唐書は、太和城と陽苴咩城とをはっきり区別した記載をしているんだから、
大理全体ではなく、陽苴咩城に絞った話にしないと×だよ。
>>774 >私の見ている地図では、ソンホン川?の上流は、「ジ海」には達していないし
地図の見方が悪いだけ
ソンホン川が洱海から流れ出ているなんて誰も言っていない
現在の大理市内にソンホン川の源流があると言っている
源流の位置は
>>731、
>>738に書いてあるから、
地図で確認しなさい
>大理と陽苴城や太和城の位置関係もはっきりしないし、
はっきりしてるんだよ!
日本語でググっても十分な情報に行き着くぞ
ごまかすな!
>3000以上の猫頭山や1000mをはるかに越える無量山脈越えのルートでは、
そんなルートは取りません
ソンホン川はその山の東側を流れ下っているんだよ
川沿いに行けばずっと下り坂だって理解できるか?
川は坂を登らないからな
>「通水陸行」出来るようなルートが存在出来る筈もない。
水行になるのはソンホン川が現在の中国、ベトナム国境を越えたあたりから
昆明までに水行する部分はない
根拠のないことを書いてごまかそうとしても無駄だよ
百回書いても嘘は嘘だ
畿内説も日本史板もおわってるな。
基地外ばっかり集まってくる。
類が友をってやつか
>>684 >なんで遠回りするの?<
東南直行ルートでは、3000m以上の山や、
1000mをはるかに越える峠越えの獣道のようなジグザグ道になって、
結局、時間も距離も労力も非常にかかってしまって、
東方向の普通の山川道の「通水陸行」の方が、楽にいけるから。
>>775
>「如至成都」とは、「成都へ至るのと同じような通路で」という意味であり、
>「通水陸行」路の状態を示しているのであり、
いいえ違います
何度も書くが、「如至成都」は距離
距離が書いてなかったら地理情報として無意味
成都に行くのにどのルートをとっても、「水行」できる部分はない
方角 目的地 距離 おまけ
「南去」 太和城 十餘里
「東北至」 成都 二千四百里
「東至」 安南 如至成都 通水陸行
こうやって並べれば「如至成都」が距離だって分かるだろう
>別に東北へ行け、とか、2400里行け、とかなど書かれていない。
だから漢文が読めてないって言ってるんだよ
陽苴?城から見て、東北に2400里で成都に至るっていう意味
>「如至成都」は「通水陸行」路の説明だ、と言って来た。
だから、そんな解釈はない
ザラコクの誤読または捏造
>悪質なヘイトスピーチ
ヘイトスピーチって言葉を使うのは、「市民(≠日本国民)」だって相場が決まってるんだが
お里が知れるな
だから、起源にこだわるんだろ? >>779 >倭人の「沢山の瓢箪をぶら下げて新羅王になった」人のように
そうだよ!
土器よりもひょうたんの方が便利なんだよ!
縄文土器を持ち運ぶ理由はないな!
>>780 >旧唐書は、太和城と陽苴?城とをはっきり区別した記載をしているんだから、
>大理全体ではなく、陽苴?城に絞った話にしないと×だよ。
区別してるだろ?
ザラコクが、地図の見方が分からないだけで?
ザラコク以外はみんな理解してるぞ、ザラコクが間違ってるって
旧唐書のこの方角、「東」は「南東」の間違いなんだよ
どうへ理屈を捏ねても無駄
さすがに南寧は持ち出さなくなったな
その分も「ごめんなさい」が言えるといいんだけど、ザラコクでは無理だろうな
>>782 >畿内説も日本史板もおわってるな。
>基地外ばっかり集まってくる。
>類が友をってやつか
まあ、今どきの九州説には、「一種類」しかいないのはしょうがない
>>773 >九州王朝なんてない
>拠って始めから×
根拠は?
>>770 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよおまえ!
>>788 畿内の大王級古墳の石棺に九州の石材(阿蘇のピンク石)が使われていること
>>788 日本書紀、古事記に記載の位置に、宮都遺跡があること
>>788 「九州王朝があった」ことを示すと九州説が主張する「根拠」に
「偽書」や「妄想」しかないこと
>>687 >>旧唐書時代には、陽苴咩城と太和城があって、陽苴咩城の場所の話をしているんだから、
陽苴咩城の位置説明が問題。<
>どっちにしろ洱海の西岸にあるんだから<
根拠は?。
>>688 >そして、地図を確認すれば分かることだが成都に行くときこそ、昆明を通ることになる、<
「昆明を通って成都に行く」なんて書かれていない。
「東北至成都二千四百里 」は、単なる位置情報。
「如至成都」は「通水陸行」路の状況説明。
>でも、成都へは「東北」と直線方向が書かれていることが分かる<
位置説明。
>安南へも直線方向なんだよ <
直線方向だなんて、書かれていない。
安南は、東へ「通水陸行」して行ける、と書かれているだけで、
そのルートは「如至成都」のようだ、という移動方向説明であり、
昆明方向が大体東であるから、「東至安南」で間違っていない。
東南直行移動では、3000mを超える山脈越えになり、「通水陸行」にならない。
>>797 >昆明方向が大体東であるか
昆明を通るんだという根拠は?
それが無いと話にならないんだが
>>701 >(スレ主)纒向遺跡の発掘状況等から、
ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、<
「西日本の広域に影響力」が間違い。
単に、「九州倭國の東征軍の存在と市があった」だけ。
そして「宗教的指導者」も間違い。「市」の祭祀があっただけ。
>それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ女性であった
と考えられる。<
「共立」とか「女性」とかの、卑弥呼や壹與を匂わしているのは、
「南≠東」に拠って×。
これについて、文句ある奴は手を挙げて文句を言え。
>>799 >これについて、文句ある奴は手を挙げて文句を言え。
理由が書いてない
>>712 >>竹島からまっすぐ東に向かって、都斯麻國には寄らかったから、
(東のままで)一支國に着いた。<
>その論理だったら、都斯麻國の「前」に東って書かれなきゃいけないって
分からないんだろうな、ザラコクだから <
東に直進する途中で都斯麻國があるのが見え、
寄らずに「經」して通り過ぎて東に直進して、一支國に至った。
>>714 >>「南=東」の確率は、ほぼ0%であり、<
>「ほぼ」? ずいぶん軟化したなww そろそろ自信がなくなってきたのか?ww
まあ、ザラコクが何を言っても現実や真実とは関係ないんだけどな <
「南=東」の確率は、ほぼ0%である、っていう事が、
「南≠東」は×、って意味だよ。
>>715 >>「ジ海」の南岸付近から、安南への「通水陸行」道は、東の昆明方向しか残っていない、<
>だから、バカ扱いされるんだよ 洱海の南岸ら辺にあるのが、「太和城」
今問題にしている「陽苴咩城」は、もっと北で洱海の西岸にあるんだよ
だから東にいこうと思うと洱海に突っ込むことになるww<
「陽苴咩城は、もっと北で洱海の西岸」の根拠は、
この715投稿時点では、まだ聞いていない。
また、西岸であれば、ジ海の横断が通水であった、という可能性もある。
方向を間違えない確率こそゼロですよ。
間違えている実例なら過去沢山存在してますから。
>>802 で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよこの老いぼれウソブキ法螺貝。
>>701 間違いとまでは言いませんが
日本書紀を参照していることを明記しないところは、詐欺的な手法と言えるでしょうね。
巻向遺跡を考古学的に調べても「女性」の要素はでてきていませんから。
>>716 >>私の見た地図では「ジ海」はメコン川方面に繋がっていて、
安南方面に繋がっているようには見えなかったが。<
>ソンホン川だって何度も書いてるだろ それは別の川
本当にザラコクの相手は大変 <
ソンホン川やジ海で検索しても、
ソンホン川の源は雲南省とあるだけで、
ジ海から流れて来た、って、全く書かれていないよ。
>>796 >根拠は?
羊苴咩城 Wikiwand
羊苴咩城,又稱「陽苴口芊城」、「陽苴咩城」、「苴咩城」,位於今天的雲南省大理白族自治州大理市。「城池遺址在今大理古城及其以西地區」。北至桃溪南岸,南至綠玉溪北岸一帶。
あと「中国西南民族史」っていう名古屋大学のおそらく講義用のパワポスライドの
pdfが見られるから、そこの図で確認しなさい
http://ocw.nagoya-u.jp/files/15/s07.pdf >>806 詐欺師岡上久々の登場
明記してあることを明記しないと書き、他人を詐欺的呼ばわりする本格詐欺師
w
■纒向遺跡の発掘状況から、ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ人物であったと考えられる。
これなら誠実で、好感持てますね。
もしくはこれか。
■纒向遺跡の発掘状況、及び日本書紀を参照すると、ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ女性であったと考えられる。
>>807 ジ海から流れて来た、って、誰も言っていないよ。
>>701
纏向遺跡のどこに特筆すべき考古価値があるの?
遺跡範囲が広いとか? 各地の土器があるとか? 柱跡があるとか?
それって特別なことなのかね? @阿波 >>803 >「陽苴咩城は、もっと北で洱海の西岸」の根拠は、
>この715投稿時点では、まだ聞いていない。
だいぶ前から
「南去太和城十餘里」
と書かれているけど?
2013年のあの日以来、小汚く年老いた奈良の自称考古学者が、優秀な若い古代研究家たちに、無茶な自説をゴリ押すための工作やパワーハラスメントを仕掛けることが多くなってきたが、良識ある若者たちは結束して、真実を次世代に伝えようとしている。。。
すなわち、巻向は邪馬台国とは無関係であると、、、
>>764 >だから、そのまま受け止めれば、
>咸亨元年には、倭国使節と日本使節とがどちらも唐へ遣使を派遣して、
>どちらもが「日本国」を名乗り、
咸亨元年に誰かが「日本国」を名乗った
なんて史料事実はありませんが?
まあ邪馬台国とは畿内、信貴山中心とした
河内湖から奈良盆地へまたがる場所を指します。
銅鐸についても古代エジプトの神由来の物だと
説明が出来ると思いますよ。
>>717 >>「東至安南如至成都通水陸行」も安南の位置説明であり、<
>これがそもそも間違い 安南(もちろん成都も)はみんな知ってるから、
それを基準にした「陽苴咩城」の位置説明なんだよ<
「陽苴咩城」と安南との位置関係を「通水陸行」コースで説明したもの。
>>筆者は(行程や旅程などのような)実際の安南への移動、
を説明、しているんではないんだよ。<
>でも、移動するときの経路は説明しているんだよ 昆明なんかは関係ない
南寧はもっと関係ない <
でも、「東方向へ通水陸行」すれば、昆明や南寧方面へ向かうんだよ。
>>819 >でも、「東方向へ通水陸行」すれば、昆明や南寧方面へ向かうんだよ。
つまり安南に着かないから、旧唐書が書いた方位は間違ってるんだね?
>>819 >「陽苴咩城」と安南との位置関係を「通水陸行」コースで説明したもの。
そして「陽苴咩城」と「安南」との位置関係は西北→東南だから
旧唐書は方角を間違ってるわけだ
>>719 >>倭人伝のも、淮南子や山海経からの転記になっていないし、
そんな事がバレたら、魏使らの首が危ないんだし・・・<
>相変わらずザラコクはバカだなあ
転記って言ってるけど、そのまま写したって話じゃないぞ<
お前は、淮南子などの情報を、「裸國と黒歯國だけを転写」して?誤魔化した、
かのような言い方をした。
>倭人は珠儒国・裸国・黒歯国など知らないって話
これの元ねたは「大陸側」にしかないんだよ<
勿論、「珠儒国・裸国・黒歯国」は、魏使らが確認した実国名ではない。
倭人側の「形態的なの説明」を元にして魏志らが形容した「国名」。
>そして、魏志倭人伝に「珠儒国・裸国・黒歯国」を書いたのは陳寿
魏使の報告書にはそんなことはひと言も書いてない <
変な・・・・男。
陳寿も、魏使らの記録がなければ、珠儒国・裸国・黒歯国なんて国名を記載出来る筈がない。
.
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
早く言えよウソブキ老人!
>>720 >>安南への「通水陸行」道は、東の昆明方向しか残っていない、<
>まだ言ってる 位置説明だから、直線方向なんだってば
でなければ、成都が北西にならないだろ?<
「成都が北西」は、「通水陸行」などの道のり説明がないから、単純な位置説明。
「東至安南」は、「通水陸行」と書かれているから、
「東への通水陸行」という移動方法での位置説明。
>>723 始めから、旧唐書のその部分は、三つとも位置説明である、と言っており、
「東至安南」の部分だけが「如至成都」の「通水陸行」の移動説明を伴っている、
という説明をしていた筈だ。
だから、「東」は、東の昆明方面への「通水陸行」路を採る説明をしており、
「東」で間違いがなく、「東南直線方向だ」と解釈したのが間違い。
だから、旧唐書も東西南北の方向間違いをした、という証拠などなく、
末盧國からの出発時点での「東南」も、「東北の間違いだ」という事にはならないし、
「南→東」にもならず、
大和説は×。
>>725の小訂正
「南→東」などの史料事実を否定曲解する嘘つき騙しの・・・・大和説男は、
不可知部分が殆どである自然や歴史においては、
孤立的な情報が幾らでも有り得て、 そのそれぞれが存在の事実証拠になる、
という事が理解出来ず、 結局は議論に負けて、
誹謗中傷のヘイトスピーチを世間の人々に宣伝して、逃げました。
九州王朝説というか、大阪で結成された筑紫シンラ王朝説だよな
最近は欲が出て完全な韓国起源説になってるけど
また
>>726の部分訂正
いや「通水陸行」は途中の状況であって、出発の方向を意味しない。
>>797 >位置説明。
>直線方向だなんて、書かれていない。
おいおい、自分の書いたこれとの整合性はどうなってるんだ?
Part330の624のザラコクの書き込み
「始度一海千餘里至對海國 :出発「始度一海」、途中「千餘里」
又南渡一海千餘里(名曰瀚海)至一大國:出発「又南渡一海」、途中「 千餘里名曰瀚海」
又渡一海千餘里至末盧國」:出発「 又渡一海」、途中「千餘里」
東南陸行五百里到伊都國 :出発「東南」、途中「陸行五百里」
東南至奴國百里:途中移動の記載無しだから、東南は方向位置説明。
東行至不彌國百里:出発「東」、途中「行」
南至投馬國水行二十日 :途中移動の記載無しだから、「南」は方向位置説明。
南至邪馬壹國(女王之所都)水行十日陸行一月 :途中移動の記載無しだから移動は無しでは「東」は方向位置説明。」
このザラコク理論の定義に従えば「方位至」と「到着」の間に文字がなければ「方向位置説明」何だろ?
そして、今問題のところは
「東至」「安南」如至成都通水陸行
となっていて、間に一文字もないから「方向位置説明」なんだよな?
そして、「方向位置説明」は側副傍線経路だから、直線方向で示してあるんだよな?
奴国の説明でそう言ってただろ?
つまりは、ザラコク理論wwだと、大理から安南へは直線東方向でなければならない訳だ
でも、南東ww
確実に間違ってるんだよ
ザラコク理論どおりに解釈してもなww
>>797 >安南は、東へ「通水陸行」して行ける、と書かれているだけで、
まず「東」へ移動したら、安南には着かない
こう書かれている時点で、「方角は間違い」だ
実際、安南へ行くのは、ソンホン川が太くなってからは水行になるので
通水陸行で行くことになるのは正しい
>そのルートは「如至成都」のようだ、という移動方向説明であり、
そのルートの「距離」は「如至成都」のようだ、という意味
成都に行くルートに、水行区間はない
移動方向説明などという概念はない
>>797 >昆明方向が大体東であるから、「東至安南」で間違っていない。
昆明方向も南東
「大体東」が間違い
そもそも昆明は関係ない
「東至安南」は間違い
「東南至安南」が正しい
>東南直行移動では、3000mを超える山脈越えになり、「通水陸行」にならない。
山越えはしないよ
大理から南に出れば、そのままホンソン川の源流で、ザラコクの言う山脈は
横手に眺めるだけで超えるルートにならない
そもそも、「東南直線方向に安南がある」であって、
「東南直線方向に移動する」という意味ではない
>>801 >東に直進する途中で都斯麻國があるのが見え、
>寄らずに「經」して通り過ぎて東に直進して、一支國に至った。
「東に直進する途中で都斯麻國」となるためには、対馬へ向かう時点で
「東」って書いてないとだめだろ
でないと「対馬に向かって」がどちらに行けばいいのか分からないじゃないか
珍島から対馬は見えないぞww
>>802 >「南=東」の確率は、ほぼ0%である、っていう事が、
>「南≠東」は×、って意味だよ。
ほぼ0%ってことは、「可能性は残っている」んだから
「南≠東」は×、というためには、その可能性がないことを示す必要があるんだよ
そのための「根拠」と「論証」が必要
いつも書いてるだろ
「大陸史書の方角が間違うはずがない」は論理学的に「偽」だ
「論証なしの南≠東」は意味がないって
ちゃんとした論証があるなら、「南≠東」を主張しても構わないが
これまでのザラコクの「根拠」は
「大陸史書の方角が間違うはずがない」だけだからな
そして、これは論理学的に「偽」なんだから、使えないってこと
>>803 >「陽苴咩城は、もっと北で洱海の西岸」の根拠は、
>この715投稿時点では、まだ聞いていない。
聞いてないっていうか、自分でちょっとぐぐればすぐに出てくるだろう?
そういう確認一つしないで議論に参加するなっていってるんだよ
>>803 >また、西岸であれば、ジ海の横断が通水であった、という可能性もある。
洱海を横断する理由がない
洱海の東側には、町も道もないからな
可能性はない
それから、「通水」という切れ方はない
水行と陸行を、合わせた語が「水陸行」
通水陸行は、「水陸行を通じ」と読む
>>807 >ジ海から流れて来た、って、全く書かれていないよ。
何度も言うが、誰もソンホン川が洱海から流れ出ているとは言っていない
自分で勝手な決め付けをして、無駄なコメントは書くな
>>819 >「陽苴咩城」と安南との位置関係を「通水陸行」コースで説明したもの。
安南との位置関係は
東至安南如至成都の部分
距離と方向を直線で計ったもの
そして、この「東」が「南東」の間違い
通水陸行は大陸内の移動で、水行が入るのが珍しいので、特記事項として
付加されているものだ
もちろん、昆明行きの道中にも成都行きの道中にも水行区間はない
>>819 >でも、「東方向へ通水陸行」すれば、昆明や南寧方面へ向かうんだよ。
向かわないし、通水陸行もしない
昆明も、南寧も無関係
嘘は何回書いても嘘
>>822 >お前は、淮南子などの情報を、「裸國と黒歯國だけを転写」して?誤魔化した、
かのような言い方をした。
また捏造している
Part331の429では
「淮南子を底本としているのは明白」
としか書いてないぞ
倭人はそんな国は知らないから、その情報の出所は大陸内にしかなくて、
そのネタ元を探せば、淮南子に行き着くっていう話だ
>勿論、「珠儒国・裸国・黒歯国」は、魏使らが確認した実国名ではない。
>倭人側の「形態的なの説明」を元にして魏志らが形容した「国名」。
倭人側が「形態的なの説明」をする訳がないだろうが
「そんな国はない」んだから
本当に、妄想乙
>陳寿も、魏使らの記録がなければ、珠儒国・裸国・黒歯国なんて国名を記載出来る筈がない。
だから、その国名は淮南子:墬形訓 にあって、東の果ての国ってことになってるから、
倭国を遠くだという表現にするために、裸国・黒歯国を出してきているんだよ
>>824 >「成都が北西」は、「通水陸行」などの道のり説明がないから、単純な位置説明。
>「東至安南」は、「通水陸行」と書かれているから、
>「東への通水陸行」という移動方法での位置説明。
この説明は
>>829にも書いたように
ザラコク理論からいっても破綻している
自分の書いたことすら覚えていられない人間が
議論に参加しようとするなって言ってるんだよ
間違ったことしか書かないし
>>733 >昆明に行くまでに水行区間はない <
揚子江と珠江のそれぞれの支流の最上流地域なので、水行区間があり得る。
>水行が混じるのはソンホン川の水行だけで「完全に南東方向」<
「ジ海」からの川は巍山や猫頭山の西を通ってメコン川方面であり、
ソンホイ川方面は、急峻な渓谷状になっているだけで、「通水陸行」路には向かない。
確率論的に倭人伝における、方角は
正確であるなんて証明する事は
不可能だからな。
根本的に何の物証もない、間違えている
実証なら後世においてまで多く存在している
から。
>>825
>始めから、旧唐書のその部分は、三つとも位置説明である、と言っており、
位置説明というなら「ザラコク理論」では直線方向になる
そして、大理から安南の直線方向は「南東」だから、「東」は間違いで確定
実際、大陸史書の地理・旅程記事は直線方向の方角と距離で示されているので
「ザラコク理論の位置説明」で解釈しないといけない
>「東至安南」の部分だけが「如至成都」の「通水陸行」の移動説明を伴っている、
という説明をしていた筈だ。
何度教えてもザラコクは理解しないが、「如至成都」の部分は距離を示す実際に地図で確認すれば分かるが、
大理ー成都間の距離と、大理ー安南間の距離は同じくらい(如至成都)だ
「通水陸行」の部分は、大陸内移動で川で水行をする区間が、ソンホン川の中下流部分のみなので、特記してある訳だ
昆明周り、成都周辺で、水行区間は一切ない
だから通水陸行が「如至成都」の説明だというのは、まったくの間違いまたは捏造
>だから、「東」は、東の昆明方面への「通水陸行」路を採る説明をしており、
だから、この一文だけでも
× 東の 昆明方向でも東南(少し北よりにはなるが)
× 昆明方面 昆明は関係ない
× 「通水陸行」路 昆明、成都付近に水行区間はない
と、間違ったことしか書いてない
>「東」で間違いがなく、「東南直線方向だ」と解釈したのが間違い。
これが、徹頭徹尾、根本から間違っていて旧唐書のこの部分は
「大理ー安南間の直線方向が『南東』なのに『東』と間違っている」が正しい解釈だ お え い 、 チ ン コ ロ は 日 本 の 掲 示 板 に 来 る な よ !
チ ン コ ロ は !
チ ン コ ロ は 日 本 の 掲 示 板 か ら 出 て け よ 。
.
またヤマとは元々は古代インド辺りから
流れてきた、ヤマ神、後の仏教における
閻魔の事である。
つまりヤマとはつまり天と同義になります。
閻魔とはそこの番人という事。
当初巨大古墳が奈良盆地に集中した理由も
わかりますね。皆天で復活したかった
という事ですよ。
>>825 >だから、旧唐書も東西南北の方向間違いをした、という証拠などなく、
嘘を百回書いても本当にはならないんだよ
何度も丁寧に解説したとおり、旧唐書の大理ー安南間の方角が間違っているのは完璧に論証済み
>末盧國からの出発時点での「東南」も、「東北の間違いだ」という事にはならないし、
そもそもこれが出発時点の方角でいいのなら、大理からの出発方向は「南南東から南」であり
さらに、「東」からはずれることになる
それに、末慮国からの出発方向を「上陸地点からの海岸沿い」などというありえないくらい恣意的なザラコク設定に従ったとしても、
当時の港は現唐津港よりも東の松浦川河口付近であり、海岸方向も東にしかならない
ザラコクの言い分を認めても、東南が東の間違いであるのは変わらない
より正確には「大陸史書の地理・旅程記事は直線方向の方角と距離で示されている」ので、「北東」であるべきところが「東南」と記されているから間違いだ
そして、隋書の「都斯麻國迥在大海中 又『東』至一支國又至竹斯國」も「南」の間違いだし、
新唐書の「其『東』海嶼中 又有邪古波邪多尼三小王」も「南」の間違い
>「南→東」にもならず、
ならない可能性は否定しないが、それには論証が必要
論証抜きの「南≠東」には何の意味もない
隋書、新唐書の例でも分かるように、大陸史書での日本周りの方角での「東」と「南」の混乱が明らかに認められる
魏志倭人伝ほかの冒頭にある「倭人在帶方『東南』大海之中」の「東南」の範囲なら適当でいいと考えられている可能性がある
>大和説は×。
九州説も、ザラコクも、九州王朝説も×
根拠は「九州王朝なんてない」から
行ってきましたという
証拠(画像)も貼り付けて、いつまで待たせるんだ
>>841 >揚子江と珠江のそれぞれの支流の最上流地域なので、水行区間があり得る。
ソンホン川でも水行するのは、下流の方の水がゆったり流れる区間だけだぞ
「支流の最上流地域」は、水量も少ないし流れも急だし、水行は不可能
昆明周辺、成都周辺で水行できる区間はない
川沿いに歩くことはできるし、流れに沿っていけば峠越えなどはないから、川沿いの陸行は交通路として重要
>「ジ海」からの川は巍山や猫頭山の西を通ってメコン川方面であり、
巍山や猫頭山の「西」じゃなくて、ソンホン川の源流は猫頭山の「東」で
巍山のある谷を流れてるんだよ
もう一つ東側の集落のある谷も、ソンホン川の源流の一つ
>ソンホイ川方面は、急峻な渓谷状になっているだけで、「通水陸行」路には向かない。
何度も書くが、ソンホン川でも水行になるのは、中越国境を過ぎたあたりから
何度も意味のないバカなことを書き続けるのはやめな
そんなに自分で主張しなくても、ザラコクはバカだってみんな知ってるから
もう今更邪馬台国の位置なんて論じてる
状況じゃないですよ。
勿論畿内周辺でしかないですから。
ざっくりいうと縄文文化が支配していた
状況に、西のエジプトやインド辺りから
中国を経て
違う文化をもたらした集団が、西日本を
中心に国を作った状態ですね。
弥生時代というのは。
大物主は西から文化を持ってきた、
物部氏の象徴という存在ですね。
>>734 >>>(昆明方面)「東~東南東」方向だから、「ほぼ東」であり<
>残念でした 昆明は関係ないし、その関係ない昆明方向ですら、南東方向
東南東じゃないよww<
この男は、以前にも、「会稽東治之東と九州」の話で、こんな嘘つきをしていたな。
・・・・人種は、もう分裂幻覚の妄想の病気なんだな。
>だからどうやっても「ほぼ東」にはならない
どうがんばっても、この部分の旧唐書の「方角は間違っている」<
「東至安南」の「通水陸行」路は、昆明方面への「ほぼ東」方向であるから、
「東は東南の間違い」にはならない。
>>735 >>隋書に書かれたように、「又東至一支國」の記載に合っており、成り立つ。<
>竹島(珍島あたり?)から東なら 「対馬の前に東」って入らないといけないんだよ<
対馬の南の「大海中」という地点を通っている事を記載しているとから、
そこから「又東至一支國」」になっている。
>>853 >「東至安南」の「通水陸行」路は、昆明方面への「ほぼ東」方向であるから、
>「東は東南の間違い」にはならない。
同じ嘘を何度書いても「嘘だ」ってそのつど書いてやるから、騙されるやつはいないよ
大理から、昆明方向へ進む場合でも、今地図で計ってきたら
方角 : 119.189° の方角だ
112.5度以上157.5度までが南東だから、しっかり南東だろ!
>>841 成程。たった今、原文と地図を確認した。誰にでも納得できる良い説明を、有難う。
>>738 >>ソンホン川は、「ジ海」に届いていない筈。<
>あと、「巍山」の隣の谷の、紅岩鎮の谷筋もホンソン川の源流だから 確認しなよ
ここは、昆明に行くにも最初に通るところだから、山越えがどうたらって
いうのは意味がないぞww <
「ジ海」自体が1000m位の高さであり、
その南側の山越えは、急峻な渓谷で、道などある筈もなく、地図に記載もされていないから、
「通水陸行」道も存在しない。
>>739 >>後代には「対馬=ツシマ」という音韻名が伝わっておれば、<
>対馬に住み続けている日本人に、対馬という音韻がずっと伝わっているぞ
この時点で、
「對海國の方が對馬國よりも「古形」であったんだ、という論理」は破綻している<
3世紀に、対馬の住民は「対馬」と書いていた、なんて情報は存在しないよ。
あったのは、「對海國」という呼称だけ。
>>741 >安易じゃなくて、同じ典拠資料によると考えられる別の書で
はっきり「邪摩堆」って書いてあるんだから、いずれかの原因で
転記ミスが生じたと考えるのが当然だろう <
後代史家らに拠る「前史書の内容説明的な書き換え」は、証拠にならないんだよ。
>>854 >対馬の南の「大海中」という地点を通っている事を記載しているとから、
また嘘をつく
対馬の「南」の大海中なんて、どこにも書いてないだろう
原文は「經都斯麻國迥在大海中 又東至一支國又至竹斯國」だ
南なんてどこにも書いてないよな
南と書いてあるのはその前の「度百濟行至竹㠀南望𨈭羅國」の部分
これは、「𨈭羅國を南に望み」だから、大海とは関係ないぞ
>そこから「又東至一支國」」になっている。
どうやっても、この「東」の基点は都斯麻國にしかならないんだって
【核弾頭】 製造していた疑惑 ≪≪ ミサイル ≫≫ 速攻削除されてる 【ネット】
http://2chb.net/r/liveplus/1521508830/l50 >>743 >大理からハノイに行く道は誰が見ても南東なのに
関係ない昆明が「東~東南東」方向だから
という、わけのわからない理由で 「ほぼ東」なのだ
旧唐書は、方向を間違えていない と言い張る神経がわからない <
旧唐書に「東至安南如至成都通水陸行」と書かれている、という事が史料事実だ。
>>857 >その南側の山越えは、急峻な渓谷で、道などある筈もなく、地図に記載もされていないから、
>「通水陸行」道も存在しない。
Yahoo!Mapでも、GoogleMapでも、十分に拡大してみれば、
大理から巍山に出る道も、大理から紅岩鎮に出る道も描いてあるよ
そして、その谷がどちらもソンホン川の源流
これで返事がなければ、ザラコクの書いたことが正しいと確定するとでも
思ってるのかね?
そして、通水陸行にあたるのはもっとずっと下流の方
繰り返し飽きずに、でたらめを書き続けるっていうのは
>>745 >単独の孤立的史料事実は鵜呑みにすべきでない、というのが 世間の常識なんだがな。<
単独の孤立的史料事実は、自然や歴史に関してに貴重な情報であり、
頭から否定抹殺にすべきでなく、
否定抹殺していればとんでもない事故が起きる、というのが
学問や科学や人類の常識なんだがな。
>>858 >3世紀に、対馬の住民は「対馬」と書いていた、なんて情報は存在しないよ。
地名っていうのは、そこに人が住み続けている限り、そうそう変化できないんだよ
人は順に生まれて死んで入れ替わっていくけれど、多くの人が生きている時間が
重なるから、そこで地名が変わる余地は少ない
対馬ももともとは、ツシマという音が先で、それに音訳で漢字を当てたのだろうが
そのときの漢字が何であったかは、対馬側の事情はほぼ関係がない
実際、隋書では都斯麻國と、万葉仮名的な表記になっている
古事記では津嶋、日本書紀では對馬嶋
對海國が古い名前だという根拠は結局はないんだな?
>>859 >後代史家らに拠る「前史書の内容説明的な書き換え」は、証拠にならないんだよ。
いやいや、隋書俀国伝の「邪靡堆」こそ、「前史書の書き換え」だろうが
>>862 >旧唐書に「東至安南如至成都通水陸行」と書かれている、という事が史料事実だ。
で、それを見ると、大理と安南の間の位置関係を示しているのに
正しい方角=「南東」ではなく、「東」という間違った方角が書かれていることが分かる訳だ
>>864 >頭から否定抹殺にすべきでなく、
演繹法っていうのは、「多数事例から共通法則を見出す方法」論であって、
たった一つの「孤立事象から、演繹的に言えることはない」って言ってるだけだよ
それはそれとして、「否定抹殺」はしていない
ただ、それを「根拠」として通用するかと言えば、通用しないって言ってるんだよ
まあ、こういう論理は、一切ザラコクには通用しないから、困っちゃうんだけどな
>>858 これも、成程である。有難う。原文を確認した。
「田川地域の自治体の文化財担当者らは一様に、丘陵を「自然の地形」として、前方後円墳との見方を明確に否定している。」
はい、終了
>>866、
>>870 どうした? ザラコク?
自演は、キウスの持ちネタだぞ?
>>862 確認済み事項だったが、有難う。記憶に効く。
.
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着した事を証明する証拠遺跡と、
その生活痕たる中国系生活土器と中国系住居と中国系耕作用農具と
中粒種のイネと漢服と木沓は?
で、呉王夫差の後裔が山門に渡来定着したとウソブいているサギサギ考古学者の
氏名と所属団体は?
さっさと言えよウソブキ老人!
753日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:28:31.14
どんどん
754日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:28:48.94
コピペ
755日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:29:17.83
貼ってよ
756日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:29:33.10
その分
邪馬台国はヤマト国、葛城山系以東の奈良盆地一帯です。邪馬台は単なる地名です。ヤマトの地が卑弥呼を共立した勢力に征伐され、都が置かれました。
纒向の外来系土器、円形周溝墓などがその証です。殉葬などそれ以前になかった風習が持ち込まれたことも、新しい別の勢力がヤマトの地を支配した傍証になります。
女王国、大和朝廷を作ったのは、出雲など山陰の勢力、尾張三河など東海の勢力、阿波、宮崎や遠賀川の石神など、縄文系勢力と縄文系勢力に半分乗っ取られた古い海神。
畿内や九州北部の渡来人系勢力はこれらの勢力に征伐されました。
757日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:29:49.54
埋める
758日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:30:04.76
手間が
遠賀川上流、赤村の巨大古墳。
奴国と関係あるのかな?
759日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:30:20.71
省ける
760日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:30:38.34
からさ
761日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:30:54.35
助かるよ
762日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:31:09.92
どうせ
763日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:33:27.84
自分の
764日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:33:45.21
考えや
765日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:34:05.79
論点なんて
766日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:34:19.85
何も
そろそろ頭の病院に行け、
お前たちの事を本気で相手にしている人なんていないから
それと肉(牛)などは
食べてはいけない事になっているんだよ
日本の話だよ
食べたいと言うのなら、天皇と言うのも必要ないし
767日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:34:35.77
なくて
768日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:34:52.56
コピペを
769日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:35:09.97
ただ
770日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:35:25.50
貼るだけ
771日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:35:43.53
なんだから
775日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:37:06.66
昔
776日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:37:22.82
誰かが
メディア(テレビなど)を観ていても、
デタラメだと気づくだろう
777日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:37:39.42
書いた
778日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:37:58.96
文章を
779日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:38:14.70
ただ
780日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:38:31.27
単に
781日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:38:52.89
コピペを
782日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:39:08.69
するだけで
783日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:39:09.52
畿内説の発狂具合が病膏肓に入っている
784日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:39:24.67
何の
785日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:39:49.43
進歩も
それと、このような曲も同じことを言っている
「聖者になんてなれないよ」
「女神なんてなれないまま」
786日本@名無史さん2018/03/17(土) 12:40:20.59
ない
言ってることが、わからない?
テイノーには、何を言っても、わからない?
♪伝説の少女に
なりたい
いつも夢見てた
一粒のシューティングスター
私の物語が
始まるの♪
『銀河』
ググると出てくる画像、あれは某徳永英明氏の曲だろう
思春期に少年から 星を眺めていた
同じような人がいるのかな、
ちなみにモレ(仮)が好きな曲、某徳永英明氏の・・・
すべて本当の話
畿内説が破綻し、自論を論破されてしまったキナイコシが、自らスレッドを埋めているな。。。
lud20241210142638caこのスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/history/1521083390/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
TOPへ TOPへ
全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000枚
新着画像
↓「邪馬台国畿内説 Part335 ->画像>8枚 」を見た人も見ています:
・邪馬台国畿内説 Part315
・邪馬台国畿内説 Part345
・邪馬台国畿内説 Part365
・邪馬台国畿内説 Part39
・邪馬台国畿内説 Part323
・邪馬台国畿内説 Part396
・邪馬台国畿内説 Part304
・邪馬台国畿内説 Part354
・邪馬台国畿内説 Part376
・邪馬台国畿内説 Part361
・邪馬台国畿内説 Part343
・邪馬台国畿内説 Part303
・邪馬台国畿内説 Part397
・邪馬台国畿内説 Part308
・邪馬台国畿内説 Part302
・邪馬台国畿内説 Part382
・邪馬台国畿内説 Part352
・邪馬台国畿内説 Part332
・邪馬台国畿内説 Part392
・邪馬台国畿内説 Part312
・邪馬台国畿内説 Part384
・邪馬台国畿内説 Part391
・邪馬台国畿内説 Part380
・邪馬台国畿内説 Part316
・邪馬台国畿内説 Part379
・邪馬台国畿内説 Part320
・邪馬台国畿内説 Part301
・邪馬台国畿内説 Part359
・邪馬台国畿内説 Part319
・邪馬台国畿内説 Part307
・邪馬台国畿内説 Part331
・邪馬台国畿内説 Part349
・邪馬台国畿内説 Part326
・邪馬台国畿内説 Part341
・邪馬台国畿内説 Part350
・邪馬台国畿内説 Part351
・邪馬台国畿内説 Part386
・邪馬台国畿内説 Part415
・邪馬台国畿内説 Part295
・邪馬台国畿内説 Part425
・邪馬台国畿内説 Part435
・邪馬台国畿内説 Part465
・邪馬台国畿内説 Part505
・邪馬台国畿内説 Part285
・邪馬台国畿内説 Part495
・邪馬台国畿内説 part1
・邪馬台国畿内説 part500
・邪馬台国畿内説 Part524
・邪馬台国畿内説 Part467
・邪馬台国畿内説 Part437
・邪馬台国畿内説 Part421
・邪馬台国畿内説 Part282
・邪馬台国畿内説 Part424
・邪馬台国畿内説 Part488
・邪馬台国畿内説 Part462
・邪馬台国畿内説 Part400
・邪馬台国畿内説 Part480
・邪馬台国畿内説 Part518
・邪馬台国畿内説 part510
・邪馬台国畿内説 Part470
・邪馬台国畿内説 Part422
・邪馬台国畿内説 Part414
・邪馬台国畿内説 Part493
・邪馬台国畿内説 Part541
・邪馬台国畿内説 Part416
00:05:41 up 25 days, 1:09, 0 users, load average: 8.25, 9.41, 10.30
in 4.1608328819275 sec
@4.1608328819275@0b7 on 020714
|



 「大和弥生社会の展開とその特質」寺澤2016
「大和弥生社会の展開とその特質」寺澤2016